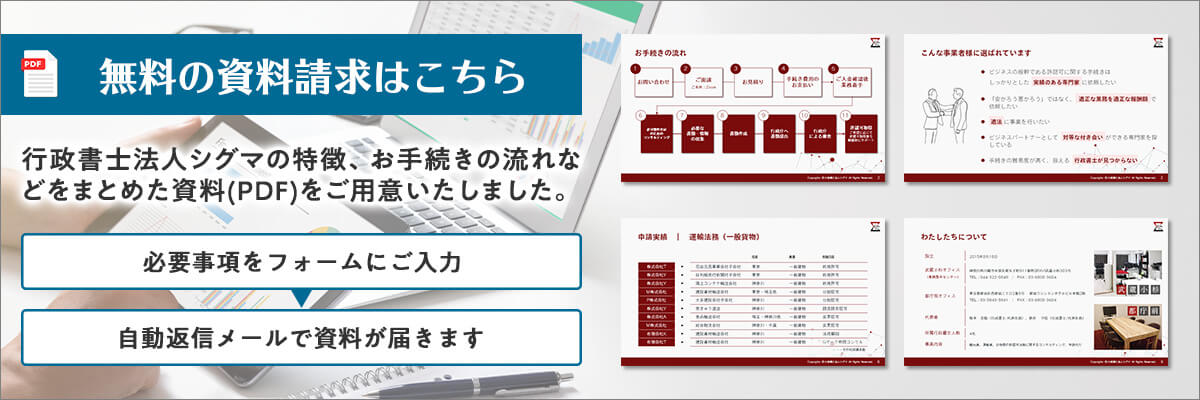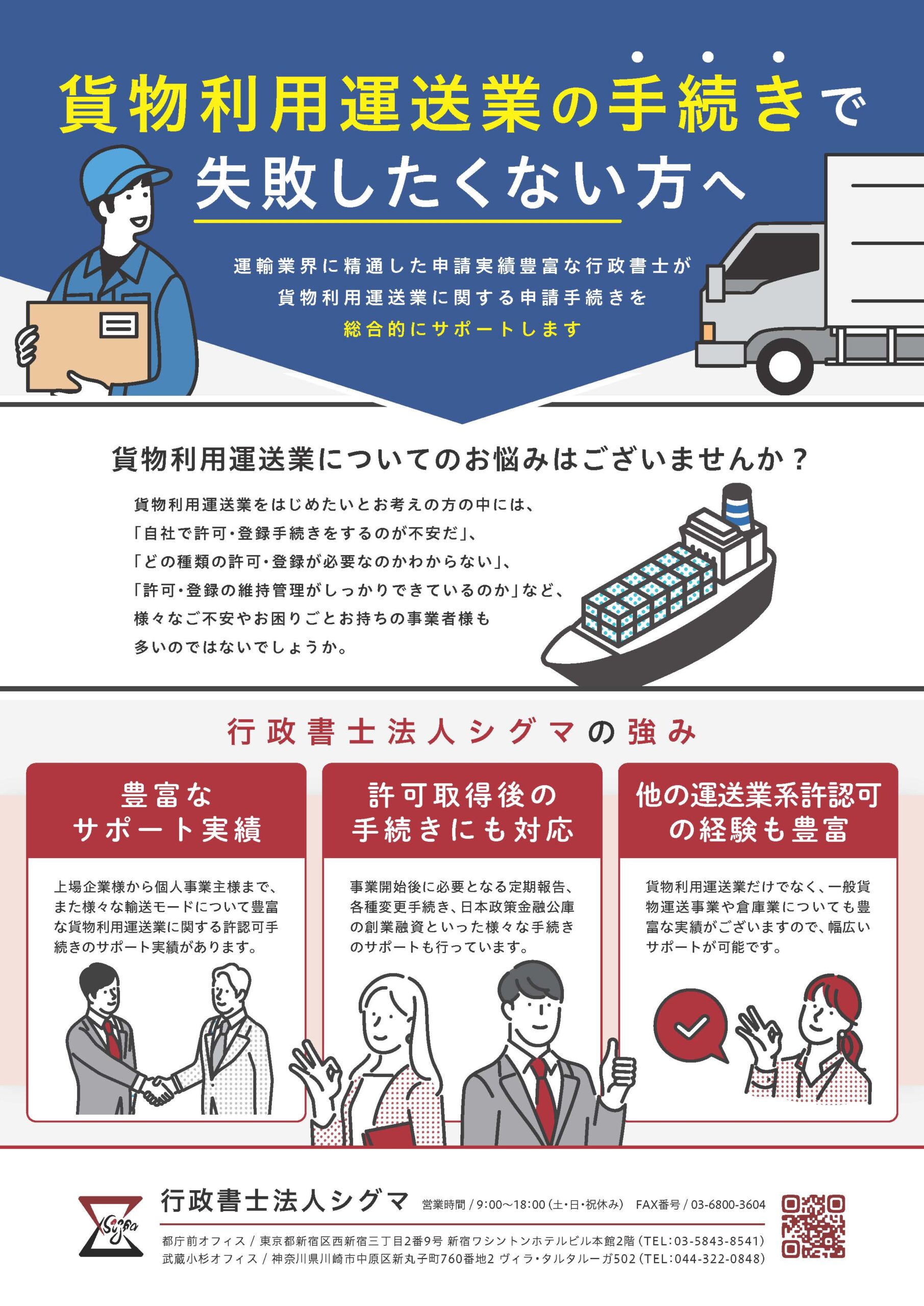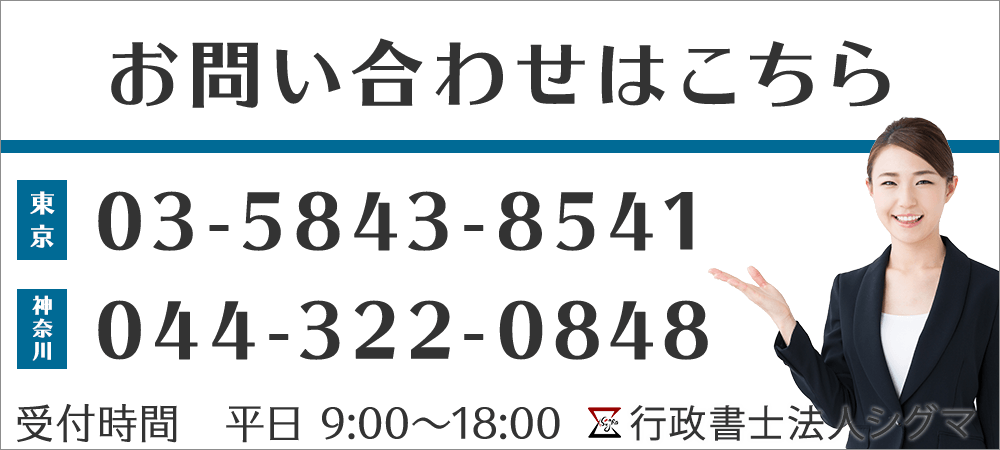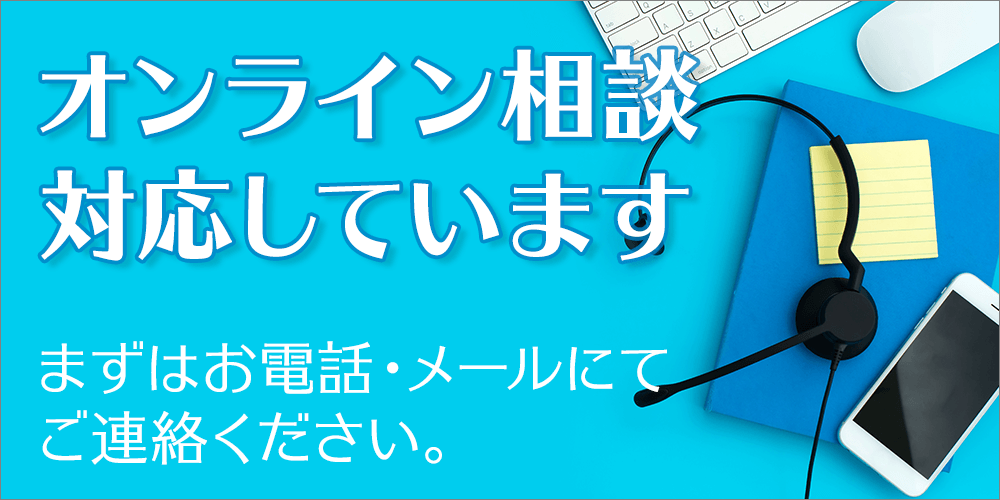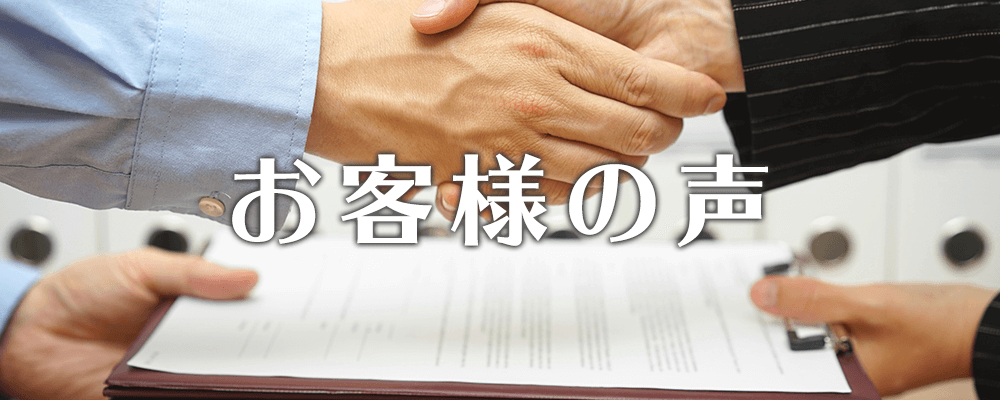今回は、運輸業に関する許認可法務分野で長年にわたり第一線で活躍し、数多くの企業の貨物利用運送事業の許認可申請を支援している行政書士の阪本浩毅氏にインタビューを行い、近年のサプライチェーン変革の中で注目される貨物利用運送業について、その実務と成功戦略を語っていただいた。
Contents
貨物利用運送事業は許認可が必要な事業です
—— 阪本さん、まずは貨物利用運送事業の基本から教えていただけますか?多くの起業家がこの分野に関心を持っていますが、法的な側面について十分理解していない方も多いようです。
阪本:はい、まず押さえておきたいのは、貨物利用運送事業が許認可事業だということです。第一種貨物利用運送事業を経営するためには国土交通大臣の登録を、第二種貨物利用運送事業を経営するためには国土交通大臣の許可を受ける必要があります。

—— 許認可が必要なのは当然のように思えますが、実際にはどうなのでしょうか?
阪本:意外かもしれませんが、必要な許認可を取得せずに事業を始めてしまうケースが少なくありません。特に近年はEC市場の拡大に伴い物流ビジネスに参入する起業家が増えており、その知識不足から必要な手続きをせずに営業してしまい、後になって荷主や金融機関から指摘を受けて慌てて対応するというケースをよく見かけます。
—— それは大変ですね。もし無許可で営業した場合、どのような罰則があるのでしょうか?
阪本:法律で明確に罰則が定められています。第一種貨物利用運送事業の登録なしに営業した場合は一年以下の懲役もしくは百万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。第二種の場合はさらに重く、三年以下の懲役もしくは三百万円以下の罰金、またはその両方が科せられることになります。2023年には首都圏で無許可営業が摘発されたケースもありましたので、決して軽視できない問題です。
—— 貨物利用運送事業の具体的な業務内容について教えていただけますか?
阪本:端的に言えば、自らが輸送手段を保有せずに他の運送事業者の運送サービスを利用して貨物の運送を行う事業です。特徴的なのは、荷主との関係では運送会社としての立場を取ることです。荷主と運送契約を結び、責任を負います。実際の運送は他の運送事業者に委託しますが、荷主に対する運送責任は貨物利用運送事業者が負うのです。これが貨物利用運送事業が許認可事業である大きな理由だと言えます。
—— 似たような業態で貨物取次事業というものもありますね。これとの違いはどこにあるのでしょうか?
阪本:良い質問です。貨物取次事業は荷主に対して運送責任を負わない点が最大の違いです。これは単に他人の依頼により、運送の取次や代弁を行う事業であり、平成15年からは規制が撤廃され、許認可なしに営業できるようになりました。実務では、この違いを理解せずにビジネスモデルを構築してしまい、後から大きな修正を迫られるケースも見受けられます。例えば、荷主との契約書で運送責任を負う内容になっているのに、貨物取次事業として営業していたというミスマッチが起きることがあります。
貨物利用運送事業の経営主体と輸送モード
—— 貨物利用運送事業は個人でも法人でも始められるのでしょうか?
阪本:法律上は個人事業主でも法人でも貨物利用運送事業の許認可を取得することができます。ただ、実態としては圧倒的に法人が多いです。私どもにご相談いただくケースもほとんどが法人ですし、関東運輸局が公開している登録事業者一覧を見ても、個人で登録を取得される方は非常に少数です。
—— なぜ法人が多いのでしょうか?
阪本:いくつか理由があります。まず資金面で、最低でも純資産300万円以上が要件となりますので、個人事業では難しい場合があります。また、荷主企業との取引においても法人であることが求められるケースが多いですね。さらには、事業の拡大を見据えた場合や物流パートナーとの契約関係を構築する上でも、法人形態の方が有利に働くことが多いです。
貨物利用運送機関の検討
—— では具体的に、貨物利用運送事業を始める場合のステップを教えていただけますか?
阪本:まず最初に検討すべきは、どのような手段を利用して運送サービスを提供するかです。これが事業の骨組みになりますので、ここからスタートする必要があります。
—— 具体的にはどのような選択肢があるのでしょうか?
阪本:例えば国内での運送サービスであれば、トラックのみを利用するのか、それとも内航船舶、鉄道、航空機なども組み合わせるのかといった検討が必要です。最近ではカーボンニュートラルの観点から鉄道や船舶を活用するモーダルシフトの流れもありますので、環境配慮型の輸送手段を選択することで付加価値を高められる可能性もあります。
国際物流サービスの場合は、コンテナ船などを使用した海上貨物輸送を提供するのか、航空機を使用した航空貨物輸送を提供するのかなどを検討します。ここで重要なのは、国際物流サービスの場合、貨物利用運送事業法の規制対象は輸出事業のみだということです。輸入事業や三国間輸送は規制対象外ですので、輸出入のバランスを考慮した事業設計も可能です。
—— 最近の物流業界のトレンドとして、どのような輸送モードが注目されていますか?
阪本:近年は環境負荷の低減やトラックドライバー不足を背景に、長距離幹線輸送では鉄道や内航船舶を活用する複合一貫輸送が増えています。また、EC市場の拡大に伴い、小口貨物の迅速な配送ニーズも高まっており、航空貨物と宅配の組み合わせなども注目されています。さらに、国際物流では中国やASEAN諸国との取引増加を背景に、海上コンテナと航空貨物を状況に応じて使い分ける「シーアンドエア」という輸送形態も増えています。市場ニーズを見極めながら、最適な輸送モードを選択することが重要です。
貨物利用運送事業の種別の確認
—— 輸送モードが決まったら、次はどのような手続きになりますか?
阪本:次に行うのが、取得する貨物利用運送事業の種別の確定です。貨物利用運送事業には第一種と第二種の2種類があり、それらをさらに輸送モード別に分類すると多くの種類に分かれます。
—— それぞれの種類について詳しく教えていただけますか?
阪本:第一種貨物利用運送事業には、貨物自動車、鉄道、内航海運、外航海運、国内航空、国際航空の6種類があります。第二種貨物利用運送事業には内航海運、外航海運、国内航空、国際航空の4種類があります。提供したい貨物利用運送サービスに合わせて、これらの中から必要な種類を選択します。
—— 第一種と第二種の違いはどこにあるのでしょうか?
阪本:第一種は他の運送事業者の行う運送を単に利用するものです。一方、第二種は利用運送に加えて、幹線輸送の前後に行われる貨物の集配も行います。第二種はドアツードアの一貫輸送サービスを提供するものです。許可基準も第二種の方が複雑になっています。
例えば、第一種貨物利用運送事業(貨物自動車)であれば、荷主から依頼を受けて一般貨物自動車運送事業者に実運送を委託するだけのシンプルなモデルです。対して第二種貨物利用運送事業(内航)であれば、内航船を利用した船舶輸送の前後の集貨・配達業務を行う事業形態になります。
外国人事業者における相互主義
—— 外国企業が日本で貨物利用運送事業を始める場合、特別な制限はありますか?
阪本:はい、外国人事業者に対しては相互主義に基づく制限があります。例えば、外国人事業者による第一種貨物利用運送事業(国内航空)の登録や第二種貨物利用運送事業(国内航空)の許可取得はできません。
—— 相互主義とはどのような考え方なのでしょうか?
阪本:相互主義は、日本企業と外国企業とが国際貨物利用運送事業の分野において公正な事業活動を行えるようにするという考え方です。簡単に言えば、国ごとに貨物利用運送に関するルールが異なりますので、日本での外国人事業者の事業活動に一定の制限を設けることで、国際的な公平性を担保しようとしているのです。
—— 具体的にはどのような企業が外国人事業者に該当するのでしょうか?
阪本:外国人事業者とは、日本国籍を有しない個人、外国または外国の公共団体、外国の法令に基づいて設立された法人、そして外国人がその代表者である法人や外国人が役員の3分の1以上または議決権の3分の1以上を占める法人を指します。
実務では、海外のフォワーダーグループが出資した日本法人などが該当します。例えば、欧州の大手フォワーダーが日本に100%子会社を設立し、その役員に本国から外国人を派遣しているようなケースです。こうした場合、国内航空の分野には参入できませんが、外航海運や国際航空の分野であれば許認可申請は可能です。ただし、外国人事業者用の特別な申請様式が用意されております。
最近では特に中国系やASEAN諸国の企業による日本進出が増えており、こうした外国人事業者向けの申請サポートも当事務所の業務として増えています。
法人設立手続き
—— 既存の法人ではなく、新たに法人を設立して貨物利用運送事業を始める場合はどうすればよいでしょうか?
阪本:貨物利用運送事業法令では、法人設立中であっても貨物利用運送事業の登録・許可申請は可能ですが、私どもとしては法人設立手続きを先に完了させてから申請することをお勧めしています。
—— なぜ法人設立を先に完了させた方がよいのですか?
阪本:法人設立途中で役員や本店所在地などの変更があった場合、許認可申請の内容も修正が必要になり、かえって時間がかかってしまうことがあるからです。法人設立手続き自体は近年簡略化されており、それほど時間がかからなくなっています。まず法人設立を確実に終わらせ、その上で貨物利用運送事業の登録・許可申請を行う方が効率的です。
—— 法人形態にはどのような選択肢がありますか?
阪本:一般的には株式会社や合同会社が選ばれますが、貨物利用運送事業法で定められている許可・登録要件を満たせるのであれば、一般社団法人や一般財団法人でも参入は可能です。ただし当法人では一般社団法人や一般財団法人での許可・登録申請はご相談いただいたことはございません。合同会社での許可・登録申請をいただくこともありますが、株式会社での申請が圧倒的に多いです。
—— 法人設立時の主な注意点を教えてください。
阪本:主な注意点は「貨物利用運送事業の許認可取得要件に準拠した法人を設立させること」と「スケジュール管理」の2点です。特に前者は事業目的、本店所在地、資本金、役員の4点に注意が必要です。
貨物利用運送事業の許認可取得要件に準拠した法人を設立させること
—— 法人設立時の4つの注意点について、詳しく教えていただけますか?まず事業目的はどのように記載すべきでしょうか?
阪本:事業目的には「貨物利用運送事業」と記載することをお勧めします。第一種や第二種のように種別を限定して記載すると、後から別の種別の申請をする際に事業目的の変更が必要になる可能性があります。「貨物利用運送事業」と記載しておけば、第一種と第二種のどちらの申請にも対応できます。
あるケースでは、「第一種貨物利用運送事業」と限定して記載した会社が、後に第二種の許可も取得したいと考えた際に、定款変更のための株主総会開催などの手続きが必要になり、申請が1ヶ月以上遅れたこともありました。余計な手間を避けるためにも、包括的な記載がベストです。
—— 本店所在地についての注意点は何でしょうか?
阪本:登記簿上の本店所在地を貨物利用運送事業の営業所とする場合は特に注意が必要です。重要なのは、営業所の使用権限を有していることと、都市計画法等関係法令の規定に抵触していないことの2点です。
実際にあった例として、登記簿上の本店を住宅地の自宅にしたものの、その地域が住居専用地域で事業所設置が制限されていたため、別途営業所を確保する必要が生じたケースがありました。また、バーチャルオフィスを本店にしている場合も、実際の営業活動を行う場所として認められませんので注意が必要です。
—— 資本金についてはどうでしょうか?
阪本:資本金は300万円以上で法人を設立することをお勧めします。貨物利用運送事業の登録・許可を取得できるのは、純資産額300万円以上の法人と決められているからです。
資本金10万円や50万円でも法人設立自体は可能ですが、その額では設立直後に貨物利用運送事業の許認可は取得できません。最初の決算前に申請したい場合は、増資手続きが必要になります。
ただし、1度でも決算が終わっていて、純資産額が300万円以上あれば、資本金自体が300万円未満でも申請は可能です。例えば、資本金が100万円でも、2期目以降に利益が計上され純資産が300万円を超えていれば、許認可取得の要件を満たします。
—— 役員に関する注意点はありますか?
阪本:貨物利用運送事業を経営する法人の役員は、貨物利用運送事業法上で規定されている欠格事由に該当していないことが求められます。欠格事由としては、2年以内に懲役や禁錮が終わった人、2年以内に貨物利用運送事業の許認可を取り消された人、2年以内に貨物利用運送事業に関して不正な行為をした人の3つがあります。
役員とは、株式会社の場合は取締役・監査役、合同会社の場合は社員のことです。これらの方々が欠格事由に該当すると、貨物利用運送事業の許認可は取得できません。特に過去に別の運送会社で役員を務めていた方が新たに法人を設立するケースでは、前の会社での犯罪歴や行政処分歴などを確認しておくことが重要です。
スケジュール
—— 貨物利用運送事業の許認可取得にはどれくらいの期間がかかるのでしょうか?
阪本:行政機関の一般的な審査期間として、第一種貨物利用運送事業の登録は2〜3ヶ月、第二種貨物利用運送事業の許可は3〜4ヶ月と公表されています。ただし、実際には第一種でも3ヶ月前後、第二種では4ヶ月以上かかることが多いです。
—— それは予想以上に長いですね。何か短縮する方法はありますか?
阪本:申請書類の準備を徹底して行い、不備がないようにすることが重要です。また、申請前に国土交通省や運輸局への事前相談を行うことで、スムーズに進むことがあります。ただし、基本的には行政側の審査期間は短縮が難しいため、余裕を持ったスケジュール設定が必要です。
事業開始時期が決まっているのであれば、貨物利用運送事業の登録・許可の審査期間に加えて、法人設立準備期間も考慮した上で、十分な余裕を持って準備を進めることをお勧めします。
—— 外国法人が日本で子会社を設立する場合は特に注意が必要でしょうか?
阪本:はい、外国法人の場合は特に時間がかかることが多いです。法人設立手続き自体に日数を要することに加え、意思決定においても本国の親会社の承認が必要なケースが多く、手続きが中断することがよくあります。
例えば、契約書の修正点や申請書の詳細について、日本法人側は早く進めたいのに親会社の決裁待ちで数週間止まってしまうというケースもあります。外国法人が関わる場合は、国内企業よりもさらに余裕を持ったスケジュール設定をお勧めします。最近の事例では、欧州企業の日本法人設立から許認可取得まで合計で8ヶ月ほどかかったケースもありました。

委託先との運送委託契約の締結
—— 委託先との運送委託契約について、注意点を教えてください。
阪本:貨物利用運送事業の登録・許可申請書には、利用する運送会社との間で締結した運送委託契約書の写しを添付する必要があります。この運送委託契約書の締結までの段取りが想像以上に時間がかかることが多いです。
—— 運送委託契約書の締結までの流れを教えていただけますか?
阪本:一般的な流れとしては、委託する運送会社の選定から始まり、契約内容の調整、運送委託契約書の作成、運送委託契約書の審査、そして最終的な調印という段階を踏みます。
委託する運送会社の選定では、その会社が保有している許認可の種類が重要です。例えば、第一種貨物利用運送事業の貨物自動車の登録申請を行いたい場合、委託先は一般貨物自動車運送事業の許可か、第一種貨物利用運送事業(貨物自動車)の登録のいずれかを保有している必要があります。
—— 「利用の利用」というのは珍しいケースなのでしょうか?
阪本:「利用の利用」、つまり貨物利用運送事業者に委託するケースは意外と多いです。特に大規模な物流ネットワークを持つ大手フォワーダーとの提携を希望する新規参入者にとっては、実運送事業者よりも利用運送事業者と契約することで、より広範なサービスにアクセスできるメリットがあります。
ただし注意点として、黒ナンバーの軽貨物車を自社運送している貨物軽自動車運送事業者は、第一種貨物利用運送事業者の委託先としては認められません。過去に、このような誤解からトラブルになったケースもありますので、委託先選定の際は許認可の種類を必ず確認してください。
—— 大手運送会社との契約は難しいのでしょうか?
阪本:委託先運送会社の規模が大きい場合、特に法務部がある運送会社では、契約書の審査に時間がかかることがあります。先方の社内稟議の過程で条項の修正や追加が入り、なかなか調印段階まで進まないこともあります。
実例として、ある大手運送会社との契約では、責任分担や損害賠償に関する条項の調整だけで1ヶ月以上を要したケースがありました。また、委託料金体系の交渉においても、新規参入者が希望する条件と相手方の標準的な条件との間に隔たりがある場合は、妥協点を見つけるのに時間がかかります。
こういった事情もあり、委託先運送会社の選定や契約書調印に予想以上の日数がかかることが多いので、余裕を持ったスケジュール設定が重要です。最近では、標準的な委託契約書のひな形を事前に準備し、それをベースに交渉を進めることで、時間短縮を図るケースも増えています。
終わりに
—— 最後に、これから貨物利用運送事業を始める方へのアドバイスをお願いします。
阪本:貨物利用運送事業の登録・許可申請は、単に書類を揃えて国土交通省や運輸局に提出して終わるような簡単なものではありません。申請準備段階で様々な要件を一つずつ丁寧に確認・調整していく必要があります。そうしないと予期しない遅延が生じ、実際に事業を開始するまでに長期間かかることも珍しくありません。
特に近年の物流業界は急速に変化しており、デジタル化や環境対応、人手不足対策など新たな課題も多くあります。新規参入の際は、これらの変化に対応できるビジネスモデルを構築することも重要です。例えば、単なる運送の仲介だけでなく、物流DXを活用した付加価値サービスや、サステナブルな輸送網の構築など、差別化要素を考慮することをお勧めします。
また、許認可取得後も、継続的なコンプライアンス対応が必要です。事業報告書の提出や、法令改正への対応など、事業運営においても専門家のサポートを受けることで、リスクを低減できます。
—— 御社ではどのようなサポートを提供されているのでしょうか?
阪本:当事務所では、貨物利用運送事業の許認可申請だけでなく、事業計画の策定から委託先選定、契約書作成、そして許認可取得後の継続的なサポートまで、トータルでお手伝いしています。
特に力を入れているのは、申請代理だけでなく「事業をはじめた後のこと」まで見据えた適切な許認可設計です。例えば、将来的な事業拡大を見据えた種別選定や、海外展開を考慮した許認可取得など、クライアント様の中長期的なビジョンに合わせたアドバイスを心がけています。
昨今では特に、環境規制の強化やドライバー不足に対応したモーダルシフトの推進、国際物流におけるリスク分散など、物流業界は大きな転換期を迎えています。こうした変化を先取りした事業戦略の構築も含め、専門家としてのノウハウを提供することで、クライアント様の成功をサポートしたいと考えています。
貨物利用運送事業をはじめたい、手続きで失敗したくないという事業者様は、ぜひ一度ご相談ください。
—— 貴重なお話をありがとうございました。これから貨物利用運送事業に挑戦する方々にとって、大変参考になる内容だったと思います。
電話での問い合わせ
お電話でのお問い合わせは、平日の9:00~18:00の間、受け付けております。
お悩みについてすぐにお答えできるので、お電話でのお問い合わせをご利用いただく方も多いです。
- 都庁前オフィス(東京都新宿区):03-5843-8541
- 武蔵小杉オフィス(神奈川県川崎市):044-322-0848
お電話の際には「利用運送業のホームページを見た」とお伝えください。
なお、コンプライアンス上の理由で、匿名・電話番号非通知でのお問い合わせには対応しておりません。お問い合わせの際には会社名・お名前・ご連絡先などを伺っておりますのであらかじめご了承ください。
担当者不在時には伝言を残していただければ遅くとも翌営業日までに折り返し担当者よりお電話いたします。
※We apologize, but we are able to assist and operate in Japanese only.
メールでのお問い合わせ
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。必ず2営業日以内に返信しております。返信が届かない場合には、
- ご入力いただいたメールアドレスが間違っている
- 返信メールが迷惑メールフォルダ等に振り分けられている
- 返信メールが受信できない設定になっている
といった原因が考えられます。メールが届かない場合には、上記をご確認いただいたうえ、お手数ですが再度メールフォームよりお問い合わせください。
※We apologize, but we are able to assist and operate in Japanese only.