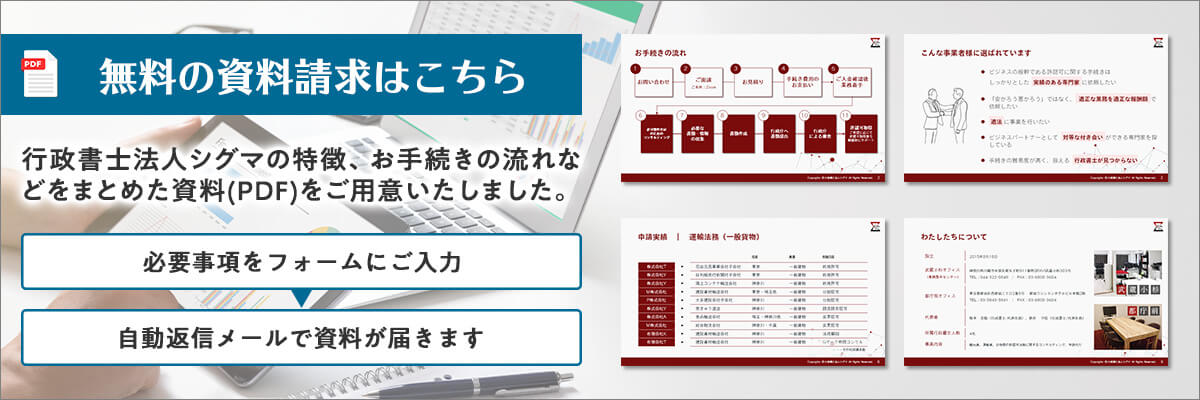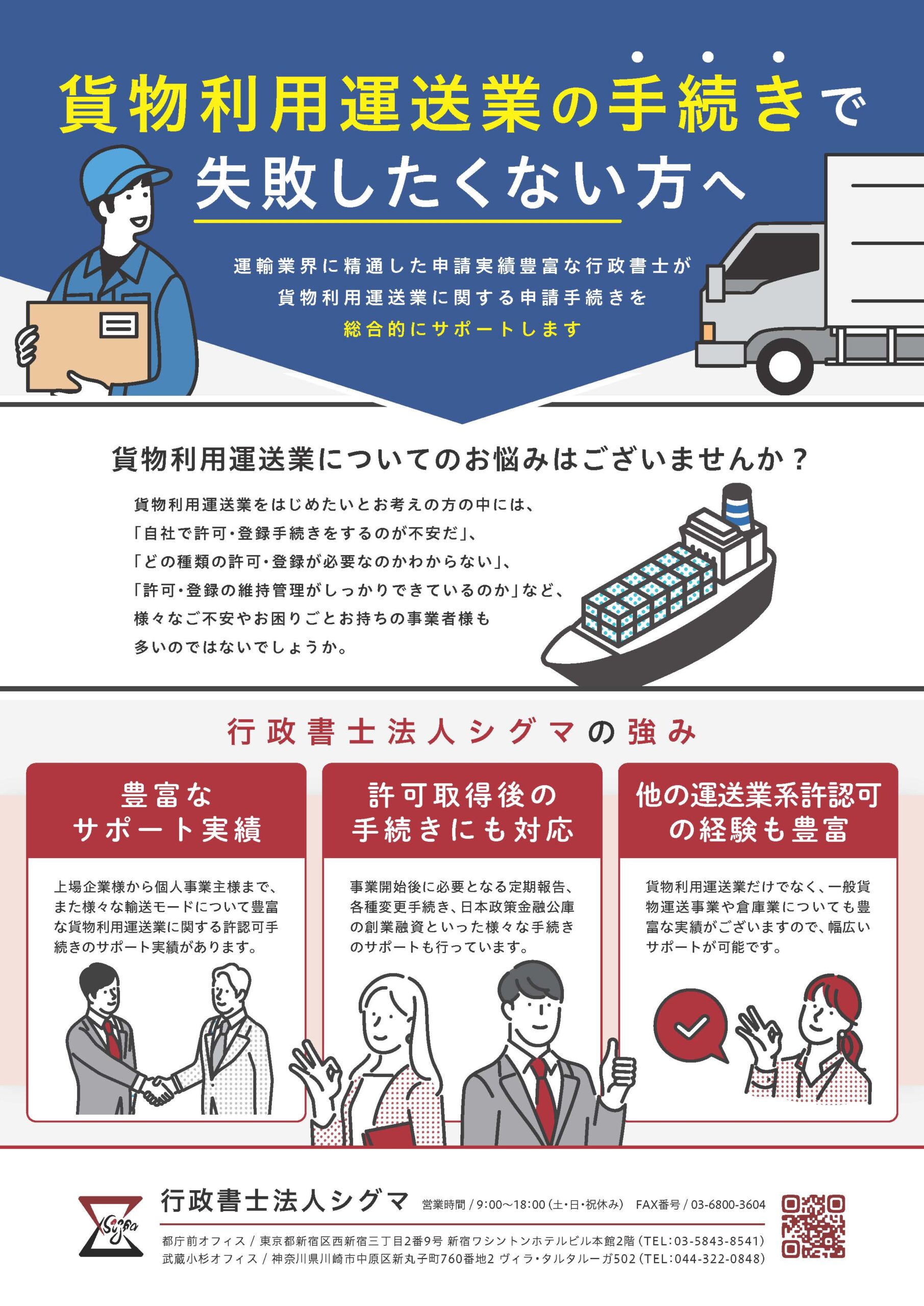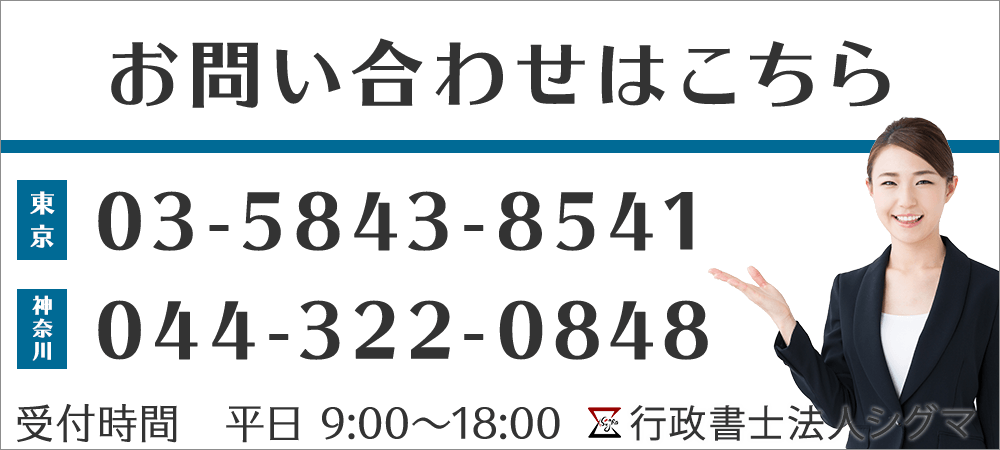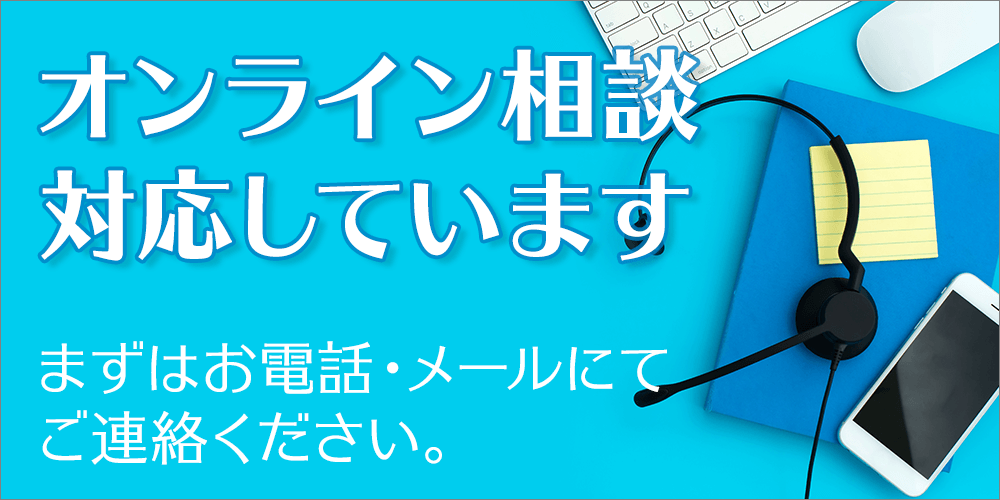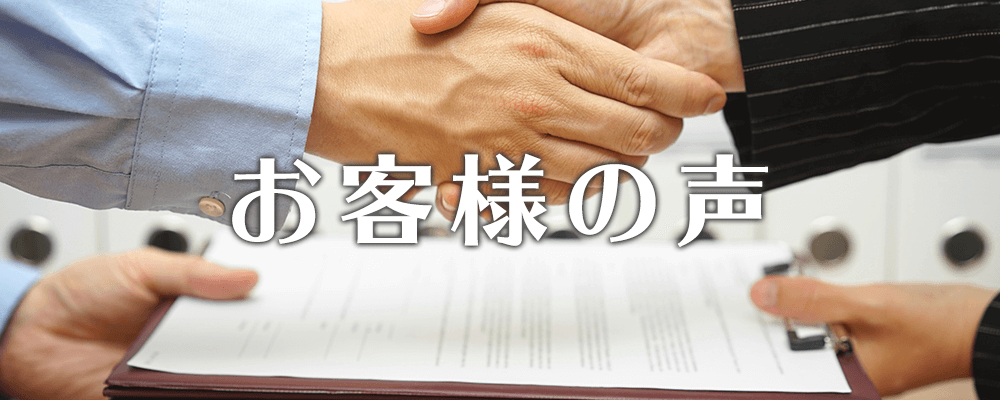今回は運送業界の許認可に精通する行政書士、阪本浩毅氏にお話を伺いました。阪本氏多くの運送業許認可申請をサポートしてきた実績を持ち、特に第一種貨物利用運送事業の登録申請手続きについては業界でも指折りのエキスパートとして知られています。
運送委託契約書の重要性
── 阪本さん、本日はお時間をいただきありがとうございます。まず第一種貨物利用運送事業の登録申請において、運送委託契約書はどのような役割を果たしているのでしょうか?
阪本:ご質問ありがとうございます。第一種貨物利用運送事業(貨物自動車)の登録申請手続きでは、実際に利用する運送会社との間で締結した運送委託契約書の写しを運輸局へ提出する必要があります。この書類は申請の核となる重要書類の一つです。
利用する運送会社というのは、具体的には運送業務を外注する実運送会社や他の第一種貨物利用運送事業者(貨物自動車)を指します。多くの事業者様が見落としがちなのですが、この運送委託契約の締結には、申請手続きを円滑に進めるための重要なポイントがいくつか存在します。

── なるほど。その運送委託契約書の作成で特に注意すべきポイントについて教えていただけますか?
阪本:はい。今日は特に重要な4つのポイントについて詳しくお話しします。実際の申請現場で多くの事業者様が戸惑われる部分ですので、ぜひ参考にしていただければと思います。
ポイント1:利用する運送会社の取得許認可
── まず最初のポイントについて教えてください。
阪本:1つ目のポイントは、利用する運送会社(外注先)の許認可についてです。第一種貨物利用運送事業(貨物自動車)が利用できる運送会社は、限定されています。具体的には次の許認可を取得している運送事業者に限られるのです。
- 一般貨物自動車運送事業許可
- 貨物自動車運送に関する第一種貨物利用運送事業者登録
つまり、外注先が実運送会社の場合は、国土交通省から一般貨物自動車運送事業の許可を取得している、いわゆる「緑ナンバー」の運送会社である必要があります。
── 貨物軽自動車運送事業や白ナンバーなどは対象外なのですね。
阪本:そのとおりです。黒ナンバーの軽貨物車を使用している貨物軽自動車運送事業は外注先として認められません。また、緑ナンバーではなく白ナンバーの車両で貨物運送を行っている無許可の事業者を外注先にすることも当然できません。
最近では宅配需要の増加に伴い、軽貨物運送業者と契約したいというご相談も増えていますが、第一種貨物利用運送事業の枠組みでは利用できないことをご理解いただく必要があります。
── 「利用の利用」という言葉をよく聞きますが、これはどういう意味でしょうか?
阪本:良いご質問です。「利用の利用」とは、実運送会社ではなく別の貨物利用運送事業者を外注先にするケースを指します。この場合は、貨物自動車運送に関する第一種貨物利用運送事業者の登録を取得している運送会社のみが外注先になれます。
ここで多くの事業者様が誤解されるのは、第一種貨物利用運送事業でも外航・内航・国内航空・国際航空といった貨物自動車以外の別モードの登録を取得している事業者や、第二種貨物利用運送事業許可を取得している事業者は、確かに貨物利用運送事業者ではありますが、第一種貨物利用運送事業(貨物自動車)の外注先にはできないという点です。
── 実際にそのような勘違いをする事業者は多いのでしょうか?
阪本:非常に多いです。当社がこれまでサポートした数百件の貨物利用運送事業の登録申請手続きの中でも、事業者様の勘違いで、外注先の事業者の取得許認可が条件に合致しないケースが少なくありません。
具体例を挙げると、ある物流会社は国際航空の第一種貨物利用運送事業の登録は持っていたものの、貨物自動車の登録は持っていなかったため、契約書を作り直す必要が生じました。また別のケースでは、長年取引のあった運送会社が実は貨物軽自動車運送事業者だったということが申請過程で判明し、急遽別の外注先を探すことになったこともあります。
ですから、利用する運送会社を選定する際には、事前に相手方の許認可証の写しなどを入手して、取得許認可を確認してから契約締結を進められることを強くお勧めします。
ポイント2:運送責任の所在
── 2つ目のポイントについて教えてください。
阪本:2つ目のポイントは「運送責任の所在」についてです。一般的な運送委託契約書は、荷主と運送会社との間での、貨物運送業務に関する条項が記載されている契約書になります。
しかし、このような一般的な運送委託契約書を貨物利用運送事業の登録申請の際にそのまま使用すると、運送責任の所在が、貨物利用運送事業のビジネスモデルと合致しないことがあるのです。
── 具体的にはどのような違いがあるのでしょうか?
阪本:一般的な運送契約書では、運送責任の所在は実運送会社が運送責任の全てを負うという形になっていることが多いです。しかし、貨物利用運送事業では、荷主に対する運送責任は貨物利用運送事業者が負う必要があります。これは貨物利用運送事業の本質的な部分です。
例えば、私が以前関わったあるケースでは、インターネット上で見つけた一般的な運送契約書のひな型を使用して申請したところ、運輸局から「運送責任の所在が不明確」という理由で補正を求められました。この契約書では、事故発生時の責任が全て実運送会社にあるという条項があり、貨物利用運送事業者としての責任が明記されていなかったのです。
また別のケースでは、運送中の貨物の保険に関する条項が貨物利用運送事業のスキームに合っていなかったため、申請が大幅に遅れるということもありました。
── では、どのような契約書を用意すべきなのでしょうか?
阪本:インターネット上からダウンロードした契約書を使って貨物利用運送事業の申請を進められる際は、その契約書が貨物利用運送事業のビジネスモデルに準拠したものであるかの確認を必ず行ってください。
特に、荷主に対する運送責任が貨物利用運送事業者にあることが明記されているか、そして実運送会社との間の責任分担が適切に規定されているかを確認することが重要です。
最近では運輸局の審査も厳格化しており、運送責任の所在が不明確な契約書では補正を求められるケースが増えています。当社では第一種貨物利用運送事業(貨物自動車)の登録申請手続きをご依頼いただいたお客様には、貨物利用運送事業に特化した当法人オリジナルの運送委託契約書の書式を提供しております。
ポイント3:契約締結年月日
── 続いて3つ目のポイントについて教えてください。
阪本:3つ目は「契約締結年月日」に関するポイントです。運送委託契約書には、契約当事者が調印する最終ページに、契約締結年月日を記載する箇所があります。
この契約締結年月日がブランクになっている契約書をよく拝見するのですが、これは多くの場合、貨物利用運送事業の登録取得前に運送委託契約を締結してよいのかという不安から来ているようです。
── 確かに、登録前に契約を結んでも大丈夫なのか不安になりますね。
阪本:そうですね。しかし、第一種貨物利用運送事業の登録申請を進める際の申請準備の正しい流れは、まず利用する運送会社との契約を締結し、その後で運輸局への登録申請書を提出するというものです。
つまり、運送委託契約書の締結年月日は、登録申請書提出前の日付であることが前提となっており、むしろ契約締結日が未記入だと運輸局から指摘される可能性があります。
実例を挙げると、ある関東の事業者様は「登録が下りてから正式に契約しよう」と考え、契約日欄を空欄のまま提出したところ、運輸局から「契約が成立していない」との指摘を受け、再提出することになりました。
── 最近の運輸局の審査状況はいかがでしょうか?
阪本:ここ数年、運輸局の審査はより厳格になってきています。特に2023年以降は、物流DXや働き方改革などの影響もあり、契約関係の書類についてより細かくチェックされるようになっています。
また、地域によっても若干の違いがあり、例えば関東運輸局と近畿運輸局では契約書の審査の重点項目が異なる場合もあるため、地域特性も考慮する必要があります。

ポイント4:収入印紙の貼付
── 最後に4つ目のポイントについて教えてください。
阪本:4つ目のポイントは「収入印紙の貼付」に関するものです。利用する運送会社との運送委託契約書は、通常「継続的取引の基本となる契約書」に該当します。
── 「継続的取引の基本となる契約書」とは具体的にどういうものですか?
阪本:「継続的取引の基本となる契約書」とは、特定の相手方との間において継続的に生じる取引の基本となる契約書のことです。貨物運送の場合、長期的・継続的に貨物輸送を依頼する基本契約がこれに当たります。
確かに「継続的取引の基本となる契約書」であっても、契約期間が3か月以内であり、かつ、更新の定めのないものは印紙税の課税対象から除外されますが、過去の貨物利用運送事業の登録申請案件で、このような短期間の契約書が受理されたケースは見たことがありません。
── なぜ短期契約では問題があるのでしょうか?
阪本:貨物利用運送事業の登録申請手続きは通常3か月程度の審査期間を要します。そのため、契約期間が3か月しかないと、運輸局の登録審査中に契約期間が満了してしまう可能性があります。その場合、「申請時の運送体制が審査中に消滅した」とみなされ、補正対象になることが予想されます。一般的には1年以上の契約期間を設定し、自動更新条項を入れることをお勧めします。
── 収入印紙の金額はいくらになるのでしょうか?
阪本:このように利用する運送会社との運送委託契約書は、原則として継続的取引の基本となる契約書に該当するため、印紙税額一覧表の第7号文書として扱われます。具体的には、契約書1通について4,000円の収入印紙の貼付が必要になります。
収入印紙を貼り付けた後は、消印も忘れずに捺印してください。この消印を忘れると、印紙税法上、印紙を貼付していないものとみなされてしまいます。
最近の実務では、電子契約システムを利用する事業者も増えていますが、その場合は印紙税の取り扱いが異なりますので、事前に税務署や専門家に確認することをお勧めします。
まとめ
── 今日は大変貴重なお話をありがとうございました。最後に、事業者の方々へのアドバイスをいただけますか?
阪本:本日ご説明した4つのポイント、「利用する運送会社の取得許認可」「運送責任の所在」「契約締結年月日」「収入印紙の貼付」は、第一種貨物利用運送事業(貨物自動車)登録申請書に添付する運送委託契約書の重要なチェックポイントです。
これらのポイントを押さえることで、運輸局からの補正指示を減らし、スムーズな登録取得が可能になります。特に近年は物流業界の変化に伴い、審査も厳格化する傾向にありますので、細部まで注意が必要です。
また、昨今のEコマースの拡大や物流DXの進展に伴い、貨物利用運送事業の形態も多様化しています。従来の枠組みに捉われない新しいビジネスモデルを検討されている事業者様は、事前に専門家に相談されることをお勧めします。
こちらの記事をご覧になって、自社だけで貨物利用運送事業の登録申請手続きを進めるのは煩雑だと感じられた事業者様は、行政書士に依頼することで、その手間を大幅に軽減することができます。私たちのような専門家は、申請書類の作成だけでなく、契約内容の適正化や運輸局とのコミュニケーションまでトータルでサポートいたします。
行政書士法人シグマでは、東京・神奈川の事業者様を中心に、第一種貨物利用運送事業(貨物自動車)の登録申請手続きの申請代行サービスを提供しております。お困りごとがございましたら、ご連絡ください。
── 阪本さん、本日は貴重なお話をありがとうございました。
電話での問い合わせ
お電話でのお問い合わせは、平日の9:00~18:00の間、受け付けております。
お悩みについてすぐにお答えできるので、お電話でのお問い合わせをご利用いただく方も多いです。
- 都庁前オフィス(東京都新宿区):03-5843-8541
- 武蔵小杉オフィス(神奈川県川崎市):044-322-0848
お電話の際には「利用運送業のホームページを見た」とお伝えください。
なお、コンプライアンス上の理由で、匿名・電話番号非通知でのお問い合わせには対応しておりません。お問い合わせの際には会社名・お名前・ご連絡先などを伺っておりますのであらかじめご了承ください。
担当者不在時には伝言を残していただければ遅くとも翌営業日までに折り返し担当者よりお電話いたします。
※We apologize, but we are able to assist and operate in Japanese only.
メールでのお問い合わせ
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。必ず2営業日以内に返信しております。返信が届かない場合には、
- ご入力いただいたメールアドレスが間違っている
- 返信メールが迷惑メールフォルダ等に振り分けられている
- 返信メールが受信できない設定になっている
といった原因が考えられます。メールが届かない場合には、上記をご確認いただいたうえ、お手数ですが再度メールフォームよりお問い合わせください。
※We apologize, but we are able to assist and operate in Japanese only.