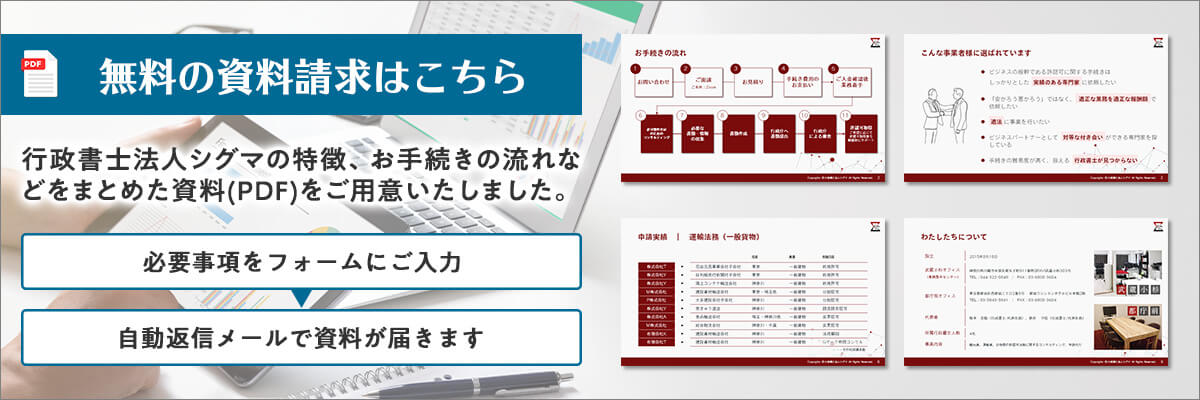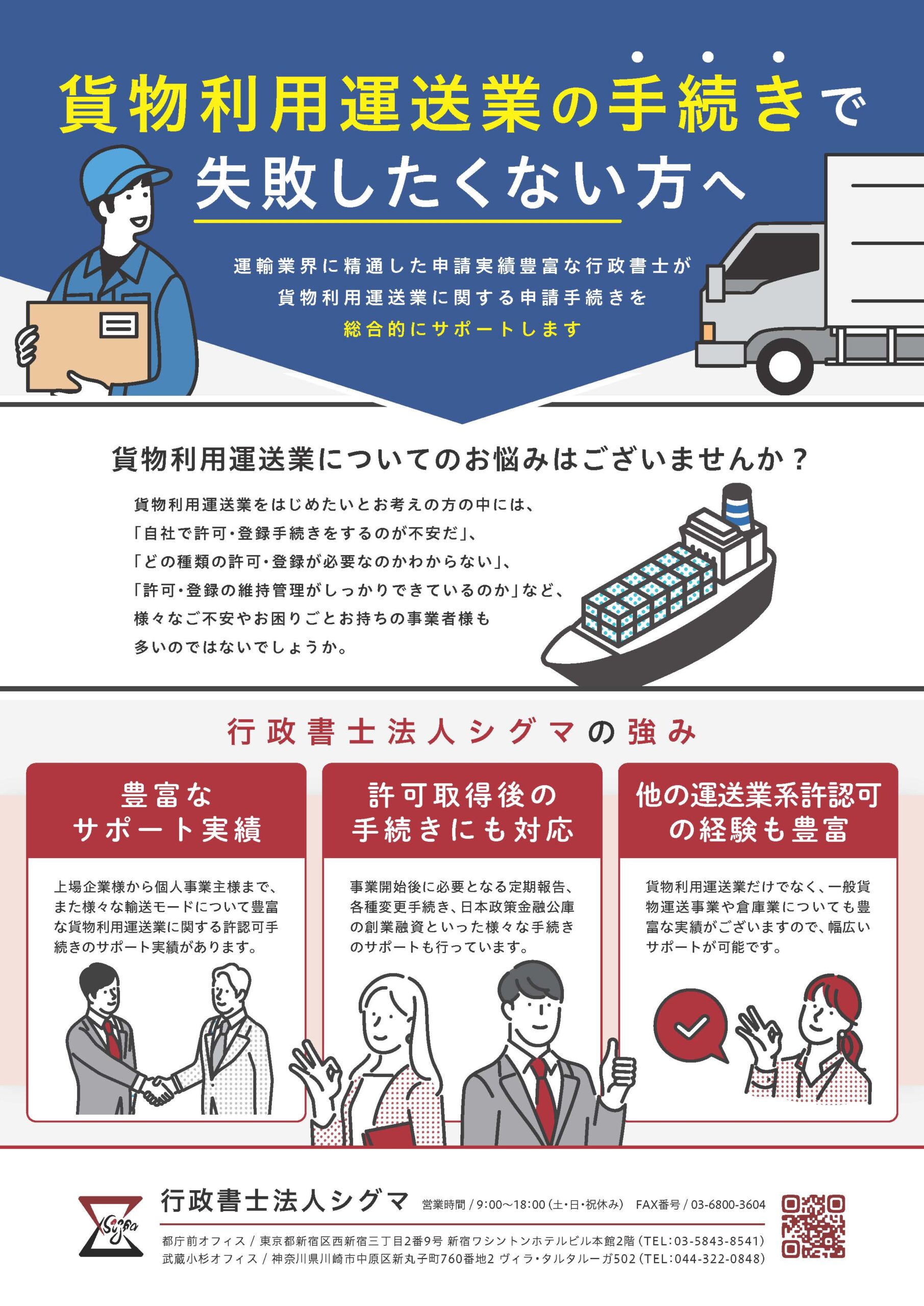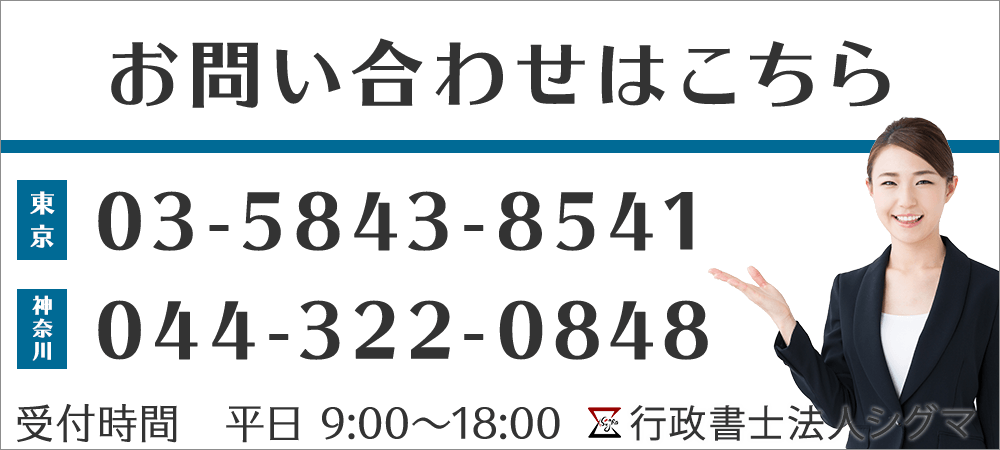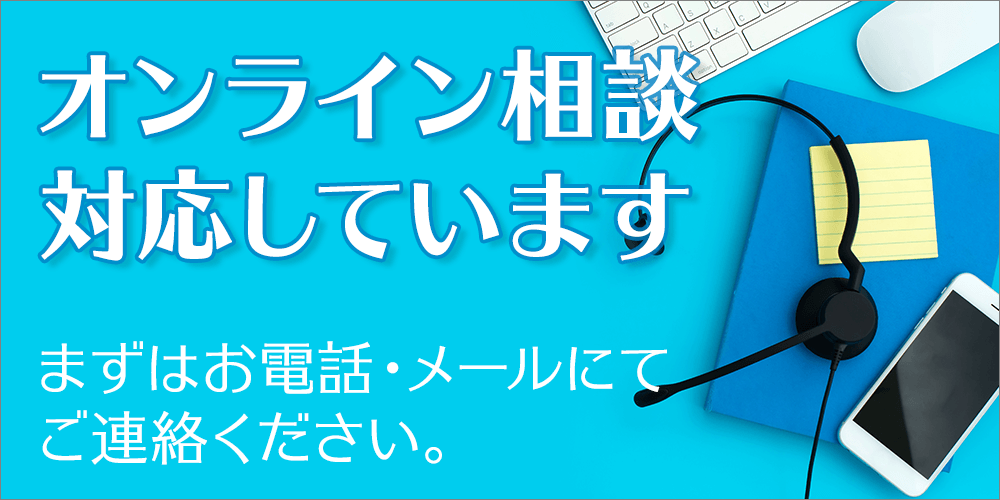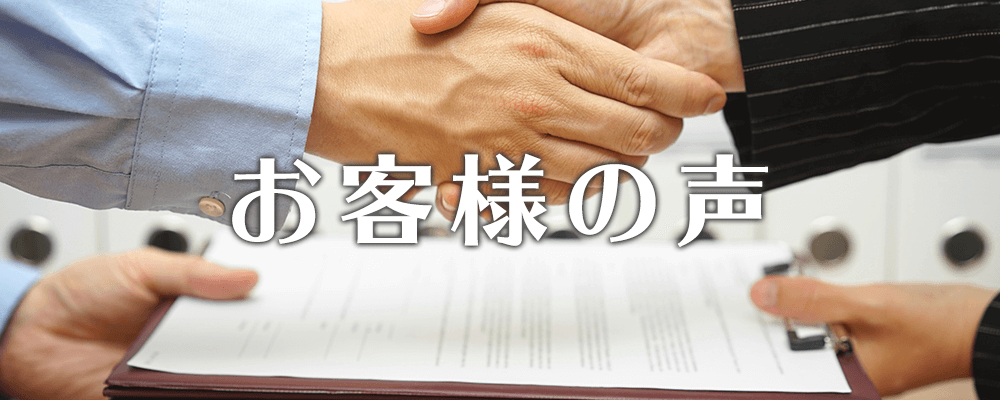今回は、運送業界の許認可に精通し、数多くの事業者の申請サポートを手がけてきた行政書士の阪本浩毅氏にお話を伺いました。阪本氏は10年以上にわたり運輸局への第一種貨物利用運送事業の登録取得の支援を行っております。昨今のEコマース急成長による物流需要の高まりを背景に、ライセンス取得を検討する企業が増加する中、実務における重要ポイントを語っていただきました。
Contents
第一種貨物利用運送事業ライセンスの取得理由と現実
── 阪本さん、まず第一種貨物利用運送事業のライセンス取得を急ぐ企業が多いと聞きますが、どのような事情があるのでしょうか?
阪本:ありがとうございます。私どもに相談される企業様の中には「荷主企業の依頼でトラックを手配するために第一種貨物利用運送事業のライセンスを早急に取得したい」とおっしゃる方が非常に多いです。緑ナンバーのトラックを手配する利用運送の場合、貨物自動車に関する第一種貨物利用運送事業の登録が必要になりますが、急いでいる理由は企業によって様々です。

── どのような理由が多いのでしょうか?
阪本:初回の相談時に伺う主な理由としては、まず「取引先から利用運送の登録通知書の提出を求められている」というケースが最も多いですね。特に大手物流会社や製造業との取引開始時に必須条件として提示されることがあります。次に「新規事業の開始時期が迫っている」というパターンです。例えば、ECサイトのローンチに合わせて自社配送網を構築したいという企業様もいらっしゃいます。また「顧問弁護士や法務部から法令遵守の観点でライセンス取得を指示された」というケースも増えています。特に昨今はコンプライアンス意識の高まりから、この理由が急増している印象です。
── なるほど。でも実際に取得するまでにはどのくらいの時間がかかるものなのでしょうか?
阪本:これが多くの方が勘違いされているポイントなのですが、第一種貨物利用運送事業の登録取得手続きは想像以上に時間と労力がかかります。「申請書類を運輸局に提出すれば、すぐに営業開始できる」と考えている方もいらっしゃいますが、実際にはそうではありません。
貨物自動車に関する第一種貨物利用運送事業の登録申請の場合、申請書類を関東運輸局などに提出してから審査完了までの標準処理期間は約3ヶ月とされています。つまり、申請書類を提出した後も、運輸局内での詳細な審査と決裁プロセスがあるため、すぐにライセンスが取得できるわけではないのです。
── 3ヶ月もかかるんですね。それは申請準備の期間も含めてですか?
阪本:いいえ、その点も大切なポイントです。先ほど申し上げた標準処理期間の3ヶ月というのは、あくまで運輸局が申請書類を正式に受理した時点からのカウントになります。申請書類の準備期間はこれに含まれていません。実際には、書類準備に1〜2ヶ月かかるケースも珍しくないため、計画的に進める必要があります。
提出書類の準備は意外と時間がかかる
── 提出書類について詳しく教えていただけますか?
阪本:運輸局のホームページには第一種貨物利用運送事業に必要な書式や必要書類が掲載されています。多くの事業者様は初めてこの一覧を見ると「意外と簡単そうだ」と感じられるようです。しかし実際に準備を始めると、必要書類の収集や作成に予想以上の時間を要してしまうことがほとんどです。
例えば、法人の登記簿謄本や決算書類の準備、事業計画書の詳細な作成、そして後ほど詳しくお話しする運送委託契約書など、様々な書類が必要になります。特に初めて申請される事業者様からは「当初のイメージよりも大変だった。自社だけでの登録取得は難しかった」という感想をよく耳にします。
── 具体的にどんな書類で苦労することが多いのでしょうか?
阪本:特に苦労されるのが「事業計画書」と「運送委託契約書」です。事業計画書には委託先運送事業者の情報、営業所の所在地、利用運送の区域又は区間、業務の範囲など詳細な情報を記載する必要があります。これらを正確に、かつ整合性を持って作成することに時間がかかります。また、運送委託契約書は、委託先運送事業者との間で締結したものが必要です。つまり委託先運送会社が未決の場合は、登録申請自体が進められないのです。
必要書類を揃えて提出すればライセンスが取得できるわけではない
── 必要な書類さえ揃えれば、審査はスムーズに通るものなのでしょうか?
阪本:これも多くの方が誤解されている点です。貨物自動車に関する第一種貨物利用運送事業の登録を検討されている事業者様の中には「運輸局が公開している申請手引きに記載されている書類を提出しさえすれば、ライセンスは取れる」と思われている方もいらっしゃいますが、実際にはそれほど簡単ではありません。
貨物利用運送事業はライセンス制を採用しているため、取得するための条件が法令で明確に定められています。ライセンス取得の詳細な条件の説明は割愛しますが、申請準備段階で事業者様が勘違いされて手続きが中断してしまうケースが少なくありません。
── 中断してしまう主な理由はどのようなものがありますか?
阪本:手続きが中断したり遅延したりする主な理由は2つあります。まず1つ目は「純資産額」の問題、2つ目は「委託先との契約関係」です。これらについて詳しくお話しします。
純資産額は300万円以上ありますか?
── 純資産額について詳しく教えてください。
阪本:第一種貨物利用運送事業の登録を法人で取得する場合、原則として直近決算期の貸借対照表に記載されている純資産額が300万円以上であることが要求されます。この「純資産額300万円以上」というのは税務署に提出した決算書上の数値であり、単に会社の預貯金が300万円あることや、利益が300万円以上あることとは異なります。
純資産は「資産から負債を引いた額」になりますので、売上や利益とは別の概念です。例えば、設備投資や借入金が多い会社では、売上は好調でも純資産が300万円を下回っているケースもあります。逆に、資本金は少なくても内部留保が多い会社では十分な純資産がある場合もあります。
── 純資産が足りない場合はどうすればよいのでしょうか?
阪本:純資産が不足している場合の対策としては、増資を行う方法があります。ただし、増資を行った場合は、その旨が反映された登記簿謄本と、増資後の貸借対照表の提出が必要になります。また、決算期が迫っている場合は、次期決算を待って申請するという選択肢もあります。

委託先との運送委託契約は締結済ですか?
── 委託先との契約関係について教えてください。
阪本:貨物自動車に関する第一種貨物利用運送事業の登録申請書類のうち、事業計画を記載する書類には、委託先(利用する運送事業者)の情報を記載する箇所があります。そして、事業計画に記載した委託先との間で締結した運送委託契約書のコピーを事業計画と一緒に提出する必要があります。つまり、委託先が確保できなければ、申請書を提出することができないのです。
── 委託先は何社くらい必要なのでしょうか?
阪本:「委託先が複数社ある場合、何社あれば登録を取得できますか?」というご質問をよくいただきますが、法令上は、貨物利用運送事業の委託先はすべて運輸局へ届け出なければならないことになっています。
しかし現実には、委託先企業の内部稟議の進行が遅く、運送委託契約書の締結がなかなか進まないということもよくあります。特に大手運送会社との契約は、法務部門の確認に時間がかかるケースが多いです。また最近では、委託先に求める保険の補償範囲や情報セキュリティ対策についての条項が複雑化しており、契約締結までの時間が長期化する傾向にあります。
── そのような場合の対応策はありますか?
阪本:このような場合は、一旦、契約締結が完了している委託先のみで登録申請手続きを進めて、登録取得後に、稟議に時間を要していた委託先を追加する変更届出を行うという方法もあります。確かに登録取得後に変更届出を提出する手間は増えてしまいますが、登録取得までのスピードと法令順守を両立することができるというメリットがあります。
実務的なアドバイスとしては、申請の何ヶ月も前から主要な委託先候補との交渉を始めておくことをお勧めします。また、契約書のひな形を事前に法務部門に確認してもらうなど、スムーズな締結に向けた準備も重要です。
おわりに
── 最後に、これから第一種貨物利用運送事業の登録取得を検討している事業者へのアドバイスをお願いします。
阪本:はじめて第一種貨物利用運送事業の登録取得手続きを行う事業者様の多くは「こんなに時間がかかるのか…」と驚かれます。繰り返しになりますが、運輸局の3ヶ月の審査期間は、どんなにお願いしても短縮はできません。これは法令で定められた手続きであり、行政側のリソース配分に基づくものだからです。
さらに手続きに慣れていない事業者様が申請する場合、運輸局からの確認の連絡対応や書類差し替えなどの補正対応で、審査期間がさらに伸びてしまうこともよくあります。私の経験では、初めての申請で4〜5ヶ月かかったケースも少なくありません。
── そのような遅延を防ぐ方法はありますか?
阪本:この点については、運輸局への提出書類の精度を上げることで、運輸局からの確認連絡や書類差し替え指示の時間をカットすることができます。なるべく早く第一種貨物利用運送事業の登録を取得されたい場合は、ポイントを押さえた申請準備を行うことが重要です。
また、計画的な申請スケジュールの立案が何よりも重要です。ライセンス取得には最低でも4〜5ヶ月の期間を見込んでおくことをお勧めします。急ぎの場合でも、書類準備の段階からプロのサポートを受け、効率的に進めていくことが近道となるでしょう。
── 貴重なお話をありがとうございました。実務的な視点から多くの気づきがありました。
阪本:こちらこそ、お時間をいただきありがとうございました。少しでも事業者の皆様のお役に立てれば幸いです。
電話での問い合わせ
お電話でのお問い合わせは、平日の9:00~18:00の間、受け付けております。
お悩みについてすぐにお答えできるので、お電話でのお問い合わせをご利用いただく方も多いです。
- 都庁前オフィス(東京都新宿区):03-5843-8541
- 武蔵小杉オフィス(神奈川県川崎市):044-322-0848
お電話の際には「利用運送業のホームページを見た」とお伝えください。
なお、コンプライアンス上の理由で、匿名・電話番号非通知でのお問い合わせには対応しておりません。お問い合わせの際には会社名・お名前・ご連絡先などを伺っておりますのであらかじめご了承ください。
担当者不在時には伝言を残していただければ遅くとも翌営業日までに折り返し担当者よりお電話いたします。
※We apologize, but we are able to assist and operate in Japanese only.
メールでのお問い合わせ
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。必ず2営業日以内に返信しております。返信が届かない場合には、
- ご入力いただいたメールアドレスが間違っている
- 返信メールが迷惑メールフォルダ等に振り分けられている
- 返信メールが受信できない設定になっている
といった原因が考えられます。メールが届かない場合には、上記をご確認いただいたうえ、お手数ですが再度メールフォームよりお問い合わせください。
※We apologize, but we are able to assist and operate in Japanese only.