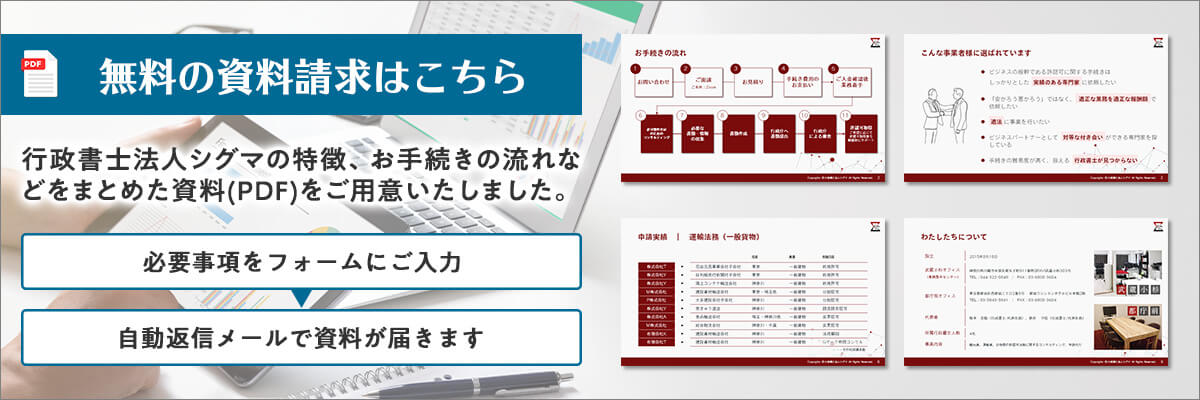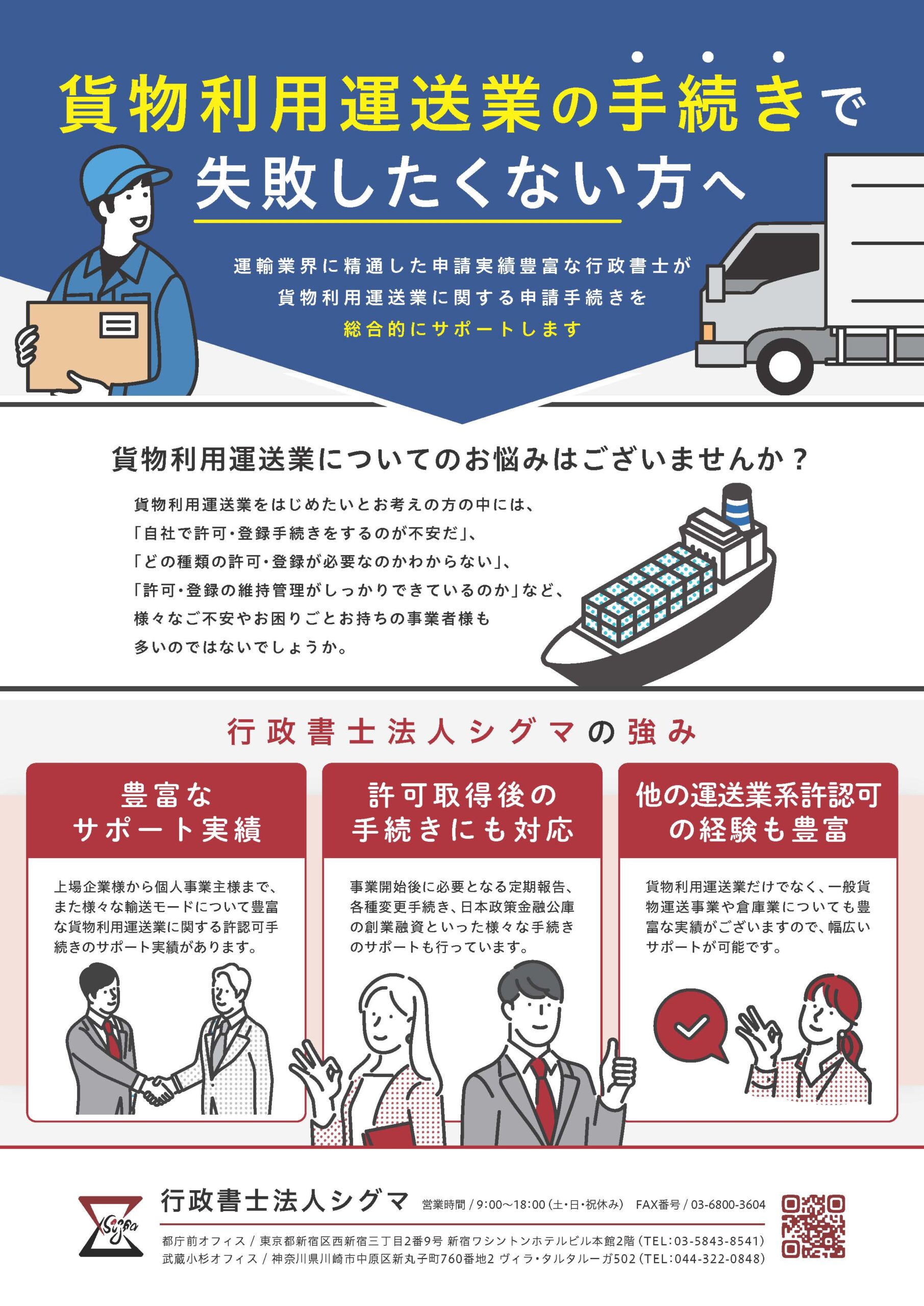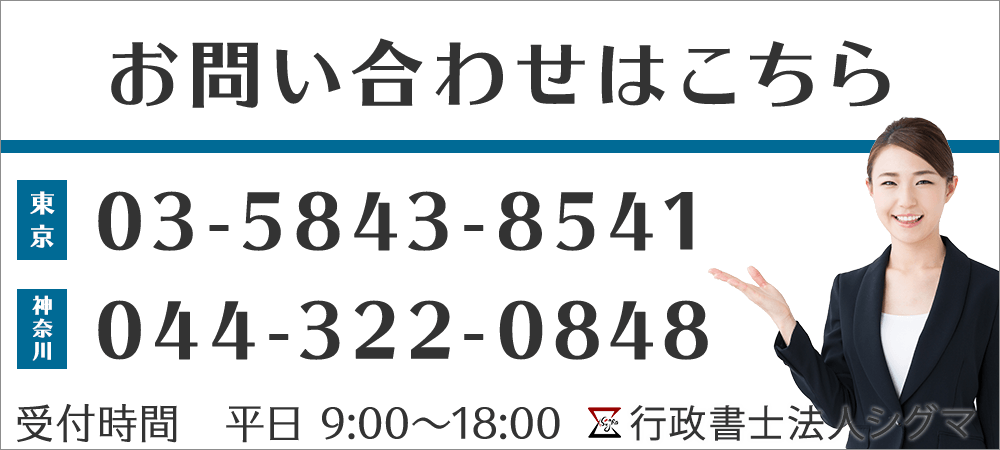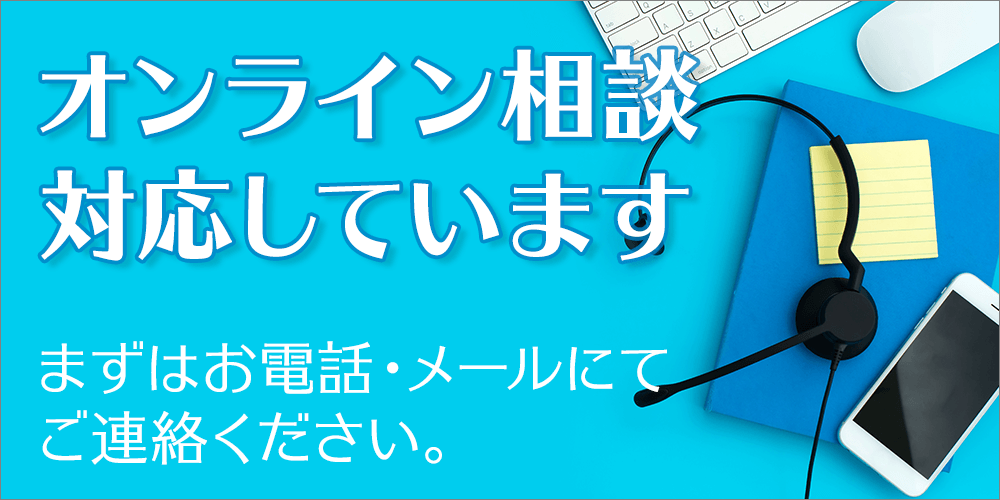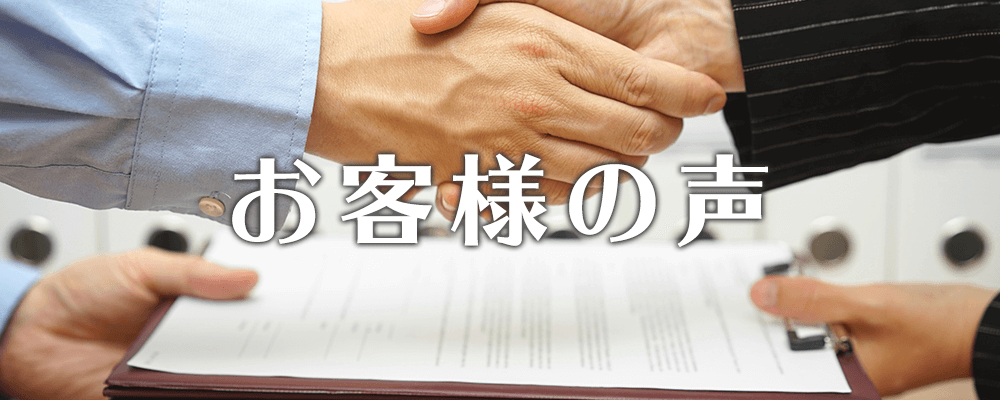本記事では、物流業界の第一線で活躍するコンサルタント阪本浩毅氏に、第一種貨物利用運送事業登録の要件について詳しく解説していただきました。物流業界への新規参入を検討する事業者必見の情報です。
── 本日はお忙しい中、お時間をいただきありがとうございます。今日は基本から教えていただければと思います。
阪本: こちらこそよろしくお願いします。多くの方が貨物利用運送事業の仕組みや登録要件について詳しく知らないので、今日はわかりやすく説明したいと思います。

── まずは基本的なところからお聞きしたいのですが、貨物利用運送事業とはどのようなものなのでしょうか?
阪本: 簡単に言うと、貨物利用運送事業とは、荷主から依頼を受けて、自社では運送せず、有償で運送業者を利用して貨物を運送する事業です。自分でトラックを持たなくても物流ビジネスができる、いわば物流の「仲介業」とイメージするとわかりやすいでしょう。
── なるほど。実際に運送するわけではないんですね。よく第一種と第二種があると聞きますが、違いはどこにあるのでしょうか?
阪本: はい、貨物利用運送事業には第一種と第二種があります。大きな違いは取扱う運送手段と許可の厳しさです。第一種は主にトラックなどの陸上輸送に関わるもので「登録制」、第二種は船舶や航空機などを使った国際輸送に関わるもので「許可制」となっています。今日は参入障壁が比較的低い第一種についてお話したいと思います。
── 私も第一種について詳しく知りたいです。登録するためには、どんな要件を満たす必要があるんでしょうか?
Contents
第一種貨物利用運送事業登録の3つの柱
阪本: 第一種貨物利用運送事業の登録要件は大きく3つに分けられます。「人」「設備」「お金」という観点からの要件です。
── 「人・物・金」ですね。わかりやすい分類です。
阪本: そうですね。具体的には:
- 人に関する要件:欠格事由に該当しないこと
- 設備に関する要件:適切な営業所・事務所・店舗、必要に応じて保管施設があること
- 財務に関する要件:300万円以上の純資産を有していること
これらの要件を満たすことで、第一種貨物利用運送事業の登録が可能になります。
── 一つずつ詳しく教えていただけますか?まず「人」の要件、欠格事由というのはどういったものですか?
人に関する要件:欠格事由を詳しく解説
阪本: 「欠格事由」というのは、登録を受けようとする方に一定の事情がある場合に、登録ができなくなる条件のことです。
── 具体的にはどのような条件がありますか?
阪本: 個人で申請する場合はその個人が、法人で申請する場合は役員(取締役・監査役など)が以下のいずれかに該当すると登録できません:
- 1年以上の懲役または禁錮の刑を受け終わってから、または刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない
- 第一種貨物利用運送事業の登録または第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過していない
- 申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした
── かなり厳しい条件ですね。一般貨物自動車運送事業では運行管理者の選任が必要と聞きましたが、貨物利用運送事業でも同じですか?
阪本: それが大きな違いなんです。貨物利用運送事業では運行管理者の選任は不要です。これは実際に自社で車両を運行させないためで、この点は一般貨物自動車運送事業と比べると参入ハードルが低くなっています。
── なるほど、そこは大きなメリットですね。次に「設備」の要件について教えてください。
設備に関する要件:営業所と保管施設のルール
阪本: 設備については、実運送業のように車両を使わないため、車庫や休憩施設は必要ありません。営業所(事務所や店舗)があれば基本的には問題ありませんが、いくつかのルールを満たす必要があります。
── 事務所があればいいんですね。特別な設備は必要ないんですか?
阪本: 基本的には普通の事務所で構いません。ただし、貨物を保管する場合には、その保管施設についても適切な基準を満たしている必要があります。
── 営業所や保管施設について気をつけるべきポイントはありますか?
阪本: まず第一に、その場所を使用する権利を持っていることが必要です。自己所有または賃貸借契約を結んでいれば「使用する権利あり」となります。
実際の登録申請では、申請者がその権利を有していることを宣誓する書類(宣誓書)を提出します。賃貸借契約書自体の提出は不要ですが、契約内容には注意が必要です。
── 賃貸で事務所を借りる場合、よくある落とし穴はありますか?
阪本: よくあるのが、物件の「使用目的」に関する問題です。契約書の使用目的が「住居」や「居住」となっている場合、営業所や保管施設として使用すると契約違反になる可能性があります。使用目的は「貨物利用運送事業の営業所」「貨物利用運送事業の保管施設」などと明確にしておくべきでしょう。
── それは気をつけないといけませんね。立地についても制限があると聞きましたが?
阪本: はい、以下のような建物は貨物利用運送事業の営業所や保管所として使用できません:
- 違法建築物
- 市街化調整区域内の建物
- 農地(地目が「田」「畑」)上の建物
── 意外と制限が多いんですね。物件探しの際には気をつけたいポイントです。では最後に「お金」の要件について教えてください。
財務に関する要件:純資産300万円の計算方法
阪本: 第一種貨物利用運送事業の登録を受けるためには、純資産が300万円以上必要です。
── 純資産というと、単純に資本金が300万円あればいいというわけではないんですよね?
阪本: そうです。純資産の計算方法は少し複雑で、「(財産的基礎としての)純資産=(会計上の)純資産-創業費その他の繰延資産・営業権-総負債」という計算式で算出します。
── なるほど、単純な資本金だけでなく、実質的な資産状況を見るんですね。
阪本: はい。この純資産は直近事業年度の決算書で証明します。新設法人の場合は、開始貸借対照表を提出し、設立時の払込資本金が300万円以上あることが求められます。
── 法人で申請する場合に気をつけるべき点は他にありますか?
法人における事業目的の記載について
阪本: 法人(株式会社や合同会社など)で第一種貨物利用運送事業の登録を受ける場合、事業目的に「貨物利用運送事業」という記載が必要です。
── それは見落としがちなポイントですね。会社設立時に想定していなかった場合、後から追加する必要があるわけですね。
阪本: そのとおりです。この記載の有無は、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)と定款で確認できます。もし事業目的に記載がない場合は、株主総会で事業目的の変更決議を行い、法務局への変更登録申請手続きが必要です。

── 臨時株主総会を開かなければならないとなると、けっこう手間ですね。
阪本: 臨時株主総会の開催が難しい場合は、個別に対応方法を相談されることをお勧めします。専門家に相談すれば、事業内容や株主構成に応じた最適な方法を提案してもらえるでしょう。
── ここまでのお話を伺うと、第一種貨物利用運送事業は比較的参入しやすそうな印象を受けます。他の運送事業と比べてどうなのでしょうか?
他の許可と比較した第一種貨物利用運送事業の特徴
阪本: おっしゃるとおり、第一種貨物利用運送事業は、第二種貨物利用運送事業許可や一般貨物自動車運送事業許可と比較すると、要件が比較的緩く設定されています。
── どのあたりが参入障壁が低いと言えるんでしょうか?
阪本: まず、車両や運行管理者が不要であることが大きいですね。また、純資産要件も300万円からとなっていて、一般貨物自動車運送事業の場合は事業規模によっては数千万円必要なケースもあります。そのため、物流業界へ新規参入するための足がかりとして選ばれることも多いです。
── なるほど。投資額も抑えられ、運転手の雇用も不要となると、小規模事業者でも始めやすいわけですね。最後に、登録申請を考えている事業者へのアドバイスをお願いします。
阪本: 要件は満たせそうでも、細かな確認事項や書類の準備など、実際の手続きには専門的な知識が必要です。「要件は満たせそうだが確認も含めて手続きを依頼したい」「手続きに不安があるので専門家に相談したい」といった場合は、ぜひ専門家へ相談することをお勧めします。
── 経験のある専門家に相談するのが安心ですね。
阪本: そうですね。初めての申請で不安を抱える事業者様も多いのですが、適切なサポートを受けることで、スムーズに登録を進めることができますよ。条件を満たしていても、書類の不備などで手続きが長引くケースもよくありますから。
── 本日は貴重なお話をいただき、ありがとうございました。貨物利用運送事業について、非常に理解が深まりました。
阪本: こちらこそ、ありがとうございました。これから貨物利用運送事業に挑戦される方の参考になれば幸いです。
本記事では第一種貨物利用運送事業登録の主要な要件について解説しました。具体的な申請手続きやお悩みについては、専門家への個別相談をご検討ください。
電話での問い合わせ
お電話でのお問い合わせは、平日の9:00~18:00の間、受け付けております。
お悩みについてすぐにお答えできるので、お電話でのお問い合わせをご利用いただく方も多いです。
- 都庁前オフィス(東京都新宿区):03-5843-8541
- 武蔵小杉オフィス(神奈川県川崎市):044-322-0848
お電話の際には「利用運送業のホームページを見た」とお伝えください。
なお、コンプライアンス上の理由で、匿名・電話番号非通知でのお問い合わせには対応しておりません。お問い合わせの際には会社名・お名前・ご連絡先などを伺っておりますのであらかじめご了承ください。
担当者不在時には伝言を残していただければ遅くとも翌営業日までに折り返し担当者よりお電話いたします。
※We apologize, but we are able to assist and operate in Japanese only.
メールでのお問い合わせ
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。必ず2営業日以内に返信しております。返信が届かない場合には、
- ご入力いただいたメールアドレスが間違っている
- 返信メールが迷惑メールフォルダ等に振り分けられている
- 返信メールが受信できない設定になっている
といった原因が考えられます。メールが届かない場合には、上記をご確認いただいたうえ、お手数ですが再度メールフォームよりお問い合わせください。
※We apologize, but we are able to assist and operate in Japanese only.