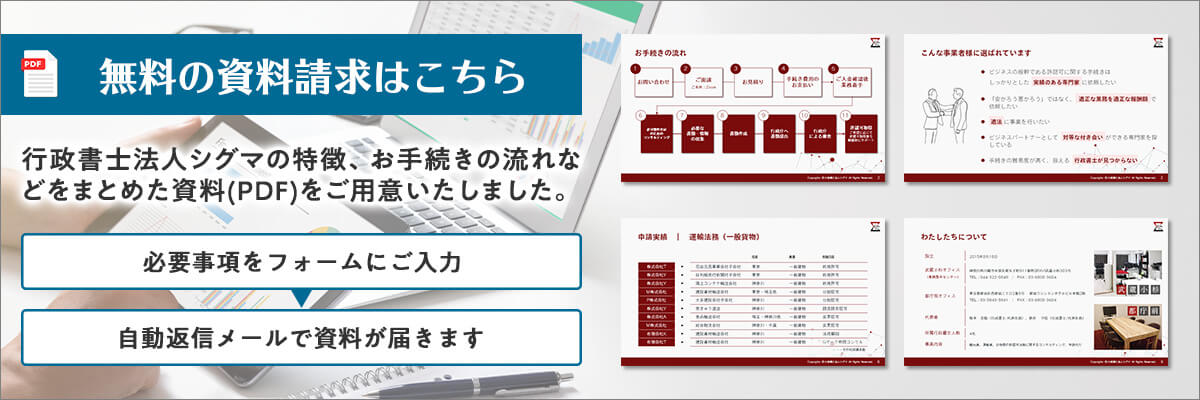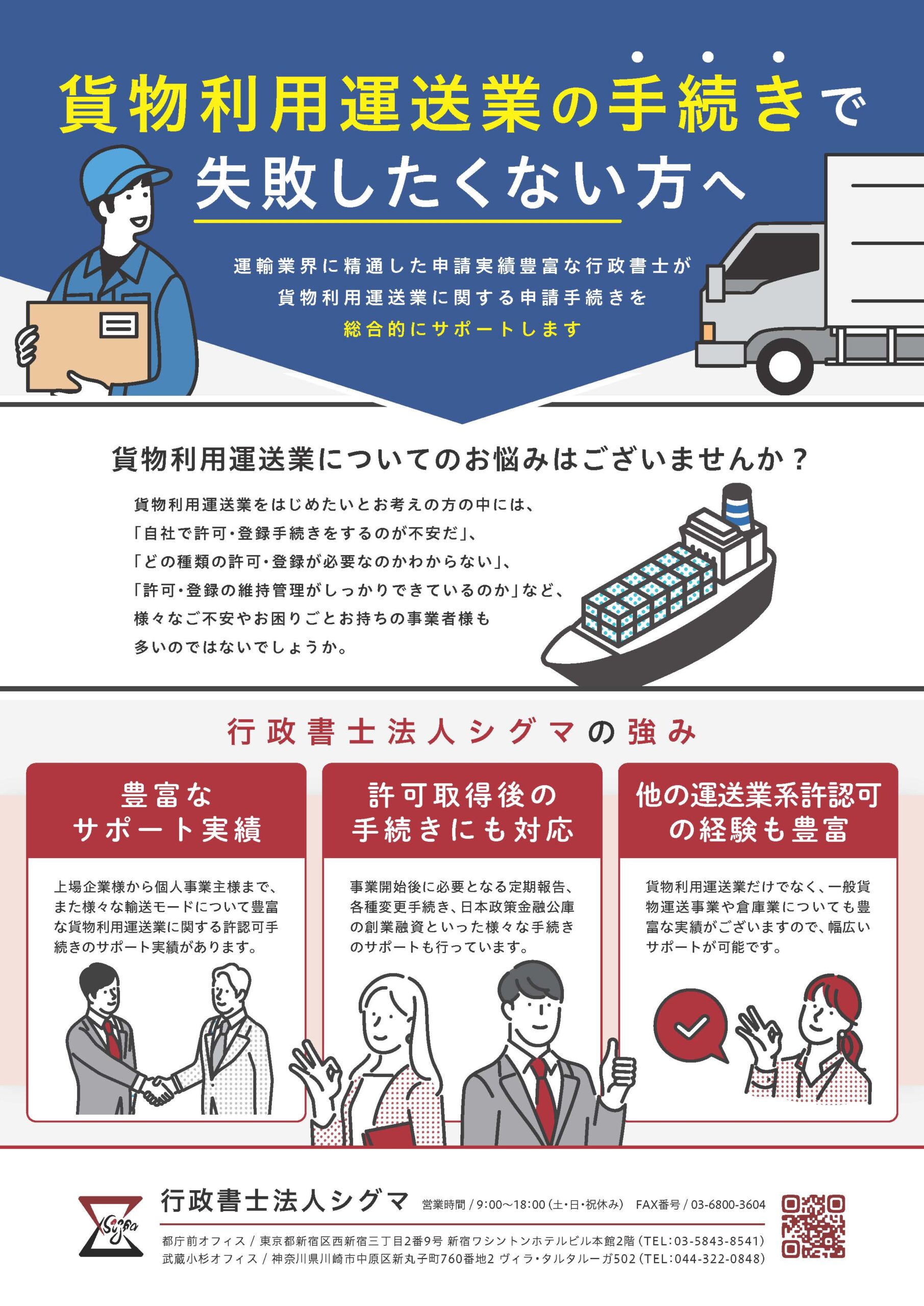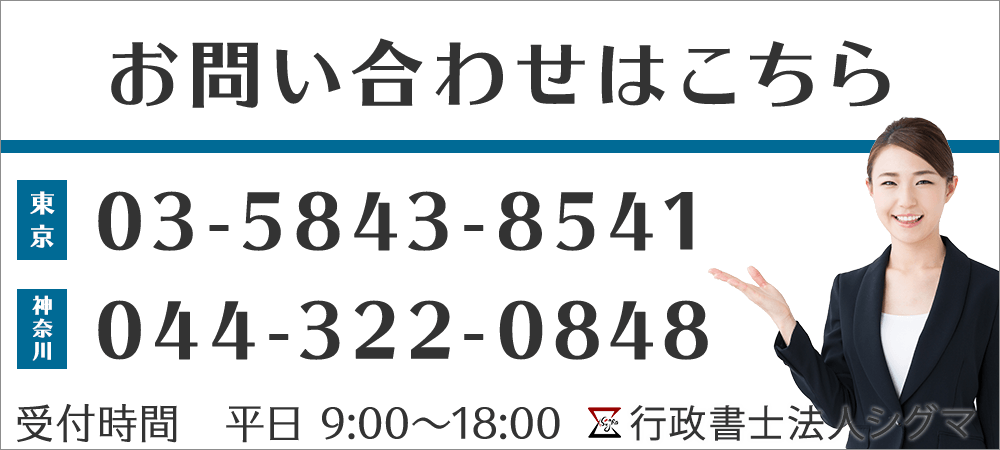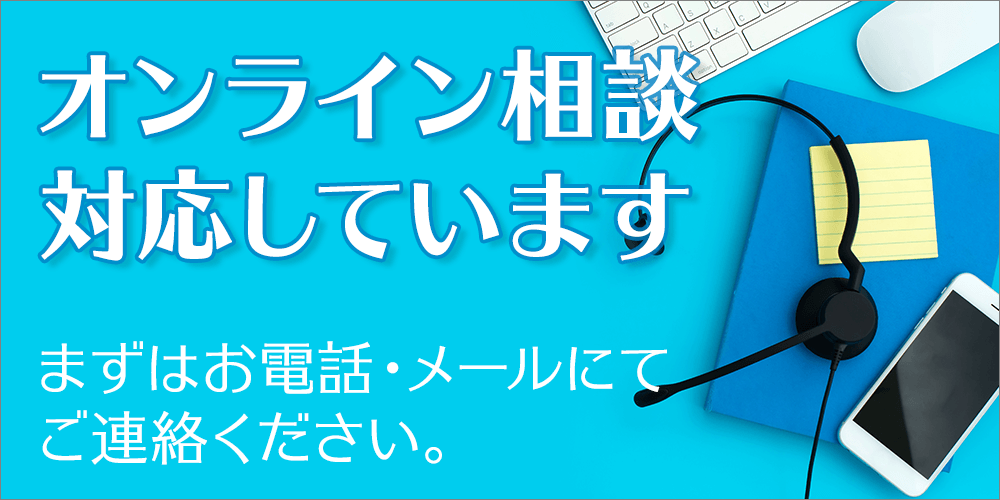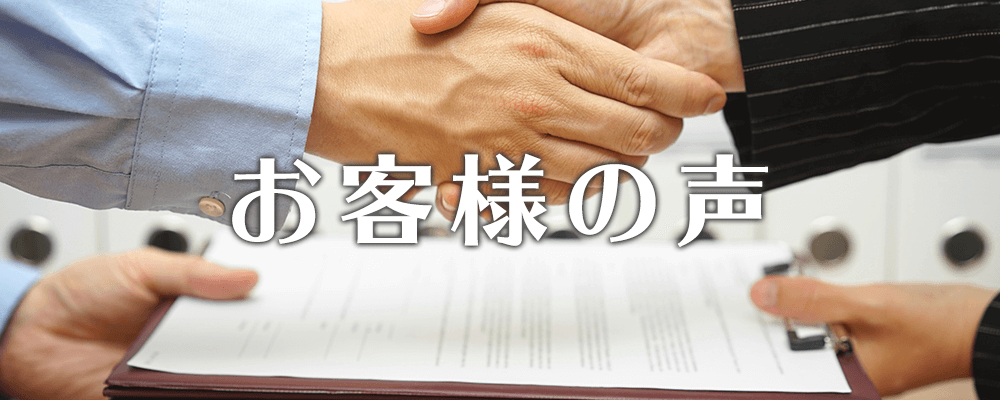今回は、運送業界における許認可法務のエキスパートとして活躍されている行政書士の阪本浩毅先生にお話を伺いました。阪本先生は10年以上にわたり運送業専門の行政書士として活動され貨物利用運送業に関する許認可手続きに精通しています。近年増加傾向にある外国資本の物流企業の事業承継についてお聞きしました。
Contents
外国人事業者と邦人事業者の区別と重要性
── 阪本先生、本日はお時間をいただきありがとうございます。まず、国際貨物利用運送事業において「邦人事業者」と「外国人事業者」という区分があると伺いましたが、この区分について教えていただけますか?
阪本:こちらこそよろしくお願いします。外航海運や国際航空といった国際貨物利用運送事業では、許認可制度において「邦人事業者」と「外国人事業者」という区分が設けられています。
この区分は相互主義と呼ばれる国際的な考え方に基づいているのですが、実はこの区分が会社の吸収合併などの事業承継の可否に大きく影響するという重要なポイントなのです。当事務所にご相談いただく案件でも、自社がどちらに分類されるのか判断できずに困っているというケースが非常に多いですね。

── なるほど、その区分が事業承継にも影響するとは知りませんでした。相互主義というのはどのような考え方なのでしょうか?
阪本:相互主義とは、簡単に言えば「お互い様」という考え方です。国際運送の分野では、相手国が自国の事業者に対して行っているのと同等の待遇を、その国の事業者に対しても行うという原則です。
例えば、ある国が日本の事業者に対して厳しい規制を課している場合、日本もその国の事業者に対して同等の規制を適用するという考え方です。これが国際貨物利用運送事業における許認可制度の基本的な枠組みになっています。
── 業界の最新動向として、この区分に関して何か変化はありますか?
阪本:近年の傾向としては、グローバル化の進展に伴い外資系物流企業の日本進出や、国内企業の外資による買収が増えています。それに伴い、「邦人事業者」から「外国人事業者」への転換や、その逆のケースも増加しています。特に2020年以降のパンデミックを経て、サプライチェーンの再構築が進む中で、こうした事業再編の動きは加速しているように感じます。法規制自体の大きな変更はありませんが、実務上の解釈やガイドラインについては徐々に整備されつつあります。
外国人事業者の定義
── では具体的に、どのような事業者が「外国人事業者」に該当するのでしょうか?
阪本:貨物利用運送事業法では、外国人事業者を次のいずれかに該当する者と定めています。
まず一つ目は「日本国籍を有しない者」、二つ目は「外国または外国の公共団体もしくはこれに準するもの」、三つ目は「外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体」です。
そして四つ目は「法人であって、上記の1〜3までに掲げる者がその代表者であるもの、またはこれらの者がその役員の3分の1以上若しくは議決権の3分の1以上を占めるもの」となります。
── その四つ目の定義について、もう少し具体的に説明していただけますか?
阪本:もちろんです。よくある例として、日本の会社法に基づいて設立された法人であっても、次のいずれかに該当する場合は外国人事業者として扱われます。
一つ目は「代表者が外国人」の場合、二つ目は「役員の3分の1以上が外国人」の場合、そして三つ目は「出資者(議決権)の3分の1以上が外国(法)人」の場合です。
私どものクライアントであるフォワーダー(貨物利用運送事業者)様の中には、これらの条件の全てに該当し、明確に外国人事業者として分類されているケースが多いですね。例えば、ある欧州系の物流企業の日本法人では、代表取締役が本国からの送り出された役員で、取締役会の半数以上が外国籍、さらに株式の100%を外国の親会社が保有しているというケースがありました。こうしたケースは典型的な外国人事業者の例です。
── 「3分の1以上」という基準は何か特別な意味があるのでしょうか?
阪本:会社法では、重要事項の決議には3分の2以上の賛成が必要な場合が多いのですが、その裏を返せば、3分の1を超える議決権があれば拒否権を持つことができます。つまり、経営に対して重要な影響力を持ち得る割合として「3分の1以上」という基準が設けられているのです。これは国際的にも類似の基準が採用されていることが多いですね。
事例1:外国人貨物利用運送事業者の吸収合併
── 具体的な事例についてお聞きしたいと思います。まず、外国人貨物利用運送事業者を吸収合併するケースについて教えていただけますか?
阪本:代表的な事例として、外航海運に関する外国人貨物利用運送事業者を吸収合併し、その事業を承継したいというケースがあります。ここで重要なポイントは、邦人事業者同士の合併と外国人事業者が関わる合併では、適用されるルールが大きく異なるということです。
邦人事業者同士の合併であれば、第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業のどちらであっても、貨物利用運送事業法令に規定されている手続きを踏むことで、事業の許認可を承継することが可能です。具体的には、第一種であれば届出、第二種であれば認可申請を行うことで、消滅会社の許認可は存続会社に引き継がれます。
── それに対して、外国人事業者の場合はどうなるのでしょうか?
阪本:外国人国際貨物利用運送事業者を吸収合併する場合は、吸収合併消滅会社が取得している貨物利用運送事業の許認可を承継することができません。これは、外国人国際貨物利用運送事業には、邦人事業者のような吸収合併による許認可承継の規定が整備されていないためです。
実例を挙げると、ある日本の物流会社が香港系の貨物利用運送事業者を吸収合併しようとしたケースでは、合併によって消滅する香港系企業の許認可を引き継ぐことができず、結局、合併存続会社が新たに許認可を取得するという二段階のプロセスを踏まなければなりませんでした。
── それは大変ですね。実務上の落とし穴として何か注意点はありますか?
阪本:最も注意すべき点は、M&Aの計画段階で許認可の承継可能性を確認することです。多くの企業が「合併すれば許認可も自動的に引き継げる」と誤解しており、合併直前になって問題が発覚するケースが少なくありません。
また、もう一つの落とし穴として、新規許認可の取得には一定の時間がかかることが挙げられます。特に外航海運の場合、申請から許可までに通常4ヶ月程度必要ですので、合併スケジュールを立てる際には、この期間を十分に考慮する必要があります。
さらに、担当官の事務処理状況や年度末の担当官の異動時期に審査期間が重なると許認可取得に時間がかかるケースもあります。合併スケジュールには余裕をもった方がよいと言えるでしょう。
事例2:代表者兼100%株主である外国人の帰化
── 次に、代表者の国籍変更があった場合のケースについても教えていただけますか?
阪本:実際に私たちが支援したケースとして、代表者の方が外国籍で、その方以外の役員はおらず、その外国籍の代表者が会社の株式全てを保有しているというケースがありました。この会社は代表者が外国籍であったため、外航海運に関する貨物利用運送事業を「外国人国際貨物利用運送事業」として取得し、事業を展開していました。
その後、代表者の方が日本国籍を取得(帰化)したのですが、ここで問題が生じました。直感的には、貨物利用運送事業の「外国人事業者」から「邦人事業者」への変更手続きを行えば良さそうですが、実は貨物利用運送事業法令では外国人と邦人間の国籍変更に関する規定が定められていないのです。

── それはどのように解決されたのでしょうか?
阪本:このケースでは、邦人事業者として新たに国際貨物利用運送事業の許認可取得の申請を行い、許認可を取得した後に、元の外国人国際貨物利用運送事業を廃業するという二段階の行政手続きが必要になりました。
具体的には、まず新たに「邦人事業者」としての許認可申請を行い、それが認められた後に、既存の「外国人事業者」としての許認可を返納するという流れです。この間、業務に支障が出ないよう、タイミングを慎重に調整する必要がありました。
── 興味深いケースですね。このような国籍変更のケースは増えていますか?
阪本:はい、近年は増加傾向にあります。特に日本で長く事業を展開している外国人経営者の中には、より安定した事業基盤を築くために日本国籍を取得するケースが見られます。また、外国人と日本人のビジネスパートナー間での株式譲渡や役員構成の変更により、「外国人事業者」から「邦人事業者」、あるいはその逆の変更が生じるケースも少なくありません。
── そのような場合の実務上の注意点はありますか?
阪本:最も重要なのは、国籍変更や株式構成の変更が生じた場合、速やかに許認可への影響を確認することです。実務上、こうした変更後も従来通りの許認可で事業を継続してしまい、後になって問題が発覚するケースが多いです。
また、新規許認可の取得には財務要件や人的要件など各種条件がありますので、これらの条件を事前に確認し、必要な準備を行うことも重要です。
外国人貨物利用運送事業者の会社分割・事業譲渡
── 吸収合併以外の事業承継方法についても教えていただけますか?
阪本:貨物利用運送事業では、「邦人事業者」と「外国人事業者」では適用ルールが異なることは先ほど触れたとおりですが、吸収合併以外にも、新設合併・吸収分割・新設分割・事業の譲渡・相続といった事業承継の場面でも同様の問題が生じます。
具体的には、外航海運や国際航空に関する外国人国際貨物利用運送事業は、これらの方法によっても承継することができません。これは、貨物利用運送事業法令で承継の規定が設けられていないためです。
例えば、ある外資系フォワーダーが事業の一部を会社分割により新会社に移管しようとしたケースでは、新会社は改めて許認可を取得する必要がありました。また、外国人事業者から邦人事業者への事業譲渡においても同様に、譲受会社が新たに許認可を取得する必要がありました。
── 業界の最新動向として、こうした事業承継に関する法規制に変化はありますか?
阪本:近年、国際物流の重要性が高まる中で、事業承継をよりスムーズに行えるように規制緩和を求める声が業界から上がっています。特に、外資系企業と国内企業の間での事業再編が増加している現状を踏まえ、より柔軟な制度設計を求める動きがあります。
ただ、現時点では大きな法改正は行われておらず、引き続き従来の枠組みの中で対応する必要があります。そのため、事業承継を計画する際には、初期段階から専門家に相談し、最適な方法を検討することが重要です。
まとめと今後の展望
── 最後に、外国人事業者が関わる利用運送事業の事業承継について、アドバイスをいただけますか?
阪本:貨物利用運送事業を組織再編する際は、まず相手方の事業者が「邦人事業者」なのか「外国人事業者」なのかを正確に把握することが出発点となります。これによって適用される法規制や必要な手続きが大きく異なってくるためです。
また、事業承継の計画段階から許認可の承継可能性を確認し、必要に応じて新規許認可の取得準備を並行して進めることが重要です。特に国際的な企業再編の場合、複数国の法規制が関わるため、各国の専門家と連携しながら進めていく必要があります。
さらに、今後の展望として、特にアジア地域での物流網の再編が活発化する中で、外資系企業の日本進出や日本企業の海外展開がさらに増加すると予想されます。それに伴い、許認可の国際的な相互承認や手続きの簡素化が進む可能性もあります。
私たちは、外国人事業者の関わる利用運送事業のM&Aなど事業承継に関するコンサルティングと手続きサポートを提供しておりますので、外国人事業者に関する利用運送事業の承継でお悩みの方はご相談ください。グローバルな視点と日本の法規制に精通した専門家として、最適な解決策をご提案いたします。
── 阪本先生、大変貴重なお話をありがとうございました。国際物流における許認可の複雑さと事業承継の重要ポイントがよく理解できました。今後も業界の動向に注目していきたいと思います。
電話での問い合わせ
お電話でのお問い合わせは、平日の9:00~18:00の間、受け付けております。
お悩みについてすぐにお答えできるので、お電話でのお問い合わせをご利用いただく方も多いです。
- 都庁前オフィス(東京都新宿区):03-5843-8541
- 武蔵小杉オフィス(神奈川県川崎市):044-322-0848
お電話の際には「利用運送業のホームページを見た」とお伝えください。
なお、コンプライアンス上の理由で、匿名・電話番号非通知でのお問い合わせには対応しておりません。お問い合わせの際には会社名・お名前・ご連絡先などを伺っておりますのであらかじめご了承ください。
担当者不在時には伝言を残していただければ遅くとも翌営業日までに折り返し担当者よりお電話いたします。
※We apologize, but we are able to assist and operate in Japanese only.
メールでのお問い合わせ
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。必ず2営業日以内に返信しております。返信が届かない場合には、
- ご入力いただいたメールアドレスが間違っている
- 返信メールが迷惑メールフォルダ等に振り分けられている
- 返信メールが受信できない設定になっている
といった原因が考えられます。メールが届かない場合には、上記をご確認いただいたうえ、お手数ですが再度メールフォームよりお問い合わせください。
※We apologize, but we are able to assist and operate in Japanese only.