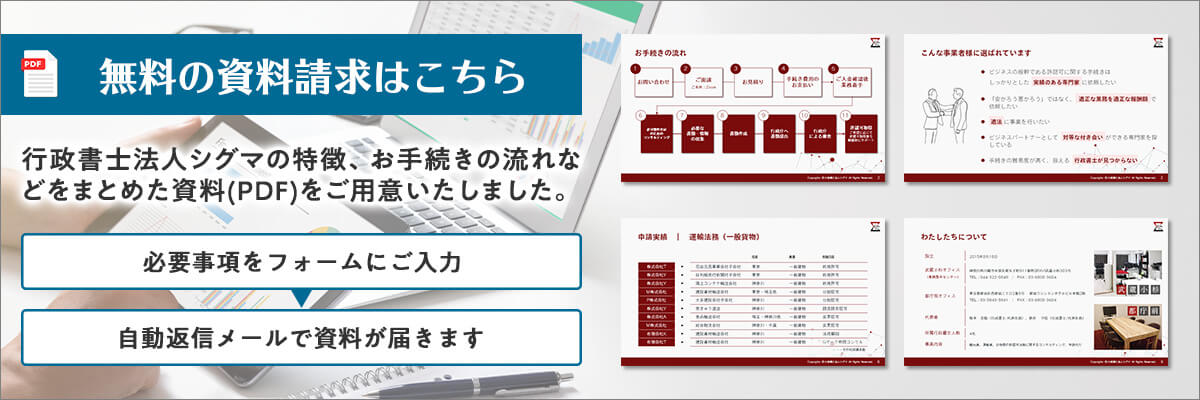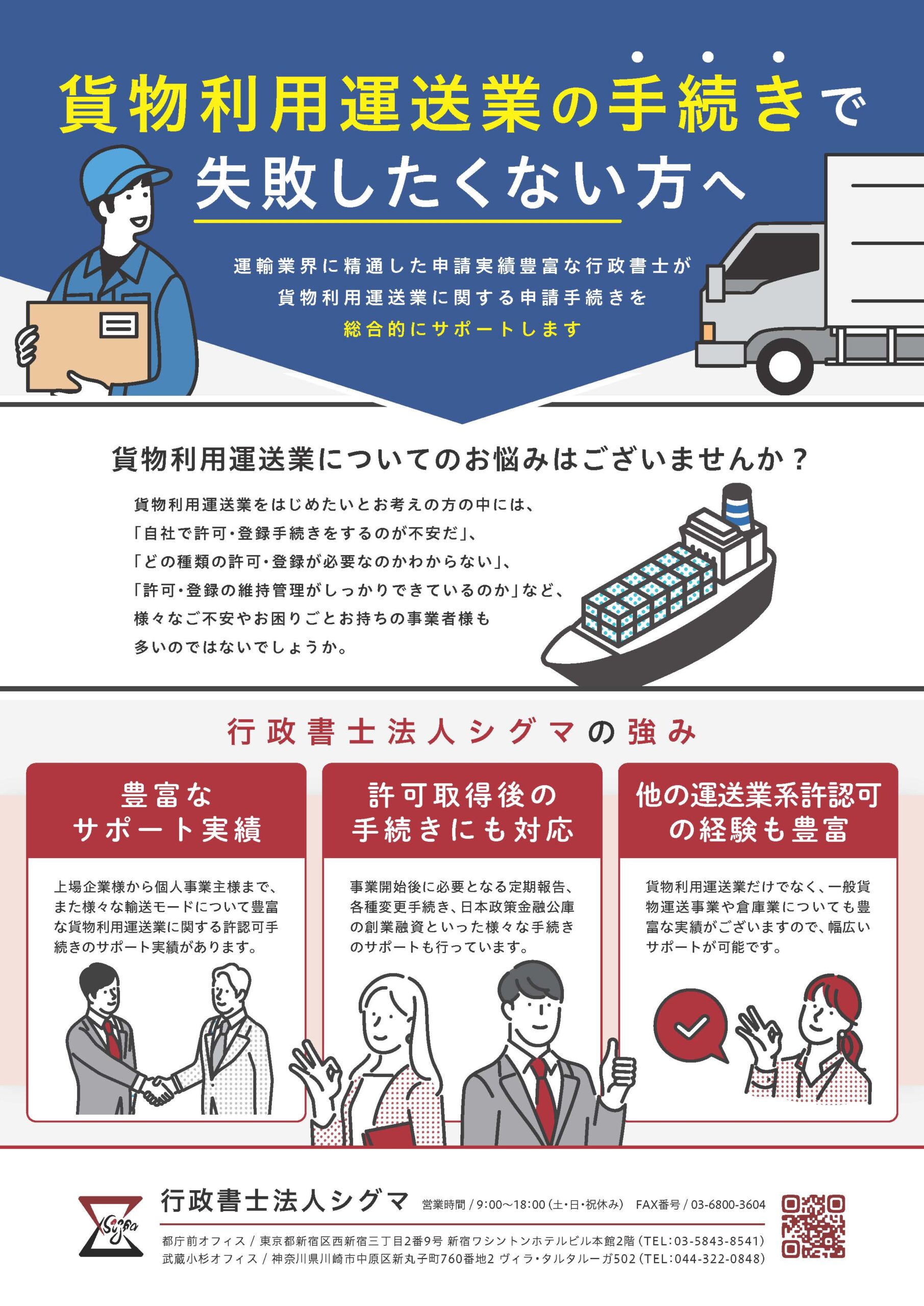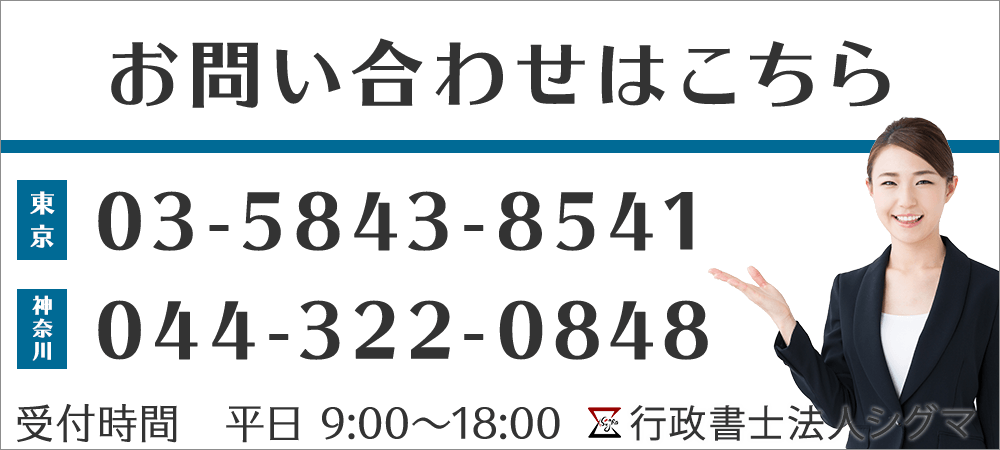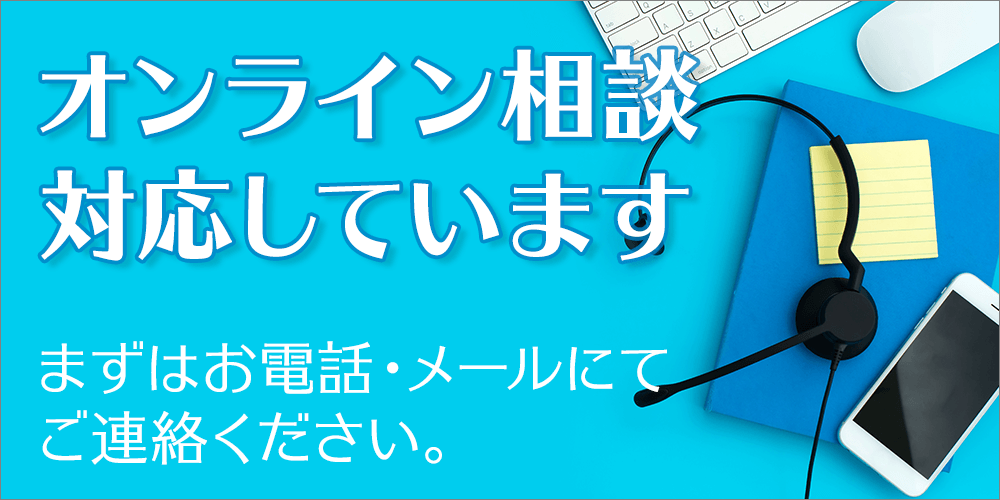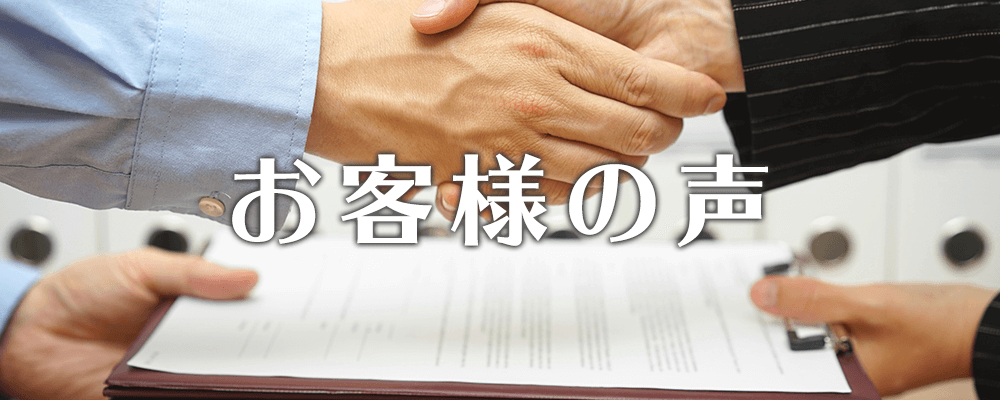今回は、運送事業に特化した行政書士として第一線で活躍する阪本浩毅氏にお話を伺います。阪本氏は多くの貨物利用運送事業の許認可取得をサポートした実績を持つエキスパートとして知られています。許認可取得の秘訣から最新の業界動向まで、貴重なアドバイスをいただきました。
Contents
貨物利用運送事業の許認可取得前に知っておくべきこと
── 阪本先生、本日はお忙しい中ありがとうございます。まず初めに、貨物利用運送事業の許認可を初めて取得しようとする事業者が抱える一般的な疑問からお聞きしたいと思います。多くの事業者が必要書類や提出先、取得までの期間などを気にされていると思いますが、実際にはそれ以前に考えるべきことがあるのでしょうか?
阪本:ご質問ありがとうございます。おっしゃる通り、多くの事業者様は申請書類や手続き期間についてまず質問されます。確かにそれらは重要ですが、実はもっと根本的な部分から考える必要があります。行政書士としての経験から申し上げると、事業者様が貨物利用運送事業法令の許認可条件を満たしているかどうかを確認することも大切ですが、それ以前に決めておかなければならないことがあります。それは、ご自身のビジネスモデルを明確にすることです。

── ビジネスモデルを明確にするとは、具体的にどういうことでしょうか?
阪本:貨物利用運送事業の許認可申請は、事業種別や輸送モードごとに個別の手続きが必要になります。つまり、どのような事業を展開するのかを明確にしないと、必要な許認可さえ特定できないのです。例えば、国際輸送と国内輸送では必要な許認可が異なりますし、海上輸送と航空輸送でも申請内容が変わってきます。私がよく経験するのは、「物流事業を始めたい」という漠然とした構想だけで相談に来られる方が、具体的な事業計画を立てる段階で予想外の壁にぶつかるケースです。
貨物利用運送事業のビジネスモデルを決める
── 貨物利用運送事業のビジネスモデルとは、どのような要素から構成されるのでしょうか?
阪本:貨物利用運送事業は大きく分けて第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業の2種類があります。第一種には貨物自動車、外航、内航、鉄道、国内航空、国際航空の6つの運送機関があり、第二種には貨物自動車を除いた5つの運送機関があります。これらは輸送モードとも呼ばれています。
── なるほど。その中からどれを選ぶべきかは、どのように決めればよいのでしょうか?
阪本:それは事業者様が展開したいビジネスによって決まります。例えば、国内で陸上輸送を中心に考えている場合は第一種貨物利用運送事業の貨物自動車が必要になりますが、国際海上コンテナの輸送を扱うなら外航の許認可が必要です。私の経験では、特にスタートアップ企業の方々は複数の輸送モードを組み合わせたサービスを考えていることが多く、その場合は複数の許認可申請が必要になることもあります。
── 最近ではEコマースの拡大に伴い、物流ニーズも多様化していますよね。そうした変化も影響しているのでしょうか?
阪本:その通りです。特に過去5年でEコマース市場は大きく拡大し、物流のあり方も変わってきています。以前は大量輸送が中心でしたが、現在は小口多頻度配送のニーズが高まっており、それに合わせたビジネスモデルの構築が求められています。また、サステナビリティへの関心の高まりから、環境負荷の少ない複合輸送を選択する企業も増えています。例えば、長距離は鉄道や内航船、集貨・配達はトラックといった組み合わせです。このような最新トレンドも踏まえたビジネスモデル設計が重要になっています。
決めておかなければならないビジネスモデルの内容
── ビジネスモデルを具体的に決める際に、どのような要素を考慮すべきでしょうか?
阪本:許認可取得に必要なビジネスモデルには、いくつかの重要な要素があります。まず、どのような貨物を輸送するのかを明確にする必要があります。次に、貨物の発地と着地はどこなのか、これは国内か国際かという点も含めて重要です。
また、輸送手段は何を使うのか、例えばトラック、船舶、航空機、鉄道などどの手段を用いるのかも決める必要があります。さらに、運送を委託する運送会社はどこなのか、これは申請時に運送委託契約書のコピーが必要になりますので、事前に契約先を確定しておく必要があります。最後に、貨物利用運送事業の業務を行う事務所(営業所)をどこに置くのかも決めておかなければなりません。
── 運送委託契約書が必要ということは、実際に運送会社と契約を結んでからでないと申請できないということでしょうか?
阪本:そのとおりです。漠然と「貨物利用運送事業を始めたい」という段階では申請に必要な書類が揃わないのです。許認可申請の際には、委託する実運送会社や他の貨物利用運送事業者との間で締結した運送委託契約書のコピーを提出する必要があります。
例えば、私が支援した家具輸送専門の貨物利用運送事業者は、当初は契約先の運送会社が見つからず苦労していました。家具という特殊な貨物を扱えるトラック事業者との交渉に時間がかかったのです。また別のケースでは、外航海運の許認可を取得したいフォワーダーが、コンテナ船運航会社との契約に苦戦し、結果的に既存の貨物利用運送事業者である大手フォワーダーを介した利用の利用の契約になったという例もあります。
── なるほど。実務上の落とし穴としては他にどのようなことがありますか?
阪本:実務上よく見られる落とし穴としては、営業所の要件を満たしていないケースがあります。特に自宅を営業所として使用する場合、賃貸契約で事業利用が認められているか、住居専用地域ではないかなどの確認が必要です。また、財政的基礎の証明において、直近決算期時点の純資産額が300万円未満であったというケースもよくあります。
さらに、最近増えているのが、外国籍の方が代表者となる場合の在留資格の問題です。特定の在留資格でないと事業経営が認められないケースがあります。このような細かい点も事前に確認しておくことが重要です。
貨物利用運送事業に関するご相談のタイミング
── 行政書士への相談は、ビジネスモデルが固まってからが良いのでしょうか?それとも検討段階からでも相談した方が良いのでしょうか?
阪本:理想的には、ビジネスモデルがある程度固まった状況で行政書士にご相談いただくと、許認可取得手続きはスムーズに進みます。ただ、貨物利用運送事業のビジネスモデルを自社だけで構築するのは難しいという事業者様も多くいらっしゃいます。
また、多くの事業者様は、ビジネスモデルの検討と並行して、自社が許認可取得の条件を満たしているかどうかを確認したいというご要望もあります。例えば、必純資産要件や利用する運送事業者との契約関係をどのように証明するかや、事業用施設の基準など、許認可取得には様々な基準があります。それらを早めに把握しておくことで、不足している部分を事前に補うことができます。
── そうした事業者向けに、どのようなサポートを提供されているのでしょうか?
阪本:私どもでは、単に申請書類の作成や提出代行にとどまらず、貨物利用運送事業のビジネスモデル構築から許認可取得要件の調整までを含めたコンサルティングサービスを提供しています。このサービスは有料になりますが、これまでの実績とノウハウに基づいて、許認可取得までの準備期間を短縮し、リスクも低減できるよう支援しています。
例えば、ある食品輸送を手がける企業様の場合、当初は単独での許認可取得を検討されていましたが、コンサルティングの結果、グループ会社との共同事業の形で申請する方が効率的であるとアドバイスし、結果的に申請から許可まで通常より1ヶ月短い期間で取得できました。

貨物利用運送事業の許認可取得を成功させるために
── 最後に、これから貨物利用運送事業の許認可取得を目指す事業者へのアドバイスをお願いします。
阪本:貨物利用運送事業の許認可取得を成功させるためには、三つの重要なポイントがあると考えています。
一つ目は「準備と計画」です。許認可申請は単なる書類手続きではなく、ビジネスモデルの構築から始まる総合的なプロジェクトです。最低でも3〜6ヶ月の準備期間を見込み、段階的に進めることをお勧めします。特に実運送事業者との契約交渉は時間がかかることが多いので、早めに着手しましょう。
二つ目は「専門家の活用」です。許認可手続きは複雑で、法改正も頻繁にあります。専門知識を持つ行政書士を活用することで、時間とコストの節約になります。特に初めての申請では、経験者のサポートが大きな助けになります。
三つ目は「業界動向の把握」です。物流業界は今、大きな変革期にあります。Eコマースの拡大、環境規制の強化、人手不足など、様々な課題と機会があります。これらの動向を踏まえたビジネスモデルを構築することが、許認可取得後の事業成功にも繋がると考えます。
私の経験では、しっかりとした準備と適切なサポートがあれば、貨物利用運送事業の許認可取得は決して難しいものではありません。ぜひ前向きに取り組んでいただければと思います。また、業界の発展のためにも、新しいアイデアや技術を取り入れた革新的な事業者の参入を歓迎したいと思っています。
── 阪本先生、大変貴重なお話をありがとうございました。これから貨物利用運送事業への参入を考えている事業者の方々にとって、非常に参考になる内容だったと思います。
電話での問い合わせ
お電話でのお問い合わせは、平日の9:00~18:00の間、受け付けております。
お悩みについてすぐにお答えできるので、お電話でのお問い合わせをご利用いただく方も多いです。
- 都庁前オフィス(東京都新宿区):03-5843-8541
- 武蔵小杉オフィス(神奈川県川崎市):044-322-0848
お電話の際には「利用運送業のホームページを見た」とお伝えください。
なお、コンプライアンス上の理由で、匿名・電話番号非通知でのお問い合わせには対応しておりません。お問い合わせの際には会社名・お名前・ご連絡先などを伺っておりますのであらかじめご了承ください。
担当者不在時には伝言を残していただければ遅くとも翌営業日までに折り返し担当者よりお電話いたします。
※We apologize, but we are able to assist and operate in Japanese only.
メールでのお問い合わせ
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。必ず2営業日以内に返信しております。返信が届かない場合には、
- ご入力いただいたメールアドレスが間違っている
- 返信メールが迷惑メールフォルダ等に振り分けられている
- 返信メールが受信できない設定になっている
といった原因が考えられます。メールが届かない場合には、上記をご確認いただいたうえ、お手数ですが再度メールフォームよりお問い合わせください。
※We apologize, but we are able to assist and operate in Japanese only.