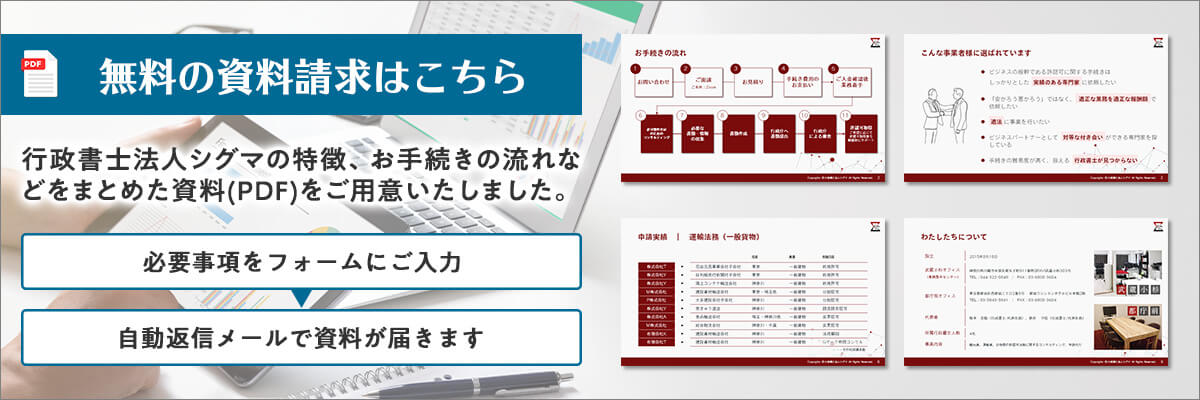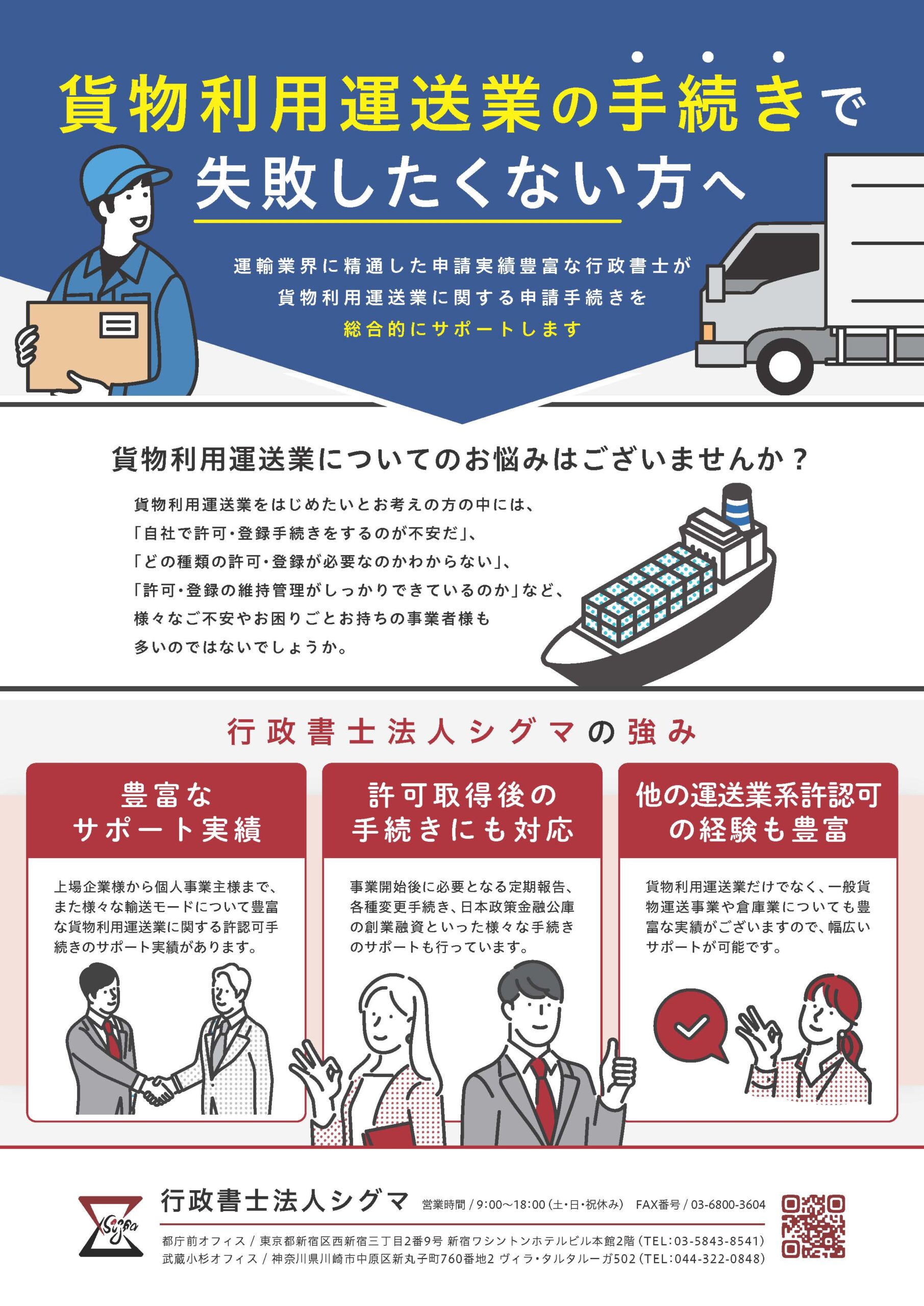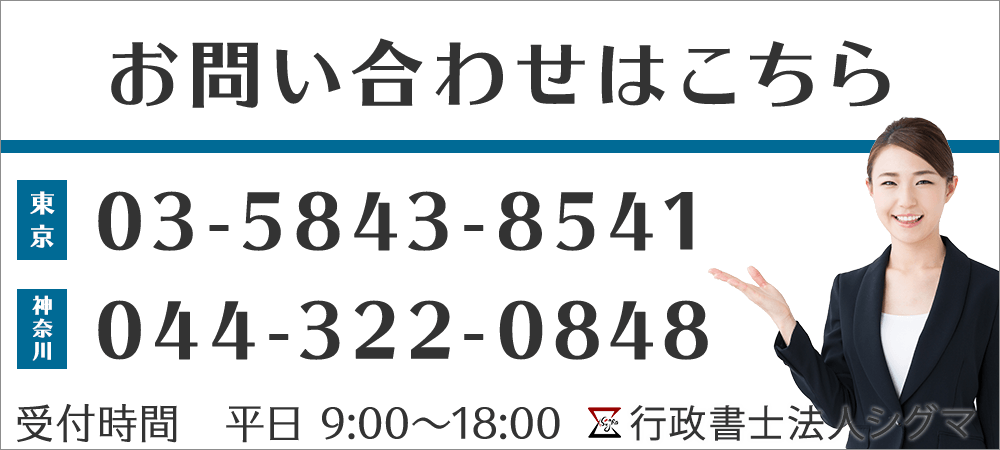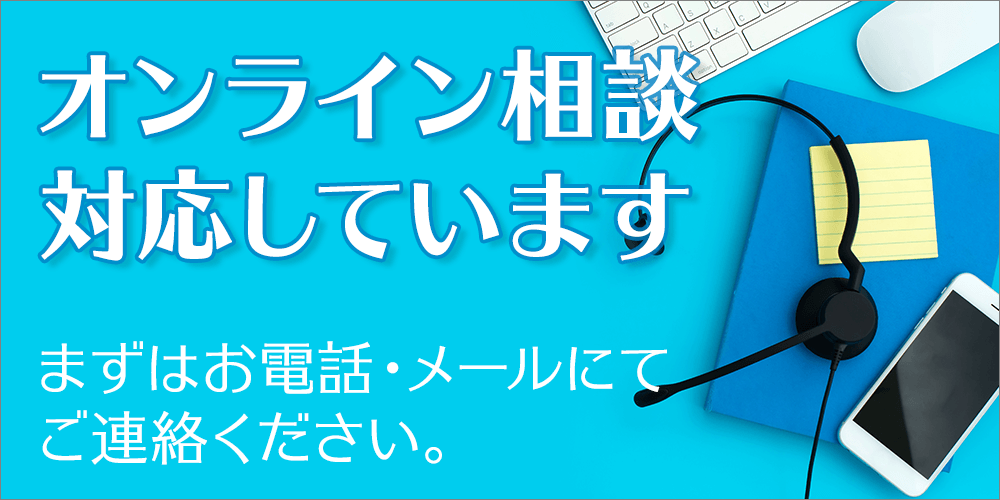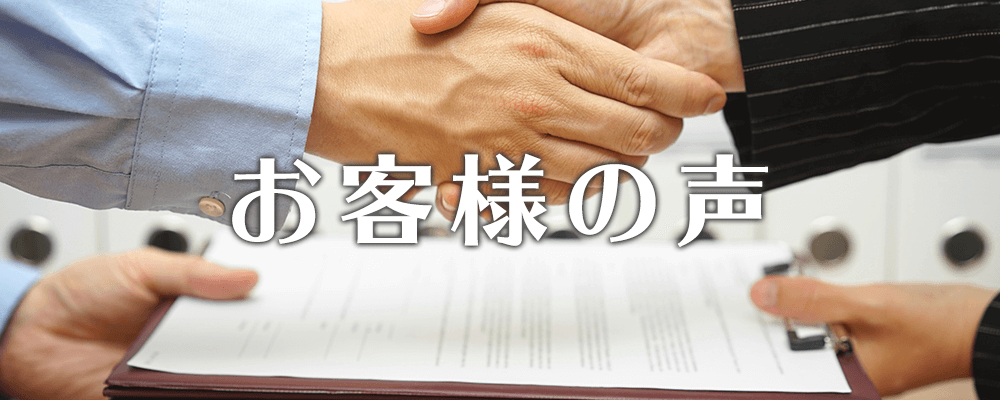今回は、運送業界の許認可手続きに精通する専門家、阪本浩毅氏をお招きしました。阪本氏は10年以上にわたり運送業の許認可申請をサポートし、特に貨物利用運送事業の許認可取得における財産的要件について深い知見を持っています。近年の法改正や申請実務の変化にも詳しく、多くの事業者の円滑な許認可取得をサポートしてきた実績を持つ行政書士です。
Contents
貨物利用運送事業の許認可と財産的基礎
── 本日は貨物利用運送事業の許認可について詳しくお聞きしたいと思います。まず、許認可取得に必要な財産的要件について教えていただけますか?
阪本:はい。貨物利用運送事業の許認可を取得するための要件のひとつに財産的基礎と呼ばれる要件があります。具体的には、純資産額が300万円以上なければならないという条件です。これは貨物利用運送事業法施行規則に明確に規定されている要件で、この条件を満たさない場合、つまり純資産額が300万円未満の会社が申請しても、許認可を取得することはできません。

── なるほど、300万円という具体的な金額が定められているんですね。申請時に特に注意すべき点はありますか?
阪本:はい、特に注意していただきたいのは、この300万円という金額は銀行口座の残高ではなく、あくまでも会計上の純資産額だということです。「口座に300万円あるから大丈夫だろう」と勘違いされる方が非常に多いのですが、純資産額は貸借対照表上の数値であり、預貯金の残高とは全く別の概念です。
純資産額300万円以上が要求される理由
── なぜこのような金額が設定されているのでしょうか?法令で300万円と定められた背景には何があるのですか?
阪本:これは荷主保護という観点から設けられた要件です。貨物利用運送事業者は、荷主に対する運送責任を一義的に負います。つまり、何か問題が発生した場合、最終的には貨物利用運送事業者が荷主に対して責任を負うことになるのです。
例えば、荷物の破損や紛失が生じた場合、あるいは配送の遅延によって荷主が損害を被った場合などに、きちんと補償できる体制が必要です。そこで「荷主を適切に保護するためには、最低限このくらいの財産的基盤が必要だ」という考えから、純資産額300万円以上という要件が定められているわけです。
── 具体的な事例で言うと、どのようなケースが考えられますか?
阪本:例えば、高額な精密機器を輸送中に破損させてしまったケースを考えてみましょう。この場合、荷主に対して数百万円の賠償責任が生じる可能性があります。また、冷凍食品などの温度管理が必要な商品で、適切な温度管理ができずに商品価値が失われてしまったような場合も、大きな賠償責任が発生します。さらに、納期の遅延によって荷主のビジネスに損害を与えてしまうようなケースもあります。
このような状況に適切に対応できるよう、一定の財産的基盤を求めているのです。なお、これは最低限の要件であり、取扱貨物の価値や量によっては、より多くの財産的基盤や保険の加入などが実務上必要になることも多いです。
純資産額とは?
── 純資産額について詳しく教えていただけますか?具体的にはどこを見て判断すればいいのでしょう?
阪本:会社の場合、純資産額は税務署に提出した直近の決算書の貸借対照表に記載されている数値です。貸借対照表の「純資産の部」に記載されている合計額を見ます。
新しく設立したばかりの会社で、まだ初回の決算を迎えていない場合は、設立時の資本金の額が判断基準になります。この場合、資本金が300万円以上あれば問題ありません。
── 直近の決算で赤字だった場合はどうなりますか?申請できなくなってしまうのでしょうか?
阪本:よくご相談いただく内容ですね。直近の決算期の損益が赤字であっても、貸借対照表上の純資産額が300万円以上であれば許認可申請は可能です。
例えば、資本金が500万円の会社が、直近の決算で150万円の赤字を出した場合でも、純資産額は350万円となり、300万円以上という要件は満たしていますので申請は可能です。ただし、赤字が継続して純資産額が減少傾向にある場合は、将来的に基準を下回るリスクがありますので注意が必要です。
── 純資産額が300万円以上あればそれでいいのでしょうか?
阪本:貨物利用運送事業の基準資産額である300万円以上というのは、創業費その他の繰延資産や営業権を除いた金額です。純資産額が500万円であっても、繰延資産が300万円ある場合は、貨物利用運送事業の基準資産額は500万円から300万円を引いた200万円となります。従って、300万円未満ですので、貨物利用運送事業の基準資産額を満たしていないことになります。
純資産額が300万円未満の場合の対処法
── 純資産額が300万円に満たない場合、どのような対処法がありますか?
阪本:最も一般的で効果的な方法は、増資手続きを行うことです。増資とは資本金の額を増やす手続きで、これにより純資産額を増やすことができます。
増資すべき金額は事業者様ごとに異なりますが、直近の月次貸借対照表での純資産額が300万円に対していくら不足しているかで判断します。例えば、現在の純資産額が200万円であれば、少なくとも100万円以上の増資が必要ということになります。
直近の純資産額がわからない場合には、顧問税理士の方に確認するとよいでしょう。また、資金状況に不安がある場合は、事前に専門家にご相談いただくことをお勧めします。相談する場合は月次試算表を準備してください。
債務超過の場合
── 債務超過の場合、つまり純資産額がマイナスの場合はどうすればよいのでしょうか?
阪本:債務超過の状態では、許認可取得のハードルがさらに高くなります。例えば、純資産額がマイナス200万円の場合、300万円以上にするためには少なくとも500万円の増資が必要になります。
このようなケースでは、必要な増資額が大きくなるため、増資が難しいという結論になることも少なくありません。実際に、債務超過で-500万円という状況から、800万円以上の増資が必要になり、断念せざるを得なかったというケースもあります。
そこで、代替策として考えられるのが、新たに資本金300万円で子会社を設立し、その会社で貨物利用運送事業の許認可を取得するという方法です。これは特に既存事業が他にあり、その事業の業績が芳しくない場合に検討される選択肢です。

── そのような新会社設立の際の注意点はありますか?
阪本:新会社を設立する場合、最初から資本金を300万円以上にしておくことが重要です。資本金50万円や100万円で会社を設立してしまうと、後から増資手続きが必要になってしまいます。
増資手続きには法務局での手続きが必要になるため、登録免許税や司法書士さんへの報酬といった追加費用が発生します。また、増資手続きには時間もかかるため、許認可取得までのスケジュールが遅れてしまう可能性があります。
最近では、資本金1円から会社設立ができるようになりましたが、貨物利用運送事業を行う予定がある場合は、最初から300万円以上の資本金で設立することをお勧めします。
まとめと専門家からのアドバイス
── 最後に、貨物利用運送事業の許認可取得を考えている事業者へのアドバイスをお願いします。
阪本:貨物利用運送事業の許認可取得において、財産的基礎要件は最も基本的な要件の一つですが、意外と多くの事業者様がつまずく部分でもあります。私からのアドバイスとしては、以下の3点を挙げたいと思います。
まず1点目は、事前の資金計画の重要性です。許認可申請の数か月前から、純資産額の状況を把握し、必要に応じて増資などの対策を計画的に行うことが重要です。
2点目は、資金的な余裕を持つことです。純資産額300万円はあくまでも最低限の要件であり、実際の事業運営では、車両の確保、人件費、保険料など様々な費用が発生します。特に事業開始直後は収益が安定しないことも多いため、余裕を持った資金計画が必要です。
3点目は、早めの専門家への相談です。「貨物利用運送事業をはじめたいが、お金の要件を満たしているかわからない」「債務超過だけど貨物利用運送事業をはじめたい」という方は、早めに専門家に相談することで、無駄な時間や費用を削減できることが多いです。
── 貴重なお話をありがとうございました。財産的基礎要件について非常に理解が深まりました。最後に読者へのメッセージをお願いします。
阪本:貨物利用運送事業は、物流業界において重要な役割を担っている事業です。適切な資金計画と準備を行い、法令遵守の姿勢を持って事業に取り組むことで、長期的に安定した事業運営が可能になります。不明点があれば早めに専門家に相談し、計画的に許認可取得を目指していただければと思います。皆様の事業の成功をお祈りしています。
電話での問い合わせ
お電話でのお問い合わせは、平日の9:00~18:00の間、受け付けております。
お悩みについてすぐにお答えできるので、お電話でのお問い合わせをご利用いただく方も多いです。
- 都庁前オフィス(東京都新宿区):03-5843-8541
- 武蔵小杉オフィス(神奈川県川崎市):044-322-0848
お電話の際には「利用運送業のホームページを見た」とお伝えください。
なお、コンプライアンス上の理由で、匿名・電話番号非通知でのお問い合わせには対応しておりません。お問い合わせの際には会社名・お名前・ご連絡先などを伺っておりますのであらかじめご了承ください。
担当者不在時には伝言を残していただければ遅くとも翌営業日までに折り返し担当者よりお電話いたします。
※We apologize, but we are able to assist and operate in Japanese only.
メールでのお問い合わせ
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。必ず2営業日以内に返信しております。返信が届かない場合には、
- ご入力いただいたメールアドレスが間違っている
- 返信メールが迷惑メールフォルダ等に振り分けられている
- 返信メールが受信できない設定になっている
といった原因が考えられます。メールが届かない場合には、上記をご確認いただいたうえ、お手数ですが再度メールフォームよりお問い合わせください。
※We apologize, but we are able to assist and operate in Japanese only.