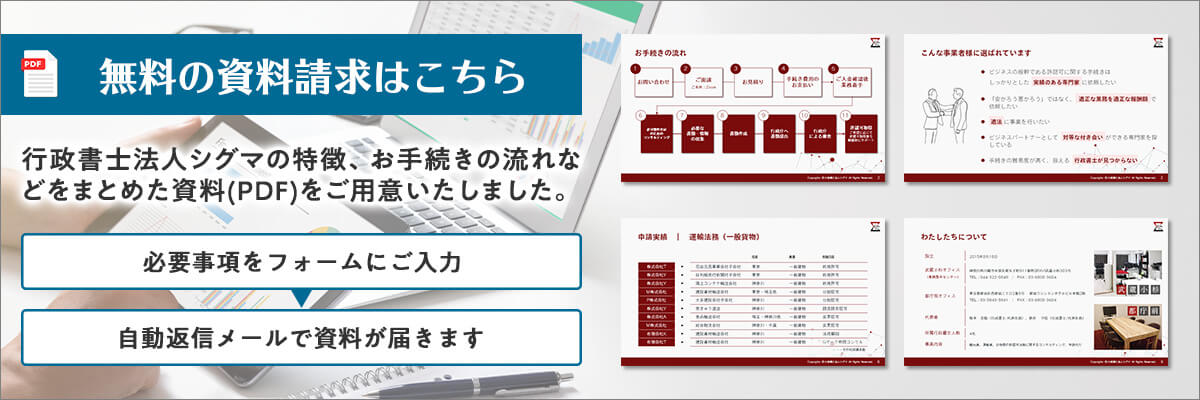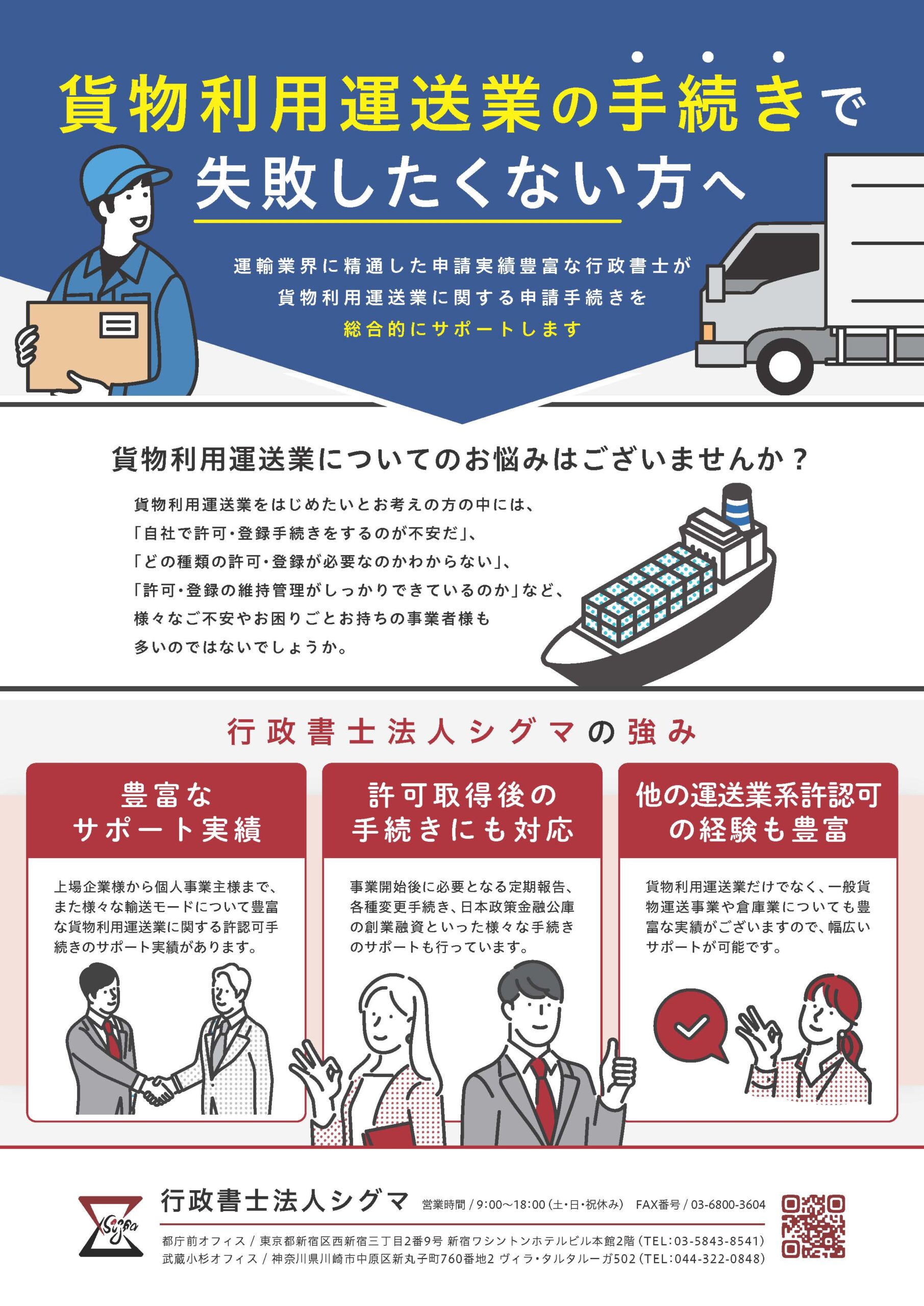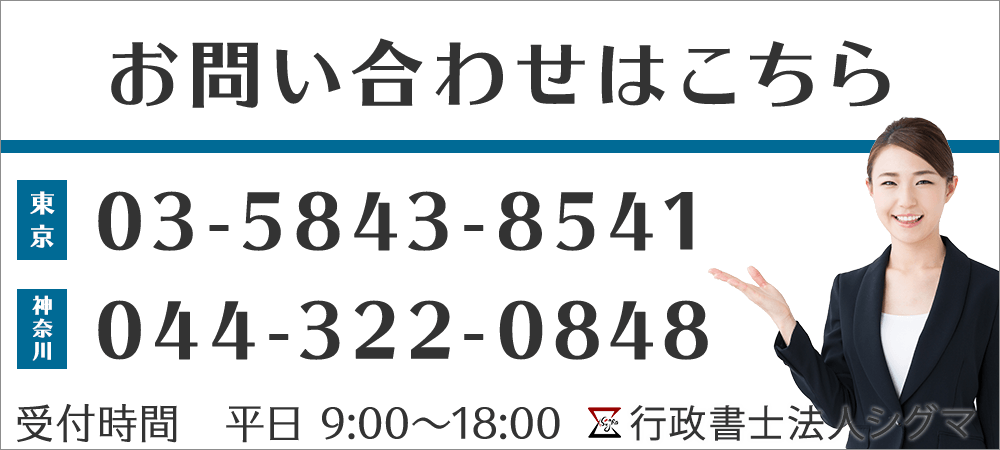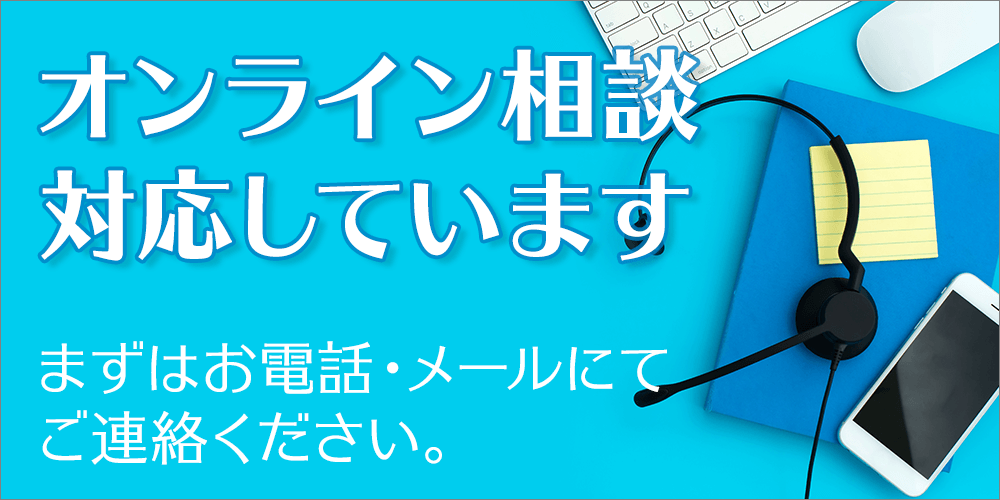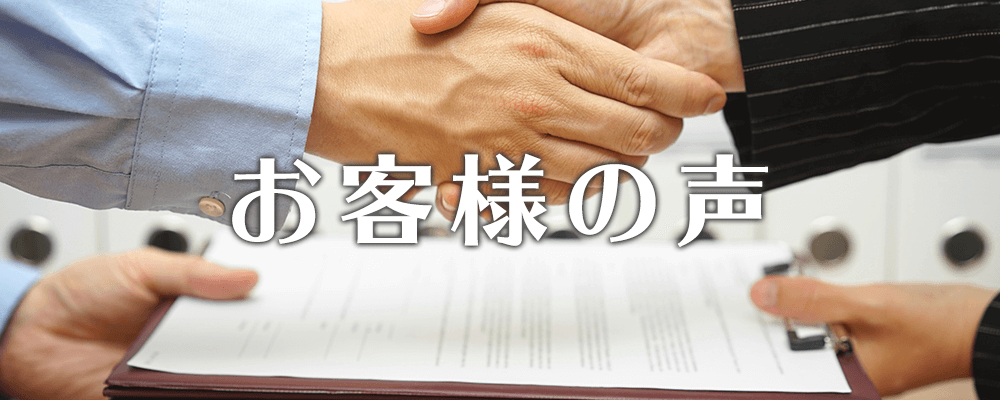今回は、貨物利用運送事業の許認可申請に精通する専門家、阪本浩毅氏にお話を伺いました。阪本氏は行政書士として多くの物流企業の立ち上げや許認可取得をサポートしています。特に近年増加している新しい形態のオフィスと許認可の関係について、詳しく解説していただきました。
Contents
貨物利用運送事業と営業所の関係
── 阪本先生、本日はよろしくお願いします。まず、貨物利用運送事業を始める際に営業所が必要だということですが、最近増えているバーチャルオフィスやレンタルオフィスを使いたいという相談は多いのでしょうか?
阪本:はい、非常に多いですね。固定費を抑えるためにバーチャルオフィスやレンタルオフィス、シェアオフィスを利用したいという方からの相談が急増しています。

── 結論から教えていただけますか?
阪本:結論から申し上げますと、バーチャルオフィスはNG、個室を占有するレンタルオフィスはOK、シェアオフィス(コワーキングスペース)はNGという形になります。この区別は非常に重要で、許認可申請の際に見落としがちなポイントです。
── なるほど。それでは詳しくお聞かせください。
貨物利用運送事業における営業所の要件
── そもそも貨物利用運送事業における「営業所」とは、どのようなものを指すのでしょうか?
阪本:貨物利用運送事業における営業所とは、基本的に荷主からの利用運送の申込を受け付けたり、実際に運送を行う運送事業者を手配したりするなど、利用運送の営業機能を有する拠点のことを指します。単なる住所だけではなく、実際に貨物利用運送事業を行う場所という位置づけが重要です。
── 法律上の定義や要件はあるのでしょうか?
阪本:はい、具体的には審査基準に明記されています。第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業それぞれの処理方針に次のように定められています。
第一種貨物利用運送事業と登録の申請等の処理方針等から抜粋すると、
- 使用権原のある営業所、店舗を有していること
- 営業所等が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと
第二種貨物利用運送事業の許可の申請等の処理方針等も同様の内容となっています。
── 「使用権原」というのは少し難しい言葉ですが、どういう意味なのでしょうか?
阪本:「使用権原」とは法律用語ですが、簡単に言えば、その場所を使用する正当な権利があるということです。具体的には、自社所有であったり、賃貸借契約を結んでいたりして、合法的にその場所を使用する権利を持っているという意味です。例えば、友人のオフィスを無断で使っているような状態では、使用権原があるとは認められません。
── 審査基準を見ても、バーチャルオフィスやレンタルオフィスが使えるかどうかは明確ではなさそうですね。
阪本:おっしゃる通りです。審査基準だけでは判断が難しいため、より根本的な法律である貨物利用運送事業法に立ち返る必要があります。同法には営業所での掲示義務についての規定があり、これが実は重要なポイントになります。
── 掲示義務とはどのようなものですか?
阪本:貨物利用運送事業法の第一種貨物利用運送事業は第9条と第二種貨物利用運送事業は第27条に規定されています。簡単に言えば、事業者である旨や、運送機関の種類、運賃・料金、利用運送約款などの情報を、営業所内の公衆に見やすい場所に掲示しなければならないというものです。
実はこれが非常に重要で、この掲示義務を果たせるかどうかが、各種オフィスを営業所として使えるかの判断基準になります。また、この規定に違反すると、貨物利用運送事業法第68条により50万円以下の過料に処せられるという罰則もあります。
── そうした法的な掲示義務があるのですね。実務上ではどのように掲示することが一般的なのでしょうか?
阪本:実務上は、A4サイズ程度の掲示物を壁に貼り付けたり、専用の掲示板を設置したりします。この掲示は形式的なものではなく、国土交通省や運輸局の監査が入った場合に確認されるので、しっかりと対応する必要があります。
バーチャルオフィスを利用運送の営業所として使えるか
── それでは、バーチャルオフィスについて詳しく教えてください。貨物利用運送事業の営業所としては使えないということですが、その理由は?
阪本:バーチャルオフィスは、実際の物理的なオフィスを借りるのではなく、住所のみを借りる形態のサービスです。主に登記住所として使われることが多いです。具体例を挙げると、東京都中央区の一等地の住所を月額数千円で借りられるようなサービスですね。
問題は、バーチャルオフィスでは貨物利用運送事業者が専有するスペースがないため、先ほど説明した事業実態がなく、法定事項の掲示ができないという点です。掲示スペースがない以上、バーチャルオフィスは貨物利用運送事業の営業所としては認められません。
── 2022年から2023年にかけて何か規制の変更はありましたか?
阪本:法律自体の変更はありませんが、物流業界の拡大に伴い、新規参入企業が増加したことで、審査の目が厳しくなっている印象です。特に東京、大阪などの大都市圏では、バーチャルオフィスによる申請が増えたことで、当局側の調査も徹底してきています。
レンタルオフィスを利用運送の営業所として使えるか
── 次に、レンタルオフィスは使えるということですが、どのような条件が必要でしょうか?
阪本:レンタルオフィスは、自社が専有使用できる個室が提供されているオフィスを指します。例えば、ビジネスセンターなどで提供されている個室タイプのオフィスですね。鍵のかかる個室があり、その中は借主が自由に使えるタイプです。
このような個室であれば、壁に貨物利用運送事業法で求められる掲示物を掲示することが可能です。したがって、個室タイプのレンタルオフィスは貨物利用運送事業の営業所として適していると言えます。
── 最近はさまざまなタイプのレンタルオフィスがありますが、何か注意点はありますか?
阪本:重要な注意点として、契約形態と実態が一致しているかどうかを確認する必要があります。名称が「レンタルオフィス」となっていても、実際には個室がなかったり、契約書上で掲示物の設置が禁止されていたりするケースがあります。
具体的な事例では、「レンタルオフィス」と謳っていても、実際には月の半分しか使えない、あるいは予約制で常時使えないタイプのオフィスでは、営業所として認められなかったケースがあります。契約内容をしっかり確認することが重要です。
── 契約書には何か特別な条項が必要ですか?
阪本:特別な条項というわけではありませんが、少なくとも以下のポイントが明記されていることが望ましいです:
- 専有使用できる個室であること
- 契約者が自由に使用できること(時間制限がないこと)
- 壁面等への掲示が可能であること(または禁止されていないこと)
- 契約期間が十分に長いこと(短期間の契約だと営業実態を疑われる可能性があります)
── 最近、柔軟な働き方が進む中で、レンタルオフィス業界にも変化はありますか?
阪本:はい、大きな変化が見られます。最近では貨物利用運送事業などの許認可事業向けに特化したレンタルオフィスも登場してきています。これらは法定掲示物の設置スペースを明確に確保し、契約書にもその旨を記載しているため、申請がスムーズに進みやすいという特徴があります。業界の需要に合わせたサービスが出てきているのは良い傾向だと思います。
シェアオフィス(コワーキングスペース)を利用運送の営業所として使えるか
── 最後に、シェアオフィスやコワーキングスペースについてはいかがでしょうか?
阪本:シェアオフィスは、共有のフリーアドレスデスクで執務をすることができるオフィス形態です。レンタルオフィスとの最大の違いは、自社が専有する個室があるかないかという点です。最近ではコワーキングスペースという名称も広く使われています。
シェアオフィスでは、自社専有のスペースはなく、デスクやテーブルは会員同士で共有する場所になります。そのため、壁に掲示物を貼ることは通常許可されません。利用規約にも、壁への掲示を禁止する条項が含まれていることがほとんどです。
このような理由から、一般的なシェアオフィスやコワーキングスペースは、貨物利用運送事業の営業所としては適さないと判断されます。
── 最近増えている「バーチャルオフィス+コワーキングスペース利用権」のようなハイブリッドサービスはどうでしょうか?
阪本:これは非常に良い質問です。最近、住所貸しと共有オフィス利用をセットにしたサービスが増えていますね。しかし、これも基本的には「使用専有権のある個室」がなければ、貨物利用運送事業の営業所としては認められません。コワーキングスペースを時々使える権利があっても、掲示義務を果たせる自社専有スペースがない限り、営業所としては不適格と判断されるでしょう。

利用運送の営業所まとめ
── ここまでのお話をまとめていただけますか?
阪本:ここまでの内容をまとめますと、レンタルオフィス運営会社と正式な賃貸借契約を締結し、使用権原を有していることが前提となりますが、個室を占有するタイプのレンタルオフィスであれば、貨物利用運送事業の営業所として許認可を取得することが可能です。
一方で、バーチャルオフィスやシェアオフィスは、基本的には営業所として認められません。これは法定掲示物を設置するスペースがないためです。
── すべてのレンタルオフィスが適しているわけではないのですね?
阪本:その通りです。すべてのレンタルオフィスが貨物利用運送事業の営業所として適しているとは断言できません。私たち行政書士が申請のお手伝いをする際には、賃貸借契約書の内容を細かく確認したり、場合によっては現地調査を行ったりして、営業所としての適合性を最終的に判断します。
近年は当局の審査も厳格化していますので、申請前の事前チェックが非常に重要になっています。不適切な営業所で申請して却下されると、再申請までに時間とコストがかかりますので、慎重に進めることをお勧めします。
── 最後に、これから貨物利用運送事業を始めようとしている方へのアドバイスをお願いします。
阪本:貨物利用運送事業は、物流のプラットフォーマーとして今後も成長が期待される分野です。コスト削減の観点から新しいオフィス形態を検討されるのは理解できますが、許認可取得の観点からは、個室型レンタルオフィスを選ぶことをお勧めします。
また、近年はテレワークや物流DXが普及してオフィスに出社しての業務という概念が薄れていますが、貨物利用運送事業の許認可に関しては、実態を伴った営業所設置が重要です。
最後に、迷った場合は専門家に相談することをお勧めします。一度却下されると再申請に時間がかかりますので、最初から正しく申請することが結果的にコスト削減につながります。
── 本日は貴重なお話をありがとうございました。
阪本:ありがとうございました。皆様のビジネスの成功をお祈りしています。
電話での問い合わせ
お電話でのお問い合わせは、平日の9:00~18:00の間、受け付けております。
お悩みについてすぐにお答えできるので、お電話でのお問い合わせをご利用いただく方も多いです。
- 都庁前オフィス(東京都新宿区):03-5843-8541
- 武蔵小杉オフィス(神奈川県川崎市):044-322-0848
お電話の際には「利用運送業のホームページを見た」とお伝えください。
なお、コンプライアンス上の理由で、匿名・電話番号非通知でのお問い合わせには対応しておりません。お問い合わせの際には会社名・お名前・ご連絡先などを伺っておりますのであらかじめご了承ください。
担当者不在時には伝言を残していただければ遅くとも翌営業日までに折り返し担当者よりお電話いたします。
※We apologize, but we are able to assist and operate in Japanese only.
メールでのお問い合わせ
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。必ず2営業日以内に返信しております。返信が届かない場合には、
- ご入力いただいたメールアドレスが間違っている
- 返信メールが迷惑メールフォルダ等に振り分けられている
- 返信メールが受信できない設定になっている
といった原因が考えられます。メールが届かない場合には、上記をご確認いただいたうえ、お手数ですが再度メールフォームよりお問い合わせください。
※We apologize, but we are able to assist and operate in Japanese only.