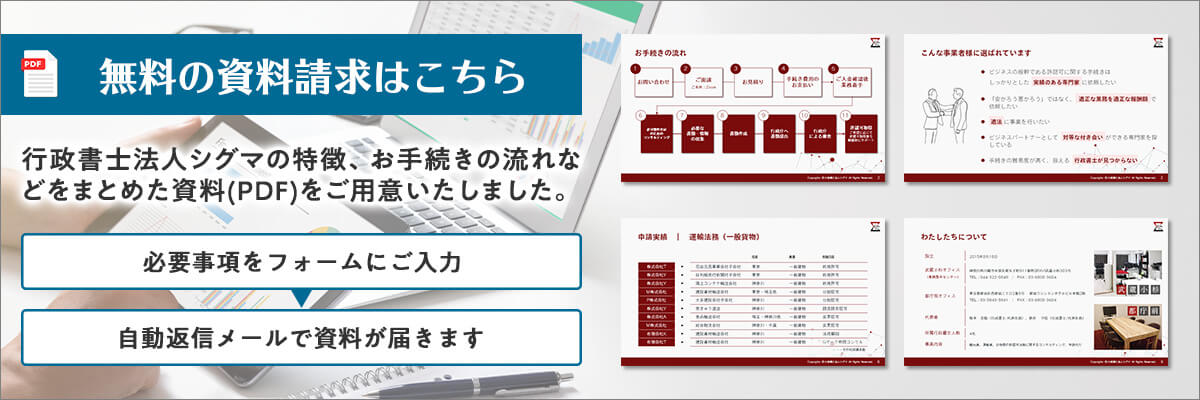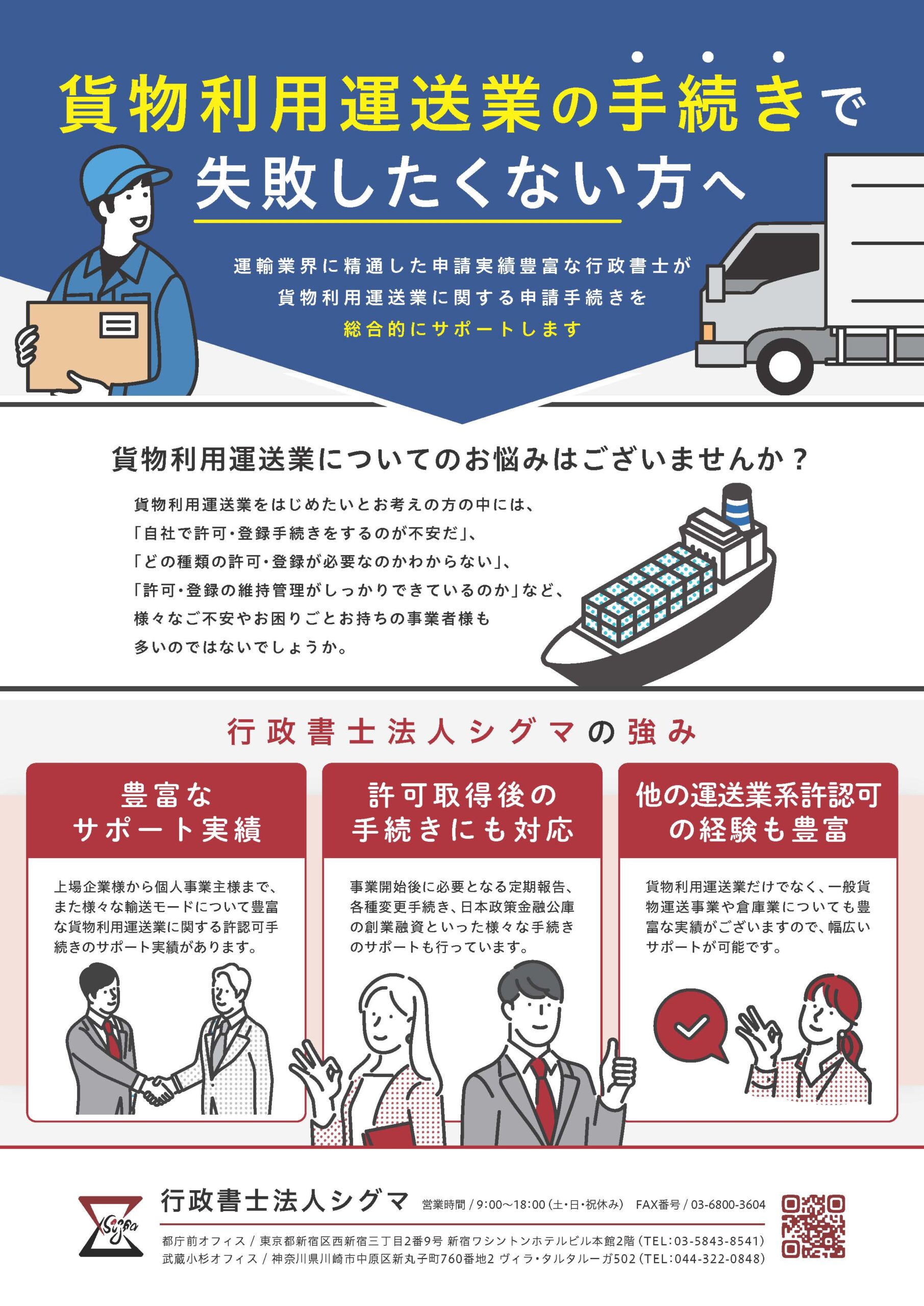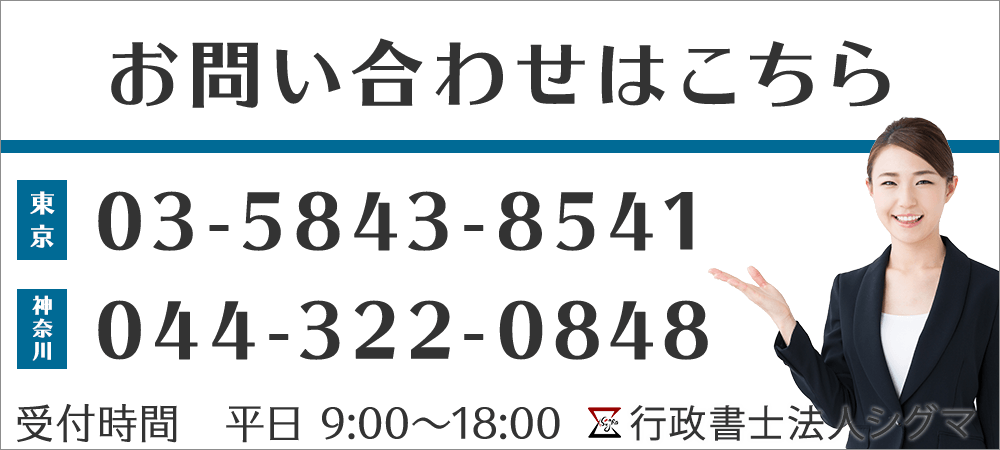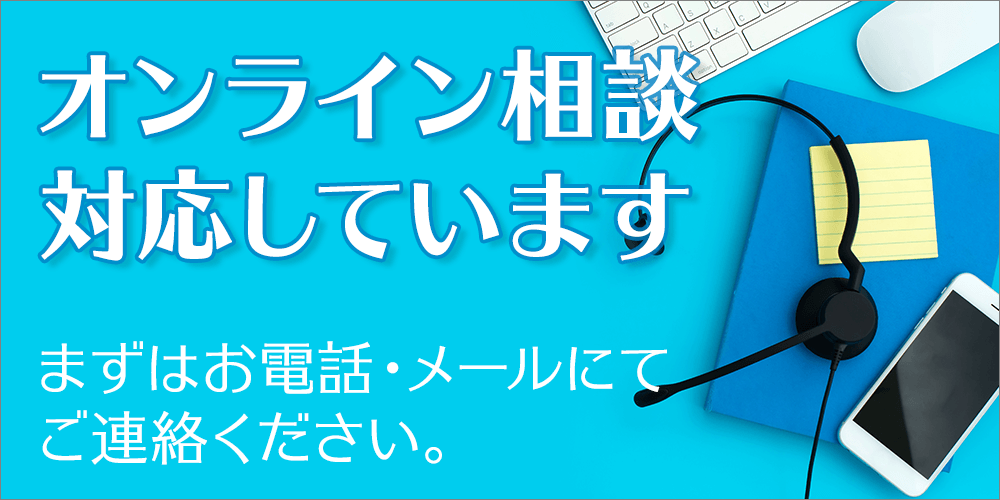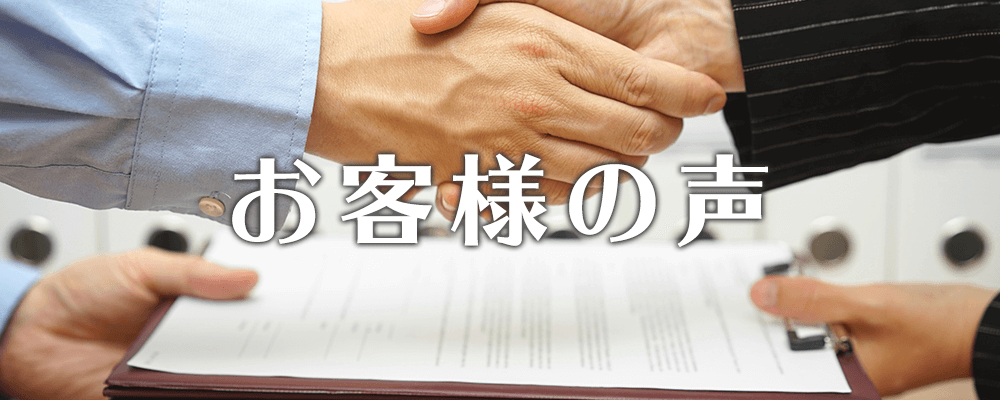運送業界のレギュレーション・法規制を専門としている行政書士阪本浩毅氏をお招きし、貨物利用運送事業の種別について詳しくお話を伺いました。阪本氏は物流企業への支援実績多数。特に許認可申請の分野では業界随一の知識を有する専門家として知られています。初めて事業参入を検討している方から、種別変更を検討中の事業者まで、誰もが悩む「第一種と第二種の違い」について明快に解説していただきました。
Contents
貨物利用運送事業における種別の基本的な違い
── 阪本さん、本日はお時間をいただきありがとうございます。まずは貨物利用運送事業の種別について基本的なところから教えていただけますか?
阪本:こちらこそお時間いただきありがとうございます。貨物利用運送事業には第一種と第二種という2つの種類があるのですが、実際にこの違いがとても分かりにくいんですね。多くの事業者様から「自分たちがやりたい事業が第一種なのか第二種なのか判断できない」というご相談をいただきます。

── 確かに一般の方には分かりにくい区分かもしれませんね。
阪本:そうなんです。今日のインタビューでは、細かい手続き上の違いではなく、どのような貨物利用運送事業が第一種に該当するのか、あるいは第二種に該当するのかについて、できるだけ分かりやすく説明していきたいと思います。実務に直結する内容ですので、これから参入される方々の参考になればと思います。
第一種と第二種の違いを表で整理
── まずは両者の違いをざっくり教えていただけますか?
阪本:はい、まずは第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業の基本的な違いを表にまとめてみましょう。
| 項目 | 第一種貨物利用運送事業 | 第二種貨物利用運送事業 |
|---|---|---|
| 荷主に対しての運送責任 | 貨物利用運送事業者が負う | 貨物利用運送事業者が負う |
| 事業形態 | 第二種以外のすべて | トラックで集荷→幹線輸送(海運・航空・鉄道)→トラックで配達の複合一貫輸送 |
| 許認可制度 | 登録制 | 許可制 |
| 許認可手続きの難易度 | 貨物自動車は比較的難易度が低いが、海運・航空・鉄道は大変なことが多い | (第一種に比べて)難易度が高く、大変なことが多い |
── この表を見ると、運送責任は両方とも事業者が負うのですね。大きな違いは事業形態と許認可制度ということでしょうか?
阪本:おっしゃる通りです。運送責任については両方とも事業者が負いますが、第二種は複合一貫輸送という特定の形態に限定されます。一方で第一種はそれ以外のすべての形態となります。また、手続き上は第一種が登録制、第二種が許可制という大きな違いがあります。
第二種以外はすべて第一種
── なるほど。では貨物利用運送事業を始めようとする場合、まず考えるべきは「第二種に該当するかどうか」ということなのでしょうか?
阪本:その通りです。貨物利用運送事業のなかで二種に該当しないものはすべて一種になるというのが大原則です。つまり第二種がどんな形態なのかわかれば、それにあてはまらないものは自動的に第一種だと判断できます。
── その前に、そもそも「貨物利用運送事業」とは何かについても確認しておきたいのですが。
阪本:大事なポイントですね。貨物利用運送事業とは、「他人の需要に応じ、有償で」「運送事業者の行う運送(実運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送」と法律で定義されています。少し分かりにくい表現ですので言い換えると、「お客さん(荷主)の依頼を受けて、有償で、自社ではない運送事業者に荷物を運んでもらう事業」ということになります。
── 自社で実際に運ぶのではなく、運送を行う事業者を利用するわけですね。
阪本:そうです。また、業界では「利用の利用」と呼ばれる形態もあります。これは、貨物利用運送事業者が実運送事業者ではなく、別の貨物利用運送事業者を使った運送事業のことですが、これも貨物利用運送事業に該当します。
── 「実運送事業者」というのは具体的にはどういった事業者を指すのでしょうか?
阪本:実運送事業者というのは、自らの運送機関、つまり自動車、船舶、鉄道、飛行機などを使って実際に貨物を運ぶ事業者のことです。例えば、トラック運送業者、船会社、鉄道会社、航空会社などが該当します。最近では自社の車両を所有せず、下請けの運送業者を使うケースもありますが、法的には実運送の責任を負っている事業者が実運送事業者となります。
手続き上の違い
── 手続き面での違いについても詳しく教えていただけますか?
阪本:はい。先ほども少し触れましたが、第一種貨物利用運送事業は登録制で、第二種貨物利用運送事業は許可制という違いがあります。許認可取得手続きを進める上では、第二種には第一種では提出を求められていない集配事業計画を作成しなければならないという違いもあります。
── 登録制と許可制では難易度に違いがあるのでしょうか?
阪本:一般的に登録は許可に比べると難易度が低く感じられる方も多いのですが、実態としては国土交通省の許可処分の種類が違うだけで、登録制であっても申請書類を提出すれば誰でも事業ができるわけではありません。登録であっても、許可と同様の細かい条件があり、申請書類提出後に審査が行われています。
── 最近は審査も厳しくなっているのでしょうか?
阪本:はい、特に物流業界の安全性や信頼性に対する要求が高まっていることから、ここ数年で審査は厳格化傾向にあります。また注意すべき点として、登録であっても、許可であっても、国土交通省や運輸局での審査期間が必要になります。「登録だから申請書類を提出さえすればすぐに営業できる」というわけではないのです。
── 具体的な審査期間はどれくらいかかるものなのでしょうか?
阪本:申請の内容や地域によって変わりますが、第一種の場合は3ヶ月、第二種の場合は少なくとも4ヶ月はかかると考えておいた方が良いでしょう。最近では審査を行う担当官の人手不足の影響もあり、審査に時間がかかるケースが増えています。事業計画を立てる際には、この審査期間も考慮に入れることが大切です。
── では、一言でまとめると?
阪本:ここでは「第二種のほうが手続きが大変」くらいに理解していただければ問題ないかと思います。具体的なケースごとに細かい違いはありますが、一般的な傾向としてはそういうことです。
第二種になるかどうかのポイントは2つ
── 第二種貨物利用運送事業に該当するかどうかのポイントを整理していただけますか?
阪本:非常にざっくり言うと、第二種貨物利用運送事業になるかのポイントは以下の2つです。
- トラックでの集荷→幹線輸送(海運・航空・鉄道)→トラックでの配達までの複合一貫輸送を提供すること
- 海運・航空・鉄道を使った幹線輸送業務に加えて、トラックを使った集荷と配達についても、荷主に対する運送責任を貨物利用運送事業者が負っていること
── つまり、第二種貨物利用運送事業者は一貫した輸送の責任を負うということですね。
阪本:その通りです。第二種貨物利用運送事業者は、貨物の集荷・幹線輸送・配達までのドア・ツー・ドアの複合一貫輸送の担い手ということになります。幹線輸送は、荷主のニーズにあわせて海運・航空・鉄道のいずれかを利用することになりますが、海運は外航と内航、航空は国内と海外など、輸送モードにあわせてそれぞれ分けられています。
── 業界の最近の傾向としては何か変化はありますか?
阪本:最近では越境ECの拡大により、国際複合一貫輸送のニーズが高まっています。特に航空貨物と海上貨物を組み合わせる「シーアンドエア」や、鉄道と航空を組み合わせる「レールアンドエア」といった複合輸送の形態も増えています。また環境負荷低減の観点から、トラック輸送から鉄道や内航海運へのモーダルシフトも進んでおり、第二種貨物利用運送事業の重要性は今後ますます高まるでしょう。
第二種貨物利用運送事業のイメージ
── 第二種貨物利用運送事業の具体的なイメージを教えていただけますか?
阪本:例えば、荷主の倉庫からトラックで集荷して港に届けて、そこから船舶を使って国内もしくは海外の他の港に運び、着港から配達先の倉庫までトラックで配達するというように、荷主から配達先までのドア・ツー・ドアでの輸送を、実運送事業者の輸送手段を利用して、一貫して提供するのが第二種貨物利用運送事業です。
── キーワードは何になりますか?
阪本:大事なのは、「ドア・ツー・ドア」と「複合」という2つのキーワードです。「ドア・ツー・ドア」というのは「集荷から配達まで」ということで、「集荷から配達まで」の輸送を一貫して提供するのが第二種の特徴です。また、「複合」というのは、[集荷と配達を行うトラック運送]と[幹線輸送(海運・航空・鉄道)]を組み合わせたものという意味です。
── 具体例を挙げるとすれば?
阪本:具体例としては、日本の製造業者の工場から製品をトラックで集荷し、成田空港から航空機でアメリカのシカゴ空港まで輸送し、そこからトラックで現地の倉庫まで配達するというケースが第二種に該当します。あるいは、愛知県の自動車部品メーカーから部品をトラックで集荷し、名古屋港から内航船で九州の港まで運び、そこから自動車工場までトラックで配達するというケースも第二種です。
── トラックだけで完結する場合はどうなりますか?
阪本:ですので、荷主からトラックで集荷して、そのままトラックで配達するという場合は、ドア・ツー・ドアで貨物を運んでいますが、幹線輸送で海運・航空・鉄道を使っておらず「複合」と言えないため、第一種貨物利用運送事業(貨物自動車)に該当します。この点は多くの方が混同されやすいポイントですので、特に注意が必要です。
── 実務上の落とし穴などはありますか?
阪本:一つよく見落とされがちな点として、複合一貫輸送を行う場合でも、そのすべての区間で運送責任を負わなければ第二種には該当しないという点があります。例えば、日本からアメリカまでの輸出で、日本国内の集荷と日本からアメリカまでの輸送までは責任を負うが、アメリカ国内の配達は現地のパートナー会社が別途契約するような場合は、第二種ではなく第一種になります。こうした細かい違いが実務上の判断を難しくしています。
貨物軽自動車運送事業者が集配をするケース
── 貨物の集配を軽貨物車やバイク便が行う場合はどうなるのでしょうか?
阪本:少し細かい話になりますが、貨物の集配を軽貨物車やバイク便などといった貨物軽自動車運送事業者が行う場合は第二種にはあたりませんので注意が必要です。
── これは意外ですね。具体的にはどういうケースになりますか?
阪本:例えば、日本国内での貨物の輸送に幹線輸送には内航船や国内航空便、鉄道を利用し、集荷・配達は小回りが利くという理由で黒ナンバーの貨物軽自動車を利用するケースを考えてみましょう。この場合、荷主に対する運送責任はドア・ツー・ドアで負っています。しかし、集荷・配達には緑ナンバーのトラックを運行している一般貨物自動車運送事業者を利用していないため、第二種貨物利用運送事業には該当しないのです。
── そのような場合は、どのような手続きが必要になるのでしょうか?
阪本:この場合は、利用する幹線輸送(海運・航空・鉄道)に対応した第一種貨物利用運送事業の登録をすることになります。つまり、内航海運であれば第一種貨物利用運送事業(内航海運)、国内航空であれば第一種貨物利用運送事業(航空)、鉄道であれば第一種貨物利用運送事業(鉄道)の登録が必要になります。
── これは見落としがちなポイントですね。実務上はよくあるケースなのでしょうか?
阪本:実はかなり多いです。特に都市部での集配では、大型トラックが入れない場所も多く、軽貨物車やバイク便を使うケースは少なくありません。また最近ではラストワンマイルの配送が重要視される中で、軽貨物車の需要は増加傾向にあります。しかしこの場合は第二種には該当しないという点は、多くの事業者が見落としがちなポイントです。
輸入や三国間での国際複合一貫輸送を行うケース
── 国際輸送の場合はどうなりますか?特に輸入や三国間輸送の場合について教えていただけますか?
阪本:幹線輸送に外航・国際航空を使用して国際複合一貫輸送を行う場合、日本から輸出する運送業務のみが貨物利用運送事業法の適用を受けます。したがって、海外からの輸入や三国間での国際複合一貫輸送を行う場合は貨物利用運送事業法の適用を受けないため、第二種貨物利用運送事業には該当いたしません。
── つまり、輸入や三国間輸送では第二種の許可は不要ということでしょうか?
阪本:はい、その通りです。つまり第二種貨物利用運送事業の許可を取得せずに事業展開ができるのです。この点は国際輸送を手がける事業者にとっては重要なポイントです。輸出のみが貨物利用運送事業法の対象となるという点を押さえておく必要があります。
── 最近の国際物流の変化についても教えていただけますか?
阪本:近年ではBCPの観点から、輸送ルートの多様化が進んでいます。コロナ禍以降、特に海上輸送の混乱もあり、「シーアンドエア」や「クロスボーダー鉄道」など、複数の輸送モードを組み合わせた国際輸送が注目されています。また環境負荷低減の動きから、長距離輸送における海上・鉄道の活用も増えています。しかし法制度が国際的な物流の動きに追いついていない面もあり、どの許認可が必要なのか、事業者も行政も判断に迷うケースが増えています。
外航船舶を利用した輸出貨物を取扱う貨物利用運送事業を行うケース
── 次に、外航船舶を利用した輸出貨物の具体的なケースについて伺いたいと思います。
阪本:例えば、ある会社が日本国内では一般貨物自動車運送事業者のトラックを利用して発荷主の倉庫より集荷して、コンテナ船が出向する横浜港まで運送を行い、横浜港からシンガポール港まで、海運会社のコンテナ船を使って海上輸送を行うケースを考えてみましょう。
── この場合、第一種と第二種のどちらになるのでしょうか?
阪本:このようなケースで、シンガポール港での受取・シンガポール港から着荷主の倉庫までの配達業務を着荷主側で手配するような場合には、当該会社はその部分の運送責任を負わないため、発荷主の倉庫から横浜港を経由してシンガポール港までの集貨と海上輸送にあたる第一種貨物利用運送事業の貨物自動車と外航海運の2つの輸送モードの登録を取得することになります。
── 実際にそのようなケースはあるのでしょうか?
阪本:これは実際にあったケースです。当初は第二種貨物利用運送事業の許可取得を検討されていましたが、運送責任の所在について整理を行ったところ、第二種ではなく、第一種で良かったことが判明しました。
── 逆のケースもあるのでしょうか?
阪本:はい、その逆に、第一種貨物利用運送事業の貨物自動車と外航海運の2つの輸送モードの登録を取得されていた事業者様が、実際には荷主企業に対してドア・ツー・ドアでの運送責任を負っていることが判明し、第二種貨物利用運送事業(外航海運)の許可を取得する必要が判明したケースもありました。
── 実務上の注意点としては?
阪本:実務上の注意点としては、契約書や見積書などの文書から、実際に誰がどこまでの運送責任を負っているのかを明確にすることが重要です。特に国際輸送の場合、通関や保険、荷受け代行など、様々なサービスが絡み合うため、実態がどうなっているのかを整理する必要があります。また、最近では「サプライチェーン可視化」のニーズから、輸送の全行程を一社が担うケースが増えており、第二種への移行を検討する企業も増えています。

第一種貨物利用運送事業
── 続いて、第一種貨物利用運送事業について詳しく教えていただけますか?
阪本:前述のとおり、貨物自動車、海運、航空、鉄道での運送を利用した第二種にならない貨物利用運送事業が第一種ということになります。簡単に言えば、第二種の条件である「ドア・ツー・ドアの複合一貫輸送」に当てはまらないものはすべて第一種ということです。
第一種貨物利用運送事業のイメージ
── 第一種貨物利用運送事業の具体的なイメージを教えていただけますか?
阪本:典型的な例では、さきほども挙げたような「荷主の依頼でトラックで集荷して、そのままトラックで配達する」という一般貨物自動車運送事業者を利用して運送するというケースが第一種にあたります。また他には、幹線輸送(海運・航空・鉄道)のみを行うケースが第一種の代表的な例です。
── 一番多いのはどのようなケースでしょうか?
阪本:貨物自動車以外では、日本国内の発港から海外の着港まで、コンテナ船を利用して海上輸送する外航海運が第一種貨物利用運送事業では多いケースでしょう。航空や鉄道の幹線輸送のみというケースは少ないとは思いますが、海運のうち外航の分野では多い印象を受けています。
── 最近の第一種貨物利用運送事業の傾向としては何かありますか?
阪本:最近の傾向としては、特に貨物自動車の分野で、デジタルプラットフォームを活用した貨物マッチングサービスが増加している点が挙げられます。これは荷主と運送事業者をオンラインでマッチングするサービスで、典型的な第一種貨物利用運送事業です。また、倉庫業と組み合わせたサービスも増えており、保管から配送までをワンストップで提供する事業者も増えています。こうした新しいビジネスモデルでは、どの許認可が必要なのか判断が難しいケースも増えていますので、専門家への相談をお勧めします。
まとめ
── 最後に、全体をまとめていただけますか?
阪本:このインタビューでは、第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業の違いについて説明させていただきました。簡単にまとめると、第二種は「トラックによる集荷→海運・航空・鉄道による幹線輸送→トラックによる配達」という複合一貫輸送を行い、全ての区間で運送責任を負う場合に該当します。それ以外のケースはすべて第一種になります。
── これまでのお話を聞いても、まだ複雑で分かりにくいと感じる方もいらっしゃるかもしれませんね。
阪本:おっしゃる通りです。ここまで読まれてみても、「やっぱり複雑で、なかなかわかりにくい」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。物流業界の実務経験があっても、許認可手続きの場面では判断に迷うケースも多いです。
── そういった場合はどうすればよいでしょうか?
阪本:専門家への相談をお勧めします。私どものような行政書士に貨物利用運送事業の登録・許可の手続きをご依頼いただいた場合には、書類の作成や提出代行に留まらず、どちらの種別にするべきかも含めて十分なコンサルティングを行わせていただいております。
── 最後に、これから貨物利用運送事業を始める方へのアドバイスをお願いします。
阪本:物流業界は今、大きな変革期にあります。デジタル化やグリーン物流の推進、人手不足への対応など、様々な課題と機会が存在します。貨物利用運送事業者として成功するためには、単なる運送の仲介だけでなく、荷主に対して付加価値を提供することが重要です。
また、許認可についても正確な理解が必須ですので、ご検討中の貨物利用運送事業が第一種、第二種のどちらになるのかわからないという事業者様は、事業計画の早い段階でぜひ一度専門家にご相談ください。適切な許認可を取得し、コンプライアンスを守りながら事業を展開することが長期的な成功につながると考えています。
電話での問い合わせ
お電話でのお問い合わせは、平日の9:00~18:00の間、受け付けております。
お悩みについてすぐにお答えできるので、お電話でのお問い合わせをご利用いただく方も多いです。
- 都庁前オフィス(東京都新宿区):03-5843-8541
- 武蔵小杉オフィス(神奈川県川崎市):044-322-0848
お電話の際には「利用運送業のホームページを見た」とお伝えください。
なお、コンプライアンス上の理由で、匿名・電話番号非通知でのお問い合わせには対応しておりません。お問い合わせの際には会社名・お名前・ご連絡先などを伺っておりますのであらかじめご了承ください。
担当者不在時には伝言を残していただければ遅くとも翌営業日までに折り返し担当者よりお電話いたします。
※We apologize, but we are able to assist and operate in Japanese only.
メールでのお問い合わせ
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。必ず2営業日以内に返信しております。返信が届かない場合には、
- ご入力いただいたメールアドレスが間違っている
- 返信メールが迷惑メールフォルダ等に振り分けられている
- 返信メールが受信できない設定になっている
といった原因が考えられます。メールが届かない場合には、上記をご確認いただいたうえ、お手数ですが再度メールフォームよりお問い合わせください。
※We apologize, but we are able to assist and operate in Japanese only.