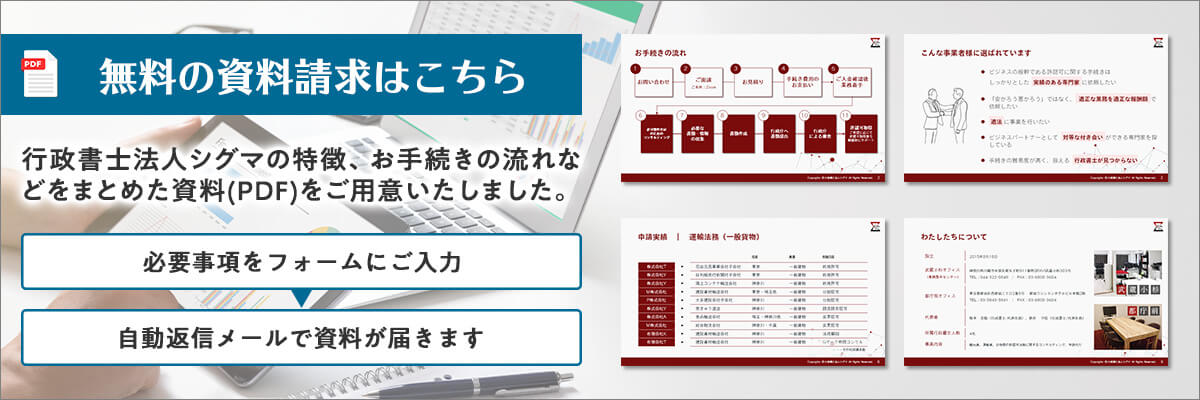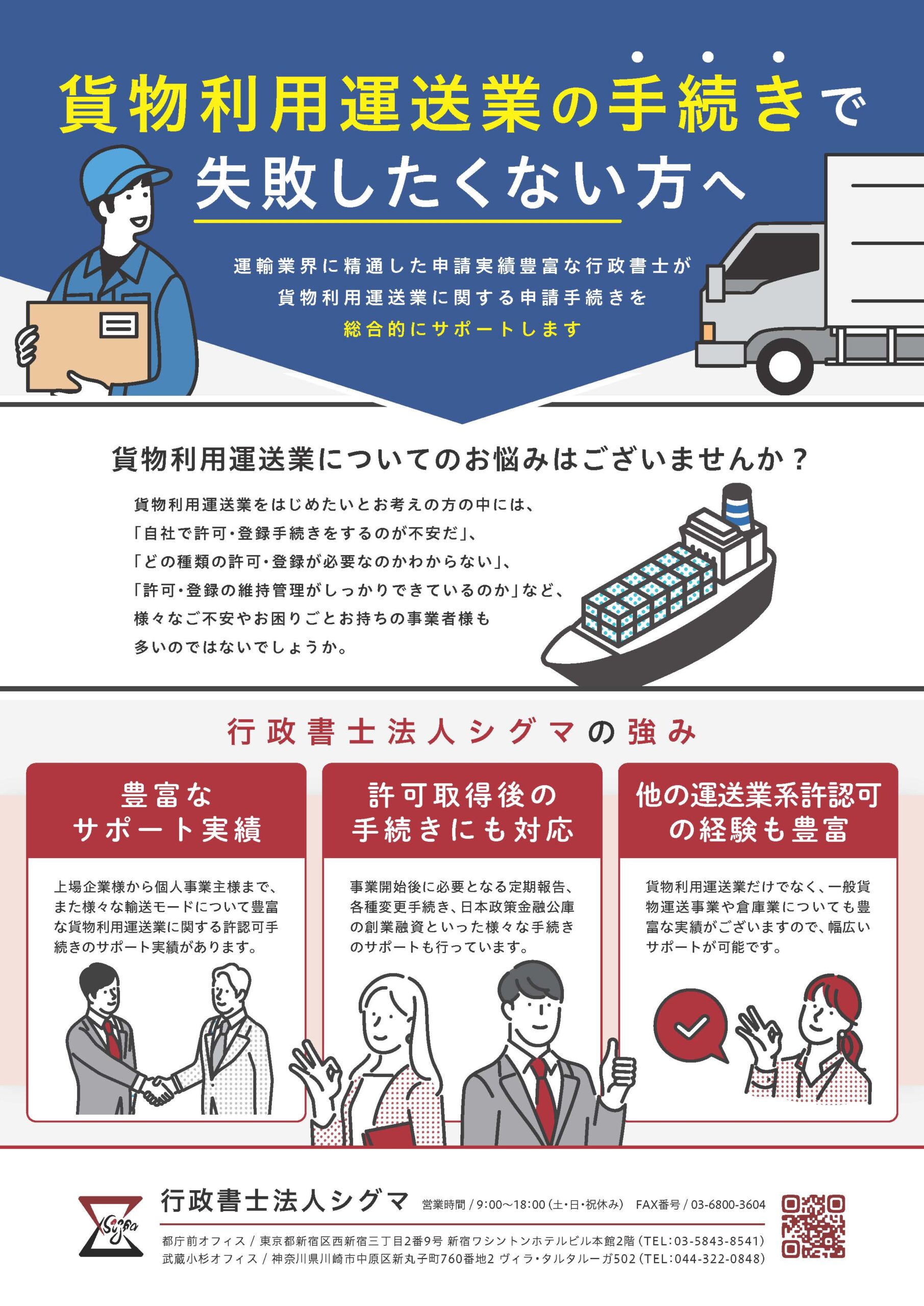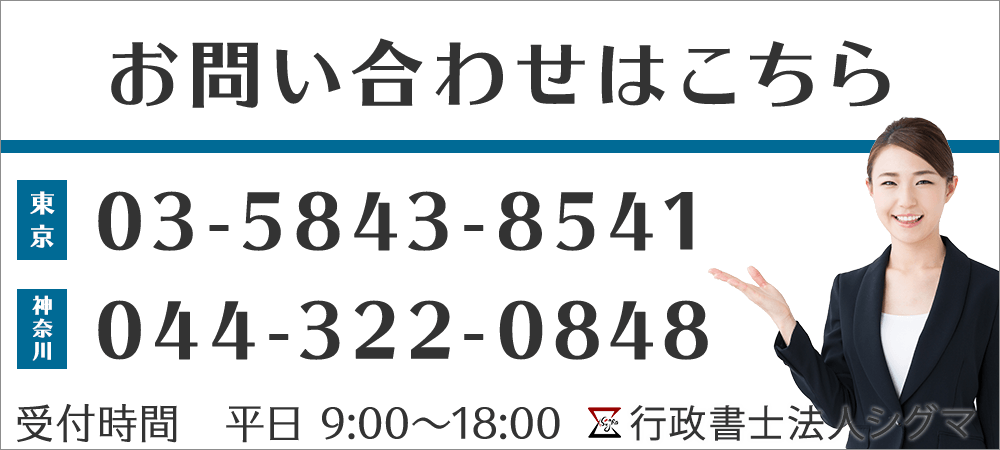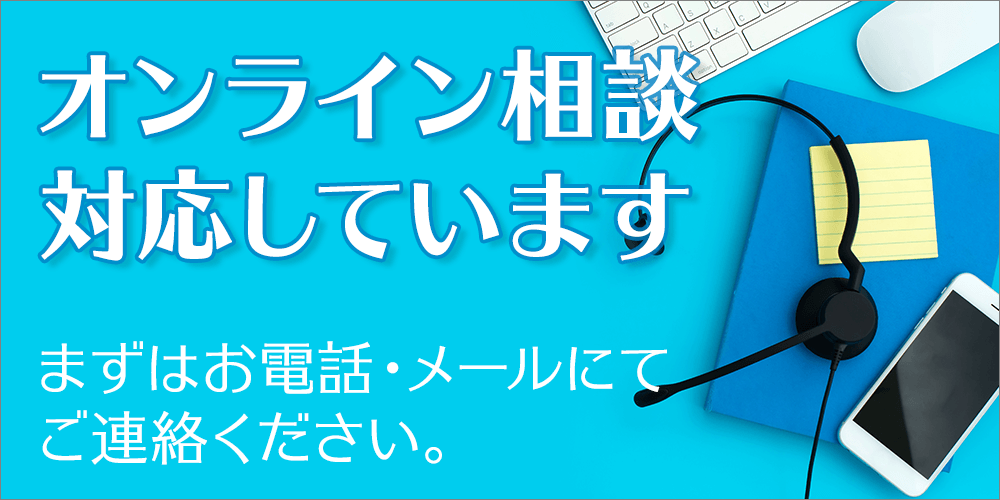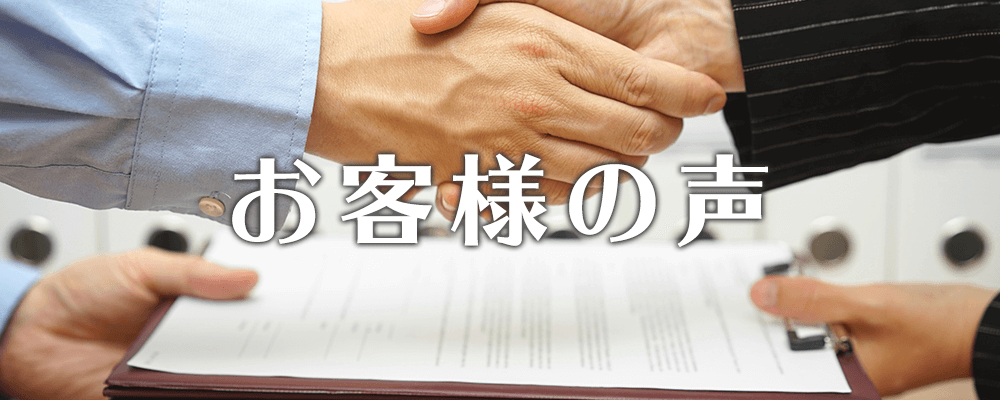今回は、運輸業に関する許認可法務分野で長年にわたり第一線で活躍し、数多くの企業の貨物利用運送事業の許認可申請を支援している行政書士の阪本浩毅氏にインタビューを行いました。阪本氏は物流関連の許認可申請のスペシャリストとして知られ、特に第二種貨物利用運送事業許可の取得支援において豊富な実績を持つ行政書士です。近年の物流業界の法規制の動向にも精通しており、実務に即した貴重なアドバイスをいただきました。
貨物利用運送事業とは何か
──まず基本的なところから教えていただきたいのですが、貨物利用運送事業とはどのようなものなのでしょうか?
阪本:貨物利用運送事業とは、荷主企業から依頼を受けて、自社で輸送手段を持たず、有償で他の運送業者を利用して貨物を運送する事業のことです。簡単に言えば、運送の仲介業のような形態ですね。ただし、単なる仲介とは異なり、荷主に対して運送責任を負うという点が貨物取次事業との違いです。

──第一種と第二種に分かれているとのことですが、その違いは何でしょうか?
阪本:第一種はトラック・船舶・航空・鉄道のいずれか一つの輸送モードを利用して運送を行う事業です。一方、第二種は、海運・鉄道・航空などによる幹線輸送と、その前後のトラックによる集荷・配達を一貫して行う「ドア・ツー・ドア」の輸送を担うのが第二種です。例えば、東京の荷主から大阪の顧客までの輸送で、トラックで集荷して発駅で積み替えて鉄道で運び、着駅においては鉄道からトラックに積み替えてトラックで配達するといった一連の流れを一括して請け負います。
──今回は第二種の許可要件について詳しく解説いただけるとのことですね。
阪本:はい。近年、EC市場の拡大やサプライチェーンの複雑化に伴い、第二種貨物利用運送事業への参入を検討される企業が増えていますが、許可要件が第一種より厳しいため、申請準備段階でつまずくケースも少なくありません。その点をしっかり解説していきたいと思います。
第二種貨物利用運送事業許可の要件
──第二種貨物利用運送事業の許可要件には、どのようなものがあるのでしょうか?
阪本:許可要件は大きく分けて3つあります。「事業計画の適切性」「事業の遂行能力」「集配事業計画の適切性」です。第一種に比べると要件が厳しくなっているのは、先ほど申し上げたように、船舶・航空・鉄道の幹線輸送の前後にトラックでの集配があるため、運送形態が複雑になっているからです。
──それぞれの要件について、順番に詳しく教えていただけますか?
阪本:もちろんです。まずは事業計画の適切性から見ていきましょう。
事業計画の適切性
──事業計画の適切性とは具体的にどのようなことを指すのでしょうか?
阪本:事業計画の適切性は「事業の円滑な遂行」「事業遂行に必要な施設」「貨物の受取を他の者に委託して行う場合」の3つの要素から成り立っています。
まず「事業の円滑な遂行」については、利用する運送事業者と適切な運送委託契約が結ばれているかどうかが最も重要です。審査には、原則として、運送委託契約書の写しが必要になります。
──実運送事業者との契約方法には何か特別なルールがあるのでしょうか?
阪本:契約方法としては主に2つのパターンがあります。1つ目は幹線輸送を担う運送事業者(海運・鉄道・航空など)と、集荷・配達を行うトラック運送事業者の両方と直接契約を結ぶ方法です。例えば、東京-大阪間の輸送であれば、JR貨物との契約と東京・大阪それぞれのトラック運送事業者との契約が必要になります。
2つ目は「利用の利用」と呼ばれる方法で、既に同じ種類の第二種貨物利用運送事業許可を持つ事業者と契約する方法です。この場合、自社が取得したい許可と同種の許可を持つ事業者と契約する必要があります。さきほど事例としてお話した鉄道の場合は、「利用の利用」が多い印象があります。
──「利用の利用」というのは少し複雑ですね。何か注意点はありますか?
阪本:非常に重要な注意点があります。「利用の利用」の場合、委託先も自社が取得したい許可と同じ種類の第二種貨物利用運送事業許可を持っている必要があります。例えば、第二種外航海運貨物利用運送事業許可を取得したい場合、委託先も同じ許可、つまり第二種外航貨物利用運送事業許可を持っていなければなりません。第一種外航海運貨物利用運送事業の登録だけでは「利用の利用」は成立しません。
実際に私が経験した事例では、契約相手が「うちは第二種を持っている」と言っていたのに、いざ契約書を作成する段階になって実は第一種しか持っていなかったということがありました。これでは申請が通りません。必ず委託先の許可書や認可書の写しを確認することをお勧めします。
──次に「事業遂行に必要な施設」についてはどうでしょうか?
阪本:こちらは基本的に第一種と同様で、使用権限のある営業所(事務所や店舗)が必要です。自己所有でも賃貸でも構いませんが、確実な使用権限があることが重要です。また、その営業所が都市計画法などの関係法令に違反していないことも求められます。例えば、市街化調整区域に無許可で建てられた建物や、農地転用許可を得ていない農地上の建物などでは認められません。
それから、貨物を保管する施設が必要な事業形態の場合は、保管施設についても同様のルールが適用されます。ただし、保管を運送会社に委託する形態であれば「保管施設なし」で申請することになります。保管施設の有無自体は許可要件ではないので、実態に合わせた申請をすれば問題ないでしょう。
──貨物の受取を外部委託する場合の要件はどうなっていますか?
阪本:貨物の受取業務を外部に委託する場合は、「貨物の受取業務を円滑に遂行することができるものと認められる受託者」に委託することが必要です。行政機関は申請者が着地の受取業者を確保しているかどうかを委託契約書から判断しますので、口頭での合意だけでは不十分です。必ず書面で契約を交わしておくことが重要です。外航や国際航空の場合は、着地受取事業者との契約が英文で契約されていることが多いです。この場合や和訳が必要になりますのでご準備をお願いいたします。
事業の遂行能力
──次に「事業の遂行能力」について教えていただけますか?
阪本:事業の遂行能力は、申請者自身に求められる要件で、「純資産300万円以上」と「組織の要件」の2つがあります。さらに欠格事由に該当しないことも必要です。
まず純資産については、第一種と同様に300万円以上必要です。計算方法も同じで、「純資産=(会計上の)純資産-創業費その他の繰延資産・営業権-総負債」となります。申請時には直近3年分の貸借対照表(決算書)を提出して証明します。新設法人の場合は、設立時の資本金が300万円以上あれば、開始貸借対照表を提出することで代えられます。
ここで一つ重要なポイントですが、純資産で判断されるため、直近の貸借対照表上で純資産が300万円以上あれば、損益計算書上で赤字の会社であっても申請は可能です。しかしながら、継続的な赤字経営の場合、純資産が減少傾向にあると判断され、事業の継続性に疑義が呈されることもありますので注意が必要です。
──組織の要件とは具体的にどのようなものでしょうか?
阪本:組織の要件は「事業遂行に十分な組織を有すること」と「事業運営に関する指揮命令系統が明確であること」の2つです。
これは国土交通省が行う審査の中で、貨物利用運送事業の責任者と指揮命令系統を確認するためのものです。具体的には、貨物利用運送事業の担当役員と社内の担当部署を記載した組織図の提出が求められます。
それから、欠格事由についても第一種と同様に、申請する法人の役員または個人申請の場合は本人が一定の事情に該当すると許可が取れません。具体的には、1年以上の懲役・禁錮刑を受けてたり、懲役・禁固刑の執行を受けることがなくなった日から2年経過していない、過去に許可取消しを受けてから2年経過していない、申請前2年以内に不正行為をしたなどが該当します。
集配事業計画の適切性
──最後に「集配事業計画の適切性」について教えてください。
阪本:第二種貨物利用運送事業の特徴として、幹線輸送と集配を一貫して行うことがあるため、集配事業計画についても審査されます。ここが第一種貨物利用運送事業との大きな違いです。主に「集配営業所」と「集配事業者の体制」の2つの観点から審査されます。
集配営業所については、先ほどの営業所と同様のルールがあります。さらに、貨物の集配を行う地域を担当する営業所をそれぞれ特定する必要があります。例えば、関東地区の集配は東京営業所、関西地区の集配は大阪営業所が担当するといった形で明確にする必要があります。
──集配を外部委託する場合はどうなりますか?
阪本:集配を外部に委託する場合は、受託者の運営体制も審査対象となります。受託者が鉄道、航空または海上貨物の集配のために必要な業務運営体制を有していることが必要です。
例えば、集配事業計画には受託事業者の営業所名称やその所在地、取得している許認可の種類を記載するのですが、この情報が、受託者が国土交通省に申請している内容と矛盾していると、審査が中断し、国土交通省担当官より修正するよう補正指示が出てしまいます。
一方、トラック運送事業者が第二種貨物利用運送事業の許可申請を行う場合は、自社車両で集荷や配達を行うケースも多いです。この場合は、集配や配達を担当する営業所の情報を集配事業計画に記載します。自社車両と委託先の車両を併用する場合には、それぞれの責任分担についても明確にする必要があります。

まとめと業界の最新動向
──ここまで詳しく解説いただいた要件を満たせば、第二種貨物利用運送事業の許可要件を満たすことができるのですね。最後に、現在の業界動向や申請時の注意点などがあれば教えてください。
阪本:はい、ここまで説明してきた要件を満たせば許可取得は可能ですが、第一種に比べると要件が厳しく、わかりにくい部分も多いのが実情です。さらに、輸送モードによって国土交通省への提出書類が異なるため、注意が必要です。
業界の最新動向としては、物流の2024年問題の影響で、トラックでの長距離輸送が困難になっています。そこで内航船や鉄道を利用するモーダルシフトを行うために、一般貨物自動車運送事業者さんが第二種貨物利用運送事業許可取得を検討されるようになっています。また、荷主企業のコンプライアンス意識が変わってきています。荷主企業が委託先が適切な許認可を保有しているかを気にするようになり、その影響で、第二種貨物利用運送事業許可を急ぎで取得するケースもあります。
申請時の落とし穴としては、まず「利用の利用」の契約相手が適切な許可を持っているかの確認不足が挙げられます。また、集配事業計画の地域と実際の営業所の配置が整合していないケースも多く見られます。さらに、コンプライアンス体制が不十分なまま申請して、欠格事由の審査で躓くケースもあります。
これから第二種貨物利用運送事業に参入を検討している事業者の方々には、しっかりと事前準備を行い、必要に応じて専門家のサポートを受けることをお勧めします。特にこの1〜2年は審査基準が厳格化していますので、過去の経験だけでは対応しきれない部分もあります。
最後に強調しておきたいのは、許可取得はゴールではなくスタートだということです。許可取得後も適切な事業運営を継続し、定期的な報告義務を果たすことが重要です。持続可能な物流サービスの提供を通じて、荷主企業、そして最終的には消費者の皆さんに貢献できる事業者となっていただきたいと思います。
──非常に詳しくわかりやすい解説をありがとうございました。第二種貨物利用運送事業許可の取得を検討している事業者の皆様にとって大変参考になるお話だったと思います。
阪本:こちらこそ、お話する機会をいただきありがとうございました。物流業界は今、大きな変革期を迎えています。困難も多いですが、それだけにやりがいのある分野です。これから参入される方々の成功を心より願っています。
電話での問い合わせ
お電話でのお問い合わせは、平日の9:00~18:00の間、受け付けております。
お悩みについてすぐにお答えできるので、お電話でのお問い合わせをご利用いただく方も多いです。
- 都庁前オフィス(東京都新宿区):03-5843-8541
- 武蔵小杉オフィス(神奈川県川崎市):044-322-0848
お電話の際には「利用運送業のホームページを見た」とお伝えください。
なお、コンプライアンス上の理由で、匿名・電話番号非通知でのお問い合わせには対応しておりません。お問い合わせの際には会社名・お名前・ご連絡先などを伺っておりますのであらかじめご了承ください。
担当者不在時には伝言を残していただければ遅くとも翌営業日までに折り返し担当者よりお電話いたします。
※We apologize, but we are able to assist and operate in Japanese only.
メールでのお問い合わせ
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。必ず2営業日以内に返信しております。返信が届かない場合には、
- ご入力いただいたメールアドレスが間違っている
- 返信メールが迷惑メールフォルダ等に振り分けられている
- 返信メールが受信できない設定になっている
といった原因が考えられます。メールが届かない場合には、上記をご確認いただいたうえ、お手数ですが再度メールフォームよりお問い合わせください。
※We apologize, but we are able to assist and operate in Japanese only.