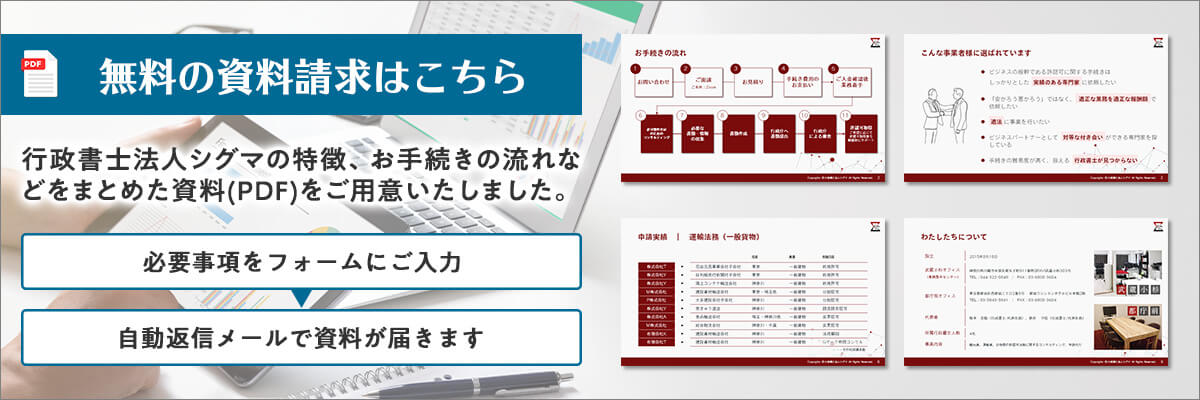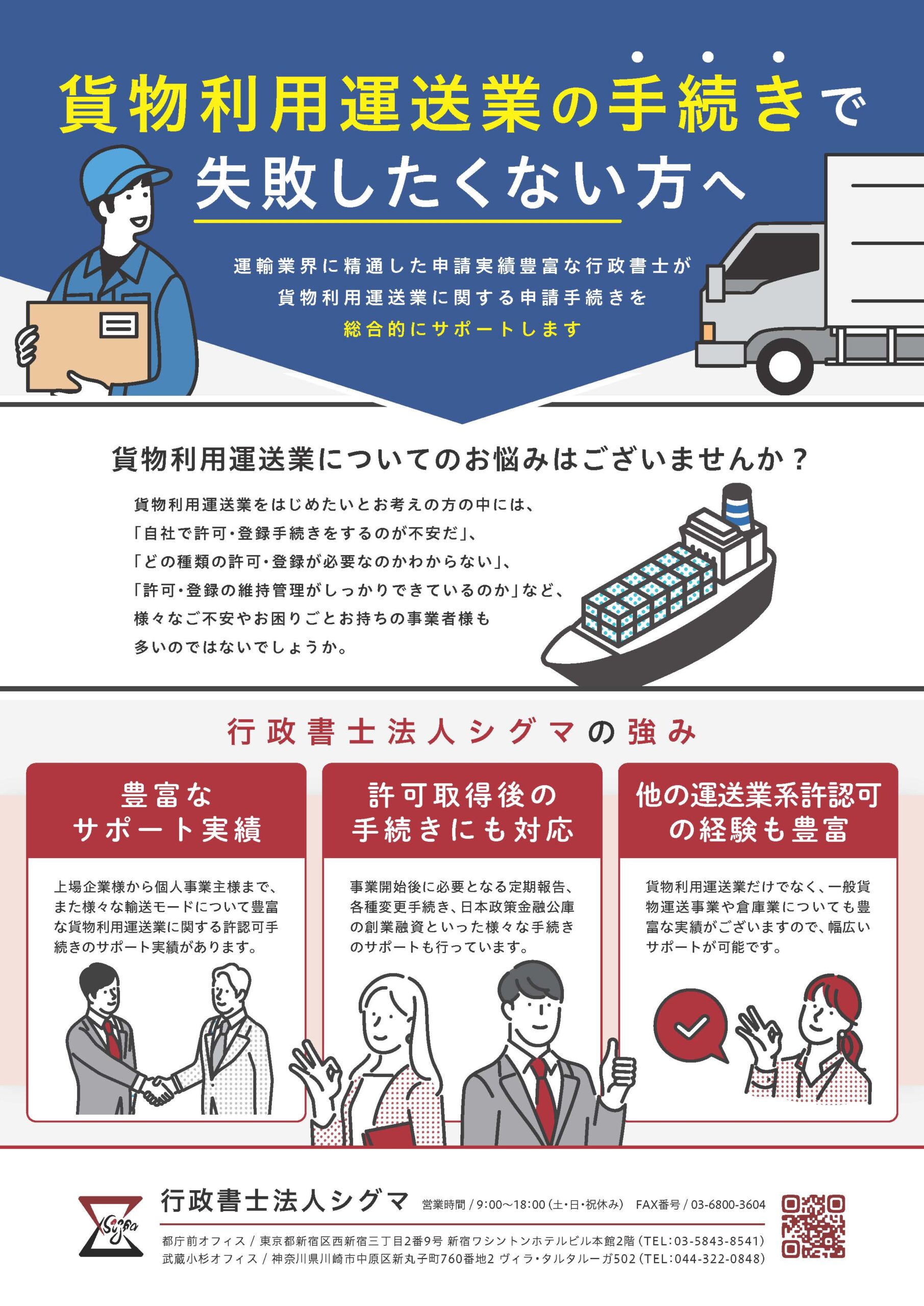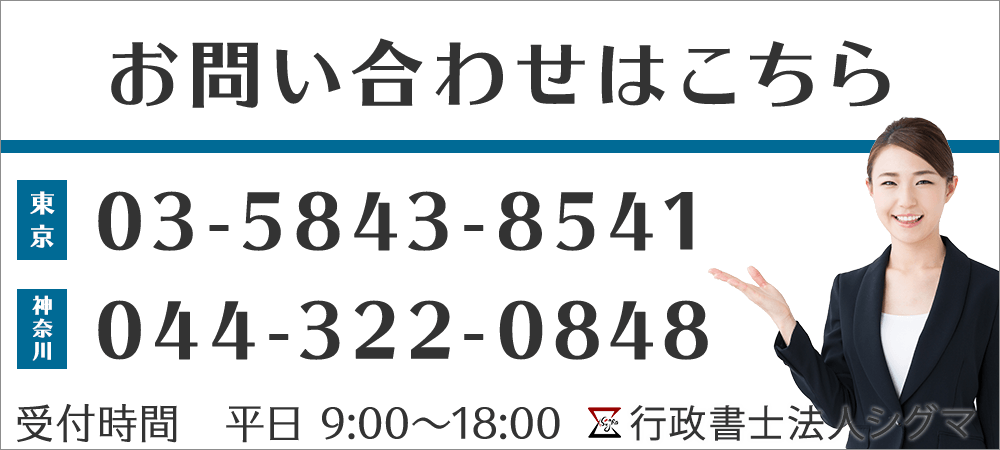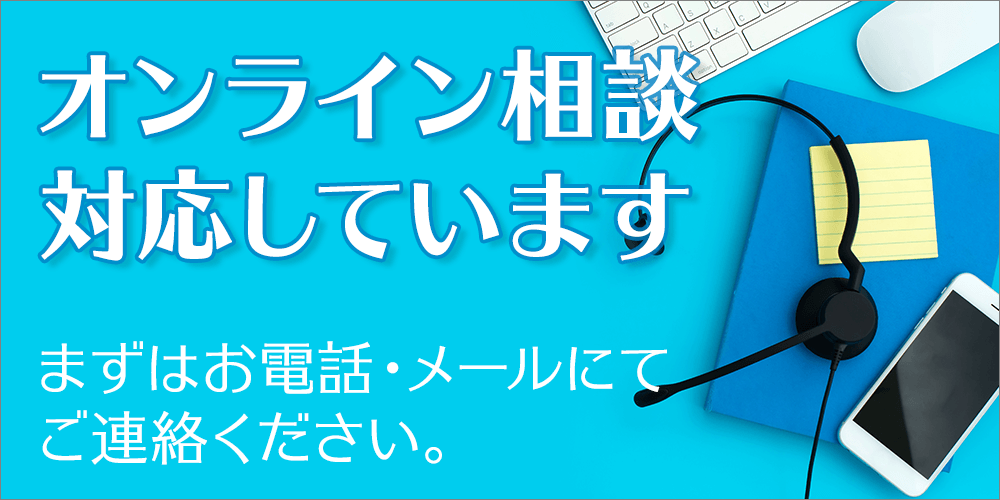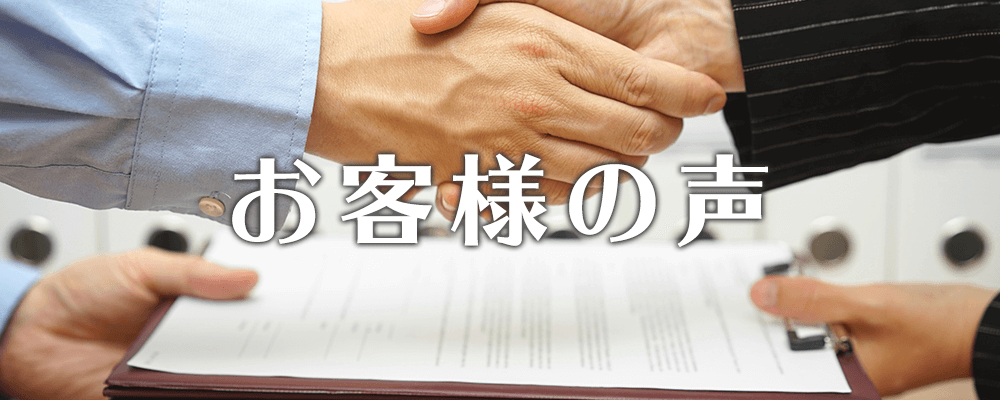今回は運送業界、特に貨物利用運送事業の許認可手続きを得意としている阪本浩毅氏にお話を伺いました。阪本氏は10年以上にわたり運送業界の許認可手続きをサポートし、多くの事業者の成功を支援してきた実績を持つ行政書士です。物流業界が変革期を迎える中、貨物利用運送事業の新たな可能性について詳しく語っていただきました。
貨物利用運送事業の基本的な仕組み
── まず基本的なことからお伺いしたいのですが、貨物利用運送事業とはどのようなビジネスなのでしょうか?
阪本:貨物利用運送事業は、荷主様から依頼を受けて、実際に貨物を輸送する運送業者を手配する事業です。私たちは業界用語で「実運送事業者」と呼んでいますが、この実運送事業者を利用して運送サービスを提供します。つまり、荷主様と実運送事業者の間に立って、物流をコーディネートする役割を担うのです。

── 自社では実際に運送しないけれど、運送の責任は負うということですね。
阪本:その通りです。基本的には自社で車両などを保有して物を運ぶわけではありませんが、荷主様との契約上は運送についての責任を全面的に負います。荷物の紛失や破損があった場合は、貨物利用運送事業者が責任を負うことになります。なお、例外として特定第二種貨物利用運送事業の場合には、一部自社の車両で集配業務を行うケースもあります。
── この事業を始めるには何か許可が必要なのでしょうか?
阪本:はい、貨物利用運送事業を行うには国土交通省から許可もしくは登録を取得する必要があります。事業の種類や扱う輸送方法によって、第一種貨物利用運送事業の登録や第二種貨物利用運送事業の許可など、取得すべき許認可が異なってきます。許認可の種類によって取得条件や可能な事業範囲が変わりますので、事業計画に合わせた適切な許認可を選ぶことが重要です。
── なるほど。では貨物利用運送事業はどのように活用できるのでしょうか?
阪本:様々な活用方法がありますが、これから私が関わってきたお客様の実例をもとに、代表的な活用パターンをご紹介したいと思います。
実運送業の準備期間としての活用
── 最初の活用方法について教えてください。
阪本:一つ目は「実運送業の準備期間としての活用」です。例えば、トラック運送業(一般貨物自動車運送事業)を始めようとすると、相当なハードルがあります。具体的には、営業所の確保はもちろんのこと、最低5台以上の事業用車両、それらを停める車庫、運転手の休憩・睡眠施設の設置、運行管理者や整備管理者といった専門資格を持つ人材の確保、そして一定以上の自己資金など、多くの要件をクリアしなければなりません。
── それはかなりハードルが高そうですね。
阪本:その通りです。実際に私のクライアントの中には、初期投資だけで数千万円を要した事業者もいらっしゃいます。一方、貨物利用運送事業は比較的取得要件のハードルが低いのが特徴です。例えば、第一種貨物利用運送事業であれば、適切な事務所と管理体制、そして純資産額ベースで300万円以上の財務基盤があれば始められるケースもあります。
── 具体的にどのように準備期間として活用するのでしょうか?
阪本:例えば、荷主様からの依頼はあるものの、すぐに実運送業の許可を取得するための条件を揃えられない場合、まず貨物利用運送事業者として事業を開始します。その間に収益を上げながら、車両や施設、人材を徐々に確保していき、条件が整ったタイミングで実運送業の許可申請を行うというステップアップの方法です。
── 具体的な事例はありますか?
阪本:はい。例えば、ある物流ベンチャー企業は創業時に資金が限られていたため、最初に第一種貨物利用運送事業の登録を取得してスタートしました。荷主企業と協力して3年間で事業基盤を固め、その後一般貨物自動車運送事業の許可を取得して自社車両での配送も始めました。現在では両方の事業を組み合わせて、効率的な物流サービスを提供しています。
また別の例では、運送業に転身したいと考えていた元商社マンの方が、いきなり大きな投資をするリスクを避けるため、まず貨物利用運送事業から始めて市場を調査しながら実績を積み、2年後に実運送業に移行したケースもあります。
非収益事業の収益化
── 次の活用方法についてお聞かせください。
阪本:二つ目の活用法は「非収益事業の収益化」です。物流に関連する事業を行っている方の中には、運送部分は単に運送会社を紹介するだけで終わり、そこからは収益を得ていないという事業者様も多く見られます。例えば、引越し業者の紹介サービスや、物流コンサルティング会社の取次事業などがこれに当たります。
── それが収益化できるということですか?
阪本:その通りです。そういった事業者様が多くの荷主様とのコネクションをお持ちであれば、貨物利用運送事業の許可・登録を取得することで、これまで収益につながっていなかった運送部分からも利益を上げられるようになります。
実例を挙げると、ある引越しポータルサイトを運営する会社は、以前は単に引越し業者を紹介するだけでしたが、第一種貨物利用運送事業の登録を取得後、自社で運送契約を結び、複数の実運送業者に発注することで、紹介料だけでなく運送差益も得られるようになりました。その結果、売上が約30%増加したという事例があります。
── それはビジネスモデルとして大きな変化ですね。何か注意点はありますか?
阪本:重要な注意点として、収益増加の一方で、荷主様に対する運送責任を全面的に負うことになる点が挙げられます。輸送中の事故や遅延、荷物の破損などが発生した場合は、貨物利用運送事業者が一義的に荷主に対しての運送責任を負うことになります。そのため、適切な運送保険への加入や、信頼できる実運送業者の選定が非常に重要です。実際に、十分な対策を講じずに事業を始めたために、大きな賠償責任を負うことになった事例も残念ながら見てきました。
── 最近の業界動向としてはどのような変化がありますか?
阪本:近年ではEC市場の拡大に伴い、小口配送の需要が急増しており、こうした配送手配サービスを行う事業者様にとっては、貨物利用運送事業がさらに重要になっています。また、運送業界全体でドライバー不足が深刻化する中、荷主企業は物流の効率化を強く求めていますので、複数の運送会社を適切に組み合わせて最適な物流を提案できる貨物利用運送事業者の価値は高まっています。
輸送の効率化
── 三つ目の活用方法である「輸送の効率化」について詳しく教えてください。
阪本:貨物利用運送事業の大きな特徴は、原則として自社では荷物を運ばないという点にあります。これは一見するとデメリットのように思えるかもしれませんが、実は大きな強みになります。なぜなら、自社の車両や設備に縛られることなく、荷主様に対して最も適した輸送方法を柔軟に提案できるからです。
── 具体的にはどのような効率化が可能なのでしょうか?
阪本:例えば、荷物の量や種類、配送先、納期などに応じて、トラック、鉄道、船舶、航空など様々な輸送手段を組み合わせたり、複数の運送業者の強みを活かした配送ルートを設計したりすることができます。特に第二種貨物利用運送事業の許可を取得している場合は、複数の輸送機関を組み合わせた複合一貫輸送のコーディネートが可能になります。
具体例を挙げると、ある地方の製造業者様は、従来トラックのみで行っていた関東から九州への定期配送を、当社のコンサルティングを受けて貨物利用運送事業者としての許可を取得後、トラックとフェリーを組み合わせた輸送に切り替えました。その結果、燃料コストを約20%削減し、CO2排出量も大幅に削減することに成功しています。
── 環境面での配慮も可能なのですね。最近の物流における課題はどのようなものでしょうか?
阪本:現在の物流業界では、ドライバー不足や燃料コストの高騰、そして環境負荷の低減という三つの大きな課題に直面しています。貨物利用運送事業者は、こうした課題に対して柔軟な輸送方法を提案できる立場にあります。例えば、複数荷主の貨物を積み合わせる共同配送や、鉄道や船舶などよりCO2排出量の少ない輸送手段の活用など、効率化と環境対応を両立させる提案が可能です。
── それは今後ますます需要が高まりそうですね。実務上の落とし穴や注意点はありますか?
阪本:最も注意すべき点は、適切な輸送手段の選定と、緊急時の代替手段の確保です。特に複数の輸送手段を組み合わせる場合、一カ所でトラブルが発生すると全体に影響が波及しやすくなります。例えば、ある食品メーカーの事例では、船舶と鉄道を組み合わせた輸送計画で、台風による船舶の欠航に対する代替手段を準備していなかったために、納期遅延が発生し、冷蔵食品の品質問題にまで発展してしまったケースがありました。緊急時の代替計画(コンティンジェンシープラン)の策定は必須です。

まとめと今後の展望
── 最後に、貨物利用運送事業の今後の可能性や展望についてお聞かせください。
阪本:このように貨物利用運送事業は、実運送業とは異なる様々な活用方法があります。特に近年のデジタル化の進展により、物流の「見える化」や「最適化」がさらに進んでいくと考えられます。貨物利用運送事業者は、荷主と実運送事業者をつなぐプラットフォームとしての役割を担い、物流DXの中心的存在になる可能性を秘めています。
私の見立てでは、今後5年間で物流業界は大きく変わります。運送業界の再編が進み、中小の実運送業者は淘汰される一方で、多様な輸送手段を組み合わせて最適解を提供できる貨物利用運送事業者の重要性はさらに高まるでしょう。特に環境配慮型の輸送手段への転換や、荷主企業のサプライチェーン効率化のニーズを満たせる事業者が競争優位に立つと予測しています。
── 最後に、これから貨物利用運送事業を検討している方へのアドバイスをお願いします。
阪本:貨物利用運送事業は参入障壁が比較的低い一方で、適切な知識と戦略がなければ成功は難しいビジネスです。まずは自社の強みと弱みを正確に把握し、差別化できるサービス領域を明確にすることが重要です。また、許認可取得は業務の入り口に過ぎません。信頼できる実運送業者のネットワーク構築や、リスク管理体制の整備、そして何より荷主企業のニーズを深く理解することが成功の鍵となります。
貨物利用運送事業を活用できるのではないかとお考えの事業者様で、許認可手続きについてご不安やお悩みがございましたら、専門家への相談をお勧めします。正しい戦略と準備があれば、この事業は大きな可能性を秘めています。
── 貴重なお話をありがとうございました。
阪本:こちらこそ、ありがとうございました。
電話での問い合わせ
お電話でのお問い合わせは、平日の9:00~18:00の間、受け付けております。
お悩みについてすぐにお答えできるので、お電話でのお問い合わせをご利用いただく方も多いです。
- 都庁前オフィス(東京都新宿区):03-5843-8541
- 武蔵小杉オフィス(神奈川県川崎市):044-322-0848
お電話の際には「利用運送業のホームページを見た」とお伝えください。
なお、コンプライアンス上の理由で、匿名・電話番号非通知でのお問い合わせには対応しておりません。お問い合わせの際には会社名・お名前・ご連絡先などを伺っておりますのであらかじめご了承ください。
担当者不在時には伝言を残していただければ遅くとも翌営業日までに折り返し担当者よりお電話いたします。
※We apologize, but we are able to assist and operate in Japanese only.
メールでのお問い合わせ
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。必ず2営業日以内に返信しております。返信が届かない場合には、
- ご入力いただいたメールアドレスが間違っている
- 返信メールが迷惑メールフォルダ等に振り分けられている
- 返信メールが受信できない設定になっている
といった原因が考えられます。メールが届かない場合には、上記をご確認いただいたうえ、お手数ですが再度メールフォームよりお問い合わせください。
※We apologize, but we are able to assist and operate in Japanese only.